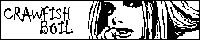クリスマスマジックを信じていたのは子供の頃の話。
感謝祭が過ぎると、何処も彼処も赤と緑に街は染まる。
あの頃、小さかった私はサンタさんが読めるようにと、毎年欲しいものをクリスマスカードに書いて、ツリーの下に置いておいた。
カードはクリスマスの朝、プレゼントに代わっていた。そしてサンタさんからの
「ありがとう。メリー・クリスマス!」
との置手紙を見る瞬間が楽しみで、その日だけは早起きした。
で、今はというと、私はクリスマスだというのにオフィスでの残務に追われていた。
あと三十分でこれを終わらせたら帰宅し、用意をして八時には 『ニューヨークエブリデー』の社主、サリンジャー女史主催のクリスマスパーティーに行く事になっていた。
この国ではクリスマスは家族と一緒に過ごすのが一般的なので、恋人の岸さんもカリフォルニアの家族のもとに戻っていた。
「仁神堂、もう帰っていいわよ。」
国民の休日の夜までつき合わせたら悪いような気がして、私は午後から彼に半日休暇を与えた。
この男が、今夜どこで誰と何をするのか知った事ではないけれど、彼は潔く、
「そうですか。有り難う御座います。」
と軽く一礼して帰宅した。
家に帰ってパーティーの支度にとりかかった私に、一つ目の悪夢が襲った。
寝室の鏡台の上を片付けようとして、隅に置いてあった香水を肘でぶつけて落としてしまったのだ。
板張りのフロアーに、紫色をした硬そうな硝子の容器は意外にも脆く砕け、ベッドルームの鏡台のあたりに強烈な匂いを充満させた。
いつものように使用人を呼ぼうとして、休暇を与えたのだと思い出す。
仕方なく自分でガラスの破片を拾い、雑巾を探し出して板張りの床を拭いた。
微量で香りの丁度よい液体は、大量だと匂いが強すぎて人を酔わせる。
時間が無いので、適当に水拭きしておいたのがまずかったらしい。
「きゃあっ。」
今度は立ち上がろうとしてコントのお約束の如く、無様に自分で拭いたばかりの床に滑って転んでしまった。
その刹那、右足首に激痛が走った。
二つ目の悪夢であった。
「……なんてついてないのかしら…。」
パーティーまであと二時間半。
シャワーを浴び、化粧をして、イブニングドレスに着替えなければならないのに、私はどうやら足を痛めてしまったらしい。
自分の情けなさに脱力し、そのまま暫く床から起き上がれなかった。
「どうしよう。」
私は頭を巡らせた。
日本にいる祖父の代わりに会社を代表してこのパーティーに出席するのは今年が初めてだ。
サリンジャー女史を初め、各界の著名人やその家族も顔を出す。
出席できなければ、会社がどれだけ損をするだろうか。
冷静に考えなければ。
私はよろよろと立ち上がり、びっこを引きながらも歩いて数歩先のベッドの上に腰を下ろした。
三十分後。
結論が分かりきっている事を考えるのも億劫になって、腫れだした足首を放置したまま私は仰向けに寝転がり、高い天井を眺めていた。
用意にとりかからなくてはならないのに、時間だけが容赦なく過ぎていく。
と、突然ベッドの横の電話が鳴った。
家にいるはずの仁神堂の携帯からであった。
「もしもし。…何かしら?」
どうせ用件は残務についてか、明日以降のスケジュールについてなのだろう。
仕事以外で私に電話してきた事など一度もなかった。
私は暗い声で電話に出る。
今は誰とも話す気分にはなれない。
特に、仁神堂とは。
「社長、突然のお電話申し訳ございません。ただ、明日のNY発成田行きのJNAのフライトが雪の為キャンセルになりそうですので、明後日に変更した事だけをお伝えしようと思いまして。」
案の定な用件だった。
わざわざ休みを与えたのに、この男は家で仕事をしている。
「…そう。…分かったわ。」
力なく答えたが、仁神堂は続ける。
「明後日帰国してからスケジュールがやや過密にはなりますが、その分明日はごゆっくりお休みください。」
「…有り難う。」
暫しの沈黙。
「…それでは社長、失礼致――。」
と電話を切ろうとした仁神堂を、何故か頭より先に口が、
「ちょっと待って!」
と言って止めてしまった。
ああ、私は何をしているのかしら?
「……何か御用でしょうか?」
訝しげな響きを持った声が電話先で問う。
今、私の周りで頼れる人間はこの男を置いて他にいなかった。
私の足首について、何か良いアドバイスをくれるかもしれない。
「ちょっと…十分だけでいいから、来てくれないかしら。」
一か八かで聞いてみた。
セントラルパークの傍のホテルを家代わりにして住んでいる彼の所から、私のブロードウェイ沿いにあるコンドまで車でそう遠くは無い。
仁神堂は何故わたしが呼び出すのか理由も問わずに、
「……畏まりました。すぐに参ります。」
と静かな声で電話を切った。
「どうなされたのですか、社長。」
私の姿を見た、仁神堂のやけに落ち着いた開口一番の言葉であった。
私は足が痛くて何もやる気が起きず、家着姿でずっと右足を投げ出し、左膝を抱えたような体勢のままベッドの上でうずくまっていた。
急いで来たからなのか、仁神堂はいつもの埃一つ無いカチッと決まったスーツ姿とは異なって、 黒い髪は無造作のまま、大きめの白いTシャツとスェットパンツにジャケットを羽織っている。
心なしか息が弾み、肩がいつもより忙しなく上下しているように見えた。
「仁神堂…。」
もしかして、私の為に急いで駆けつけてくれたのかしら…?
いや、そんな筈はないわね。
「足を、どうかなされたのですか?」
言いながら仁神堂は大股で近寄ってきてベッドの前でひざまずき、確認するように腫れ上がった私の足首に手を触れた。
外の冷気で冷えたらしい、脈の通っていないような冷たい指先が何度も私の足首の上を這った。
軽く押されると、耐え難い激痛が走った。
「つっ。」
「捻挫…よりひどいですね。でも、折れてはいないようです。脱臼なされたのかもしれません。」
「脱臼…?。」
「氷は、台所にありますね?」
「ええ…。あの――。」
「まず冷やします。お話は、その後で。」
仁神堂は私が言いかけた言葉を落ち着いた声で遮り、立ち上がってキッチンの方へと姿を消してしまった。
「今夜は、確かサリンジャー女史のクリスマスパーティーでしたね。」
仁神堂は私に氷の入った袋を渡しながら真顔で聞いてきた。
私は無言で頷く。
「御出席なさるおつもりでしょうが、その足では無理ではないでしょうか。」
「でも、私が行かなかったら会社が…。」
「社長。私が今から女史に連絡を入れておきます。ドクター松山にも明朝一番に足をみて頂くよう予約を入れておきますので、明日からの日程の為にも、今夜はどうか安静にしていてください。」
「そんな事出来ないわ!」
と口に出す暇もなく。
手で素早く私の動きを制して、仁神堂はジャケットから携帯を取り出し電話をかけに私の寝室を出た。
ベッドに再び取り残された私の目の裏には、初めてみる仁神堂の私服が焼きついていた。
普段着の仁神堂は、私が今まで感じた事もない強い男の精気を匂い立たせていた。
一部の隙も無いスーツ姿に比べ、ラフな格好の彼は実に男らしい精悍さに溢れていて、私好みの苦味走った魅力的な男に映った。
嫌だわ、私った ら…。
「眼科に行かなくちゃ。」
苦笑し声を出して、自分を否定してみた。
数分後。
「明日朝九時に予約を入れておきました。ドクター松山のオフィスはご存知ですね?あと…キッチンを勝手に詮索いたしました。赤ワインはお嫌いでしょうか。」
豊かに香る赤い液体が、指紋一つない透明に輝くグラスに半分注がれてある。
ベッドの上の私の手に持たせながら、仁神堂は聞いてきた。
「いいえ。ありがとう。」
一口つけると、その濃厚な葡萄の香りが口いっぱいに広がった。
「ごめんなさいね。クリスマスだっていうのに呼び出してしまって。しかも雑務までさせてしまって。」
ベッドの横に設置された円形テーブルの椅子に腰を下ろしながら仁神堂は自らもワインに口をつけた。
「これも仕事ですし、今夜は別にこれといった予定は御座いませんので。」
……沈黙。
この男とはどうも仕事以外の会話が弾まない。
でも、そういえば、この間家族はいないと言っていたわね。
…ついでに恋人も。
今年、クリスマスを独りで過ごさなければならないのは私も同じだけれど。
「……社長。質問をしてもよろしいでしょうか。」
ワインをテーブルに置いて、静かに仁神堂が訊ねてきた。
顔は、いつも通り真剣。
ただ、ラフな格好が違う雰囲気を醸し出している。
「えっ?ええ。何かしら?」
「私の顔に、何かついているのでしょうか?」
「は?え?いや、いつもと仁神堂の雰囲気が違うから…。」
私は指摘されるまで、自分が仁神堂を凝視していた事に気付かなかった。
魅力的に見えるだなんて口が裂けても言えないわ。
仁神堂は再びワインに口をつける。
「それは…、どういう意味なのでしょう?」
意味深に方眉を上げて、仁神堂は問う。
「どういう意味も何も、そういう意味よ。」
私は苦笑しながら肩をすくめて言った。
仁神堂は何故かかけていた眼鏡をはずして、テーブルの上に置く。
「社長は先日……。」
言いながら額にかかっていた前髪を無造作にかき上げ横を向く。
「私にジェット機内での出来事についてお訊ねなされましたね?」
何を言い出すのかしら、この男は?
「そんな事聞いたかしら?」
と、しらを切った私を無視して仁神堂は続ける。
「その時の私の答えを、覚えておられますか?」
端正な顔の、茶色くて澄んだ二つの怜悧な瞳に射られて、私は一瞬、瞬きを忘れてしまった。
今夜の私は、何かがおかしい。
いつものように強がりや皮肉で言い返すことが出来ないなんて、絶対におかしいわ。
「お、覚えてないわ。」
「そうですか。」
また一口ワインに口をつけて仁神堂は優雅にグラスをゆする。
やはり仁神堂は眼鏡が無い方が似合っている。
この見慣れない普段着も、彫りの深い整った顔立ちも、この寝室という空間にこのシチュエーションも、足を痛めて精神的に弱っている私の心を惑わせるのに充分な要素をもっていた。
…なんて言い訳じみているわね。でも……。
「仁神堂。」
「はい?」
「実行…してもいいわよ。」
仁神堂は無言で小首を傾げる。
私の苛立ちが募った。
分かりきっているくせに、この男は…。
「だから、その、セクハラに値しないのであれば、もう一度試してあげてもいいわよ。」
「……。」
仁神堂はワインを置いて、私を見下ろした。
硝子細工のような薄茶色の瞳が艶めいている。
それでも、何も言わないでじっとしていた。
「だから、こう!」
と、私は仁神堂のTシャツの胸倉を掴んで引き寄せた。
微量ながらに、あのコロンの匂いが漂う。
仁神堂の匂い。
それは、この間のジェットの時のような、優しくて、丁寧で、心地好いキスだった。
でも、今回ばかりは私の理性がそれだけで済ましてくれそうになかった。
足首は痛いのに、体の他の部分は快楽で疼きだす。
首に回した手からは仁神堂の、微かに湿っている熱い体温が伝わった。
「今回は…これだけでは済まないかもしれませんよ…?」
息も切れ切れのキスの合間、仁神堂は顔を上げた。
その顔には、複雑な色が浮かんでいた。
無口、無表情の奥には感情があるという事実に、今更ながら気付いた。
「……やめないで。」
もう、どうでも良かった。
ただ、やめて欲しくなかったから。
三つ目の悪夢。
クリスマスの今夜、私は秘書の仁神堂 浬と一夜を共にしてしまった。
注:仁神堂の聖夜バージョンをご覧になりたい方のみ下(↓)をクリックしてください。
『聖夜XXX』へGO