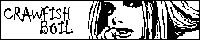その際は大変お世話になりました彼の方に、お礼と尊敬の意を込めまして、このページと下記の小説を捧げます*
良識のある18歳以上の方のみお楽しみ下さい
FC2ブログランキング
We Love 木蘭!(シリーズ)
絶世の美人と噂の松田屋の格子、木蘭のぶっとび一話完結日記シリーズ。彼女を愛するあらゆる階層の顧客達。いわゆるラブラブあまあまで、ラブコメ調の逆ハー状態(?!)なのでそっち系が苦手な人は今すぐ回れ右!!不定期更新です。
未年の朝(長編)
ふつーのOL増子明日香22歳は、ある日突然江戸初期へタイムトリップしてしまった!!とある侍に拾われた明日香だけど…。シリアスな時代物ではありません。R18の、和風ラブコメです。時代考証等あやふやで適当なので、シリアスな時代ものがお好きな方はお引き帰しくだされ。
FORTUNATE (短編)
アルバイトの早乙女晃(ひかる:♂)は会社のキャリアウーマン、かほり(♀)と関係を持っています。ベッドの上で積極的な彼女の言いなりになっている彼ですが…。女性が攻め、男性が受身のお話です。年下攻めや、そういうシチュエーションが苦手な方にはちょっと辛いお話かも?!
風に揺らめく木 (短編)
松田屋の天神、楓と名門有馬家の四男坊惟宗のお話。『楓道』番外編、二人の激しい一夜を書いてみました。もちろん、R18です。喧嘩ばかりの二人ですが、 体の相性はいいようです。本編を読まなくても充分堪能できるようになっております。
手白香(てしろか)の姫 (短編)
不弥国の姫、手白香は父王の敵を討つ為敵国の奴王を殺そうと試みるが…。古代+R18+恋愛の三つを組み合わせてみました。密室の中で繰り広げられる男女の性をとくとお楽しみください。
仁神堂(にがみどう)聖夜X (短編)
本サイト『仁神堂(にがみどう)シリーズ』の特別エッチバージョンです。話は本編の第四話『聖夜と悪夢』の直後です。本編をお読みになってからの方が解り やすくなってはいますが、このままでも充分堪能できます。でも、仁神堂に対し清いイメージを持ち続けたい方はお引帰しくださいね。

手白香(てしろか)の姫
手白香の策は失敗に終わった。
永年にわたって続けられた戦は手白香姫(てしろかひめ)が十三になった年、皆既日食による大飢饉などの災いが両国を襲い、納得しないまま奴国側の要求を受け入れ一旦和平を結んだ。
多くの血を流し、命を失ったことにより蓄積されてきた憎悪はそう簡単に消せるものでもなく、両国間の関係はぎこちなく不安定なまま数年が過ぎた。
齢十六になった手白香姫は不弥国の王である異母兄の為、奴国の暗殺計画によって命を落とした前王の父の為、憎き奴国王を暗殺する駒となる事を自ら志願した。
不弥国から奴国王に和平の印として班布と生口(奴隷)を献上する為の使者となり、奴国に潜入して奴国王暗殺を試みた。
足元に何かが這っている気配を感じ、目を覚ました。
狭い竪穴式の住居の中央に建つ、大きな柱に括り付けられた縄で両手を縛られていた。
綺麗に結われていた筈の髪の毛は解かれ、豊かな黒髪が真っ直ぐ腰まで垂れている。
着ていた男物の横幅衣も膝上まで捲られて、足を大きく開かされていた。
下を見て見ると、手白香の左足元に男がうずくまり、踝辺りを舐めていた。
「な、何をしている!!」
右足を使って男を蹴り上げようとした手白香の細くて白い足を、男は左手でいとも簡単に掴んで止めた。
「何を、だと?罪人に罰を与えている。」
顔を上げた男を見て、手白香は息を呑んだ。
両方の米神から眉間に向かって両眉の上に、幾何学模様の刺青が入っていた。
この国でそこに刺青を入れる事の出来る男は一人しかいない。
その顔は恐ろしいほど整っていて、女と見まごう程妖艶な美しさと細身で引き締まった体を華麗に合わせ持った若者であった。
……手白香はこの男をつい先ほど殺そうとして、しくじった。
「奴王。あっ、あなたは……何をっ…。」
滅茶苦茶に振り上げようとして宙を切った両足を、男は腕力でねじ伏せて更に足を広げさせた。
無言で王は手白香の太股の内側を舐めながら這い登っていく。
衣を腹部の上まで捲った。
「あっ…。」
手白香の女が露わになった。
王はちらり、とそこに目をやると、自身の足で彼女の両足を開いたまま固定し、半身を上げた。
美しい顔が近づく。
この秘部を異性に見られたのも、触られるのも生まれて初めてだった。
王を殺すと決意した時点で自分の命は捨てたも同然であった。
誰かの妻となる運命も捨て、祖国の為にと自ら暗殺者となった。
玉砕すれば、塵の如く己の手でその人生を終わらせるつもりであった。
なのにこうして陵辱されている。
悔しさで、涙が一滴出た。
王は首筋に痕が残るほどしつこく口付けをしてきた。
「罪人なれど、ここは綺麗だ。」
首を舐めながらも王の白い手が、手白香の下の茂みをまさぐる。
「あっ…。」
花のおしべのような突起に指があてられた。
軽く左右に擦られると、四肢が快感でビクッ、と反応した。
「気持ちがいいのか。」
妖艶な顔に意地の悪い笑みを浮かべながら奴王は熱く耳元で囁いた。
手白香は首を回して横を向く。
「私を、殺せっ。」
蕩けそうな下半身に飲み込まれそうになりながらも、振り絞って声を出した。
王は花園に沸いてきた蜜を中指ですくった。
糸を引いたそれを手白香の目の前でぺろり、と舐めてみる。
「もう濡れ始めているな。」
「ああ……あぁぁぁんッ。」
声なんて出すまい、と思っても、奴王に親指で突起をくすぐりながら手の平で花園全体を震わされると、喘ぎ声が出た。
「ああっ、ああっ、ああっ…。」
手白香は木の柱に爪を立てて懸命に堪えた。
しかし長い事蜜で滑る手を充てられたまま細かい振動で苛められていると、あっけなく達してしまった。
「はぁぁぁぁ…。」
深く息を吐くと、体の緊張が解けてぐったりとなった。
白い快感の渦の中で、手白香は思った。
まだ、この男を討つ機会はあるのかもしれない、と。
「なぜ俺がお前の正体を見破ったか判るか?」
王は先ほどと同じ体勢のまま、手を手白香の顎に置いて訊ねた。
手白香は無言で王を睨みつける。
「お前は男の服を着て、薬草を飲み声すらも低く潰していた。俺はおまえが短刀を抜き出す前から見破っていたぞ。…何故だか判るか?」
艶めいた形の良い唇が無理やり手白香の唇に合わさった。
湿っぽく味わう。
「不弥国王の文とやらを読み上げていた時……。」
接吻の合間、王は話を続ける。
「俺はお前のある所を見つめていた。……班布を持つ男の手が、このように手入れのされた白くて細いものの筈がないとね。」
手白香は奴王に抗うでもなく、人形の如く無表情で話を聞いていた。
「不弥国の現王の異母妹、手白香姫の噂は隣国でも有名なのでな。」
縄で縛られている手白香の手の指を一本一本口に含む。
「実際…お目見えするのは初めてだが。」
また、王の手が彼女の茂みの中に分け入った。
「……ぁあ……。」
先ほどの快感でヌルヌルと蜜が溢れている秘部の、禁断の小穴に指が侵入した。
「男装をしていても、噂に違わぬ美しい姫だ。……ここへの侵入は初めてか?」
「はぁっ…。」
指を一本入れられると、思わず声が出た。
王は指を奥深くへ突き刺しながらも、親指で上の芽を優しく擦る。
指が中で律動的に動かされ、かき回される。
(奴国の王よ、お前を……絶対殺してやる……!!)
喜び始めている己の下半身が憎い。
流れ続ける涙を拭う事も出来ず、手白香は頭の中で叫んだ。
噛み締めた唇から血が滲む。
王はそんな彼女の姿を見て驚いたように目を開いた。
冷たく微笑む。
「ほう?俺がそんなに憎いか?」
体を手白香の足元に移動させ、彼女の尻を持ち上げた。
蜜の溢れた花園が、奴王の目の前にあった。
王は指で左右に手白香の花園を広げ、まじまじと見つめた。
「ここは俺を憎んでいないようだぞ。」
低く囁きながら熱い息を秘部に吹きかける。
そして、溢れた蜜を舌でぺロリと舐めとった。
「ううっ…ああっ。」
快感で足に力が出ない。
舌は容赦なく蜜を舐め続け、手白香の内襞を上下に移動し、味わった。
そして、一番敏感に感じる突起の芽を舌先でちろちろと突付いてきた。左右上下に動かされると、快楽の波がまた大きく打ち寄せる。
「ああぁぁっ…!!。」
絶叫ともいえる声を上げて、手白香は力尽きた。
奴国の王は毎日決まった時間に手白香を訪れた。
彼女に喜びを与えても、決して自身が果てることもなく、ましてや手白香を抱く事もなく、彼女独りに快楽を与える事のみにとどまった。
彼女は縄で腕を縛られたまま、決まった時間に食事を与えられ、王が訪問する前と後の二回、湯で体を拭かれた。
もちろん、秘部も綺麗に拭かれた。
いつも手白香の世話をする若い男は、手白香の質問に答えることもなく、無言で作業を行った。
暗い住居で独り手白香は考えていた。
兄上は何をしているのだろう。
失敗をした手白香は、もう国に戻る事は出来ないのかもしれない。
ならば、せめて奴国の王を殺して自分も死のう。
この屈辱に耐えて、耐えて、耐え抜いて機会を窺う。
「不弥国が兵をあげた。だが俺は急遽お前の兄に使者を送り、お前が生きていて、奴国の人質となっている旨を伝えた。」
全裸にされた手白香の体に手を這わせながら奴王は低い声で伝えた。
いつも美しく結われている髪を下ろして、上半身裸の奴王は今日も日課の如く手白香を訪れていた。
捕まってからもう、七日が過ぎた。
「今、返事を待っている。不弥王がお前を見捨てて戦に持ち込もうとするならば、戦おうと思う。」
赤子のように手白香の白い乳房の、仄かに赤く色付いた頂を吸いながら体を寄せてきた。
「いい匂いだ。白くて美しい手をもった、香り良い姫…か。」
固く膨張した自身を手白香の足に押し付ける。
しつこく頂を吸いながら、両手は彼女の細くて凹んだ腹部の上を撫でる。
「信じられないかもしれないが、俺は和平を望んでいるのだよ。」
妖艶な瞳が間近で真っ直ぐ手白香の目を射た。
「お前の国との永年の戦は元はといえば俺の父…前王がしかけたものだ。俺は自分の国の民が平和で豊かになれるのなら、それでいい。戦など無駄だと思っている。」
「きれい事を言うな。お前らは私の父を殺した。私達の民を傷つけた。無数の命がおまえらのせいで失われた。」
強い声音で言い返した手白香を、王は立ち上がって冷たく見下ろした。
ゾッとするほど美しい。
「そして、お前らも俺の民を殺した。戦とは、そういうものだろう?侵略するか、されるか。生きるか、死ぬか。それしかない。」
王は腰に巻いていた布を取り去った。
手白香の目の前に形よく怒張した男が現れた。
手白香が生まれて初めて見る男であった。
体の一部なのに生命を誇っていて、熱い生気を感じる。
王は手白香の頭を掴んで、自身を近づけた。
手白香は鼻先にあてられたそれをどう扱えば良いのか分からず、困った顔をした。
暫く見つめていると、
「舐めろ。間違っても噛み切ろうなんて馬鹿な事は考えるな。」
と、声が上から降ってきた。
おずおずと舌を竿の中央に這わせてみる。
少し汗ばんだ味がしたが、構わず舐め続けた。
王はからだの位置をずらして亀頭を口元に あてがった。
先端の割れ目をちろちろと堪能していると、小穴から透明な何かが滲み出た。
糸の引くそれを舐め取る。
そして、柔らかい頭部全体を口に咥えてみた。
「はぁ……っ。」
軽く吸ったり、口の中で舌を笠の部分に這わせたりしていると、奴王は吐息を漏らした。
手白香の頭を左手で押さえつけたまま、右手で自身の竿の部分を握り上下に擦りだした。
手白香も強弱をつけて吸い続けた。
奴王の手はどんどん速くなり…。
「………ぁっ……。」
快感の声を上げたかと思うと、口の中のものがビクン、と波打ち精が放出された。
彼女の口の中に苦酸っぱい何かが勢いよく飛び出し、広がる。
全部出し終えると奴王は手白香を解放した。
「おえっ。」
口の中のどろどろしたものをどうしていいのか分からず、彼女は横を向いて吐き出した。
「………。初めてにしては上手いじゃないか。」
そういい捨てて奴王は手白香を押し離し、背を向け出て行ってしまった。
「吉報だ。お前の兄がこちら側の条件を飲んだぞ。」
宴でもあったのか、赤貝で染められた衣を着た奴王は、華やかな衣服とは正反対の不機嫌そうな顔をして、手白香を閉じ込めてある空間にやってきた。
拘束されてから、十四日が過ぎていた。
殆ど毎晩いいように体を弄ばれ、苛まれた。
王は手白香に快感を与え自ら達する事はあっても、決して彼女の中で己の精を放つ事はなかった。
「お前は近々解放されるだろう。」
手で顎を固定し、王は冷たい瞳で彼女を見つめた。
「嬉しいか?………故国に帰れる事が?」
ゆっくりと唇が手白香の唇に触れた。
毎日行われる熱情で、従順になる技を覚えた。
熱く応える。
王は舌を絡ませ、強引に口の中に入ってきた。
手白香の口の隅々を味わう。
(今だ!!)
手白香は気付かれないようにゆっくりと両手を下ろし、繋がれていた筈の縄を一瞬にして王の首に巻きつけた。
そして、力の限り引っ張った。
「!!」
王は目を見開き、解こうと縄に手をかけた。
「奴国の王よ。我が父王の仇、そして私が受けた屈辱の数々を思い知れ!!」
きりきりと締め上げる。
だが。
女の腕力と男の腕力では流石に差が有りすぎた。
あっけなく縄を解かれ、下に組み伏せられそうになる。
「は、放せ!!」
「…成る程。今日まで少しずつ歯で噛み切っていたとは。大した女だ。」
それでも暴れて、男の下から逃れた。
十四日ぶりに自由になった両腕がヒリヒリと痺れる。
「美しい不弥国の姫は男も顔負けのはねっ返りだという噂も聞いた事があったのを思い出した。」
手白香は睨み付けた。
「ええ。貴方がそれを知らなかったとは。」
息を切らしながらも部屋の隅で奴王に対峙する。
二度目の失敗。もう、殺される準備は出来ていた。
「まず、女としての作法を教えなければな。」
また逃れようとすると、奴王は手白香の腕を掴んで引き寄せた。
気付くと王の腕の中にいた。
「そんなに俺が憎いか?」
静かな、とても静かな落ち着いた声で奴王は手白香に問うた。
暫く腕の中で暴れていた手白香はやがて心身共に疲れ、抵抗するのをやめた。
もう、どうなってもいい。
また涙が頬を濡らし始める。
彼女が大人しくなったのを確認すると、王は手早く彼女の貫頭衣を剥ぎ取り裸体を地面に押し倒した。
自身の衣服も脱いで彼女に覆いかぶさる。
「俺は、他国の人間が思っているほど非情な王ではないぞ。戦も好まぬし、自国の民から愛されているという自信もある。……よく考えろ。今、俺を殺したければそうすればいい。だが、俺はこれ以上憎しみを生みたくはない。」
言いながら優しく手白香の髪を撫でた。
その手つきは、意外なほど思いやりに溢れていた。
整った顔を近づけて、頬の涙を啜った。
「これは、俺の我が儘だ。だがどうやったら、お前の信用を得る事が出来る?」
切なげに呟いて、湿った唇を首筋に移動させる。
そこを強く吸った。赤い痕が出来る。
手白香は無言で目を閉じた。
そして、初めて、自分から手を伸ばし、王の体に触れた。
ビクッ、と王は体を震わせる。
刺青が体中に彫られ、筋肉の盛り上がっている細身の体の隅々を撫でる。
王は愛撫の一つ一つに反応した。
そのうち、手白香の手を離して、体の向きを変えた。
王の息が手白香の下腹部に暖かく吹きかかる。
そして、固く張り詰めたモノが彼女の顔に押し当てられた。
手白香の足を開いて、王はパックリと口を開いた花園に舌を這わせ始めた。
手白香も押し付けられて、先端が濡れそぼっている王の男を口に含んだ。
お互いに強弱をつけ刺激を与え合った。
「あ…っ。」
花園の蜜を吸いながらもふと、王は指を一本手白香の尻の割れ目に這わせた。
奥のきゅっと引き締まった隠花を軽く舌で舐めまわし、よくほぐしてから指を押し入れて来た。
「あっ―――あああっ。」
第一間接まで入れられると、不思議な快感が下肢を支配した。
手白香も、王の先端を吸いながら手で暖かくて柔らかい袋を刺激する。
おずおずと、躊躇うように王の奥の隠花に指を添えた。拒否をされなかったので、彼女もそのまま軽く指を入れてみた。
「……っ。」
王は再び体を震わせる。腰を動かして、手白香の喉元まで自身を埋めた。
同時に彼女の芽を舌で刺激したり、禁断の穴に舌を差し入れたりして、互いを刺激しあった。
「あ…ンッ……。」
手白香は大波が押し寄せるのを感じた。
ぴちゃぴちゃと手白香の花園を舐め上げながらも、彼女の口に自身を差し入れている王の動きが徐々に激しくなり、そして―――。
二人は同時に果てた。
どれほど経ったのか。
裸の男女が二人、身を寄せ合っていた。
王は愛しそうに傍らの手白香の漆黒の髪の毛を指で梳いていた。
何度も二人で快楽を味わい、昇りつめた。
それでも王は、彼女の中に自身を満たす事はしなかった。
「お前は明日、不弥国に帰される。」
静まり返った空間に、王の低い声が響いた。
手白香は無言で頷く。
「俺には二人の妻がいるが、お前の国は多夫多妻だと聞く。本当か?」
「……はい。」
「……そうか。」
それっきり王は黙りこんで、手白香を抱いたまま眠りに落ちた。
十五日ぶりの外の空気は清々しく、爽やかに手白香の肺を満たした。
薄い紫に染めてある装飾の凝った貫頭衣を着せられ髪を丁寧に結われた手白香姫は、奴王との最後の謁見を命ぜられた。
大きな高床式の建物の中に案内され、美貌の王の鎮座している前に出された。
王らしく着飾った奴王は周りの者に退室する事を命じると、手白香を強く抱きしめた。
「やはり姫らしく見えるな。……いい匂いだ。」
彼女の体から溢れ出す香りをを嗅ぎ、そして耳元に口を寄せた。
王は低く一言、囁く。
「夜眉という。」
「えっ?」
手白香は吃驚して王の顔を凝視した。
名を明かす、という行為は禁忌とされている。
下手に明かせば呪をかけられる恐れがあった。
それは相手に対して敗北、屈服を意味する。
特に王の名は、側近ですら知らないはずであった。
「俺の名だ。呪術をかけるなり何なり好きなようにしろ。いや、……お前が使者に化けて俺の前に現れたときから虜となった。その瞬間からお前の呪にかかったらしい。でなければ、このように胸が高鳴る筈がない。切なく痛む筈がない。……お前を手放すのが、こんなにも辛い筈がない。」
再び手白香を強く胸にかき抱いた。
「何を…考えているのですか、貴方は…?」
王の胸の中で手白香は訊ねた。
王は衣が湿り気を帯びるのを感じた。
彼女の涙であった。
「お前は知っていたか?俺がお前を無理やり己のものにしなかった理由が?何度も、お前を欲した。我がものにしたかった。だが…。」
泣いている手白香は顔を上げた。
「俺は心から和平を望む。お前という人質を解放し、両国の関係修復に励む。そして近い未来……。」
両手で彼女の顔を挟み大きな黒い瞳を覗き込んだ。
いつも冷たそうな王の目が、美しい顔が、苦痛で切なげにゆがめられていた。
「不弥国王に頼み、お前を迎えに行く。……だからそれまで、俺以外の誰も受け入れるでないぞ……。」
己の印をつけるかのように深く激しく口付けした。
「これは、永久の別れではない。」
初めて手白香は王に笑みを向けた。
虹色に辺りが照らされたような、美しい笑顔であった。
両国はその後何十年も友好関係を保った。東に大和という大国が建てられても、何百年の時が流れ一人の支配者が国を統一するようになっても、不弥国の姫と奴国の王の恋物語は語り継がれた。
<完>
小さな禿(かむろ)が歌を歌っていた。
風に揺らめく木の下で
風に揺らめく木の下で
私はあなたを待つでしょう
秋に色付く紅葉の
赤子の手のひら風に舞う
上下する胸。乱れる鼓動。熱い息。触れ合う素肌。飛び散る汗。
「あ、ああん……。」
もうすでに愛液で潤い濡れている女の花園全体を、固くて熱い自身の柔らかい先っぽでつん、つん、と突付いてきた。触れられた場所がくすぐったく熱を帯びる。
「ここに…触って……。」
彼女は自分の指で花びらを開いて真珠に触れてみた。軽く摩擦する。彼はその行為を、目を落として熱く見つめた後、大きく張った自身で彼女の蜜をくちゅくちゅとすくってから柔らかい先端を優しく真珠に擦り付けてきた。
「あ…あんん…ふっ……。」
ぶるっ、と喜びで目を閉じて身震いする。
「いい眺めだな…。」
そういいながら彼は真珠に押し付けた自身を左右上下に擦った。
「あ…あっ…!」
摩擦される度に声が上がる。そろそろと片目を開けてみると、ニヤリ、と茶目っ気のある笑顔とぶつかった。
「指を入れるぞ?」
左手で自身を動かしながら、右手をゆっくりとその真下に持っていった。
「あんっ…駄目!」
指が一本、彼女のなかに入れられた。円を描きながらどんどん奥に入っていくのが感じられる。彼女は快感で体を仰け反らす。桃色に色付いている固く張り詰めた乳首を自分で触った。
もう、蕩けそうだった。
さんざん弄った後、指を引き出した彼は快感の糸を引く蜜をそっと、彼女の唇に塗りつける。
まるで、見えない紅のように。
そして、彼は自分の舌でそれをぺろり、と舐めた。そのまま熱く激しく口付けをしてくる。
自分の熱い自身を楓の入り口にあてがい深く挿入する直前、彼は低く囁いた。
―――苦労はさせねーから、俺の女になれ―――と。
有馬惟宗(ありま ただむね)。祖父は剣聖と呼ばれた偉人。父は徳川家に剣術を教える名門家の四男坊。自身は兄弟達と江戸で有馬流剣術を教える道場を営み師範代を勤めながら生活している。剣の腕は名門の血を組んでか、達人級。道場破りにも、道端で売られた喧嘩にも負けた事がない。性格は我が儘で傲慢。顔は上の上の中。黙ってさえいれば切れ長の男らしい目つきと武士らしい引き締まった大きな体躯をした結構な色男である。
そんな四男坊は今日も同じ徳川家に仕える武家の嫡男、青山健一郎と大澤幸之助と共に暇をもてあましていた。
「あんた今日も来たんだね。」
明らかに歓迎していない、低い声音。松田屋の天神楓(かえで)の、惟宗を見た開口一番の一言であった。先日、初めて同衾する事を許した日から、惟宗は自分の女気取りで定期的に松田屋に顔を出すようになった。しかも彼の大いなる勘違いは、楓が心底自分に惚れている、と思い込んでいることである。そして、巷にそれを言いふらしているのだ。おかげで常連客の数は減り、楓にとって多大なる迷惑をかけているのであった。
「そうだ。お前が会いたそうだったから今日も来てやった。」
ふん、と偉そうに踏ん反り返ったその態度が癪に障る。彼と松田屋にやってきた来た青山と大澤は禿(かむろ)を冷やかしながら楽しげに飲んでいた。楓は不快気に惟宗を睨む。
「そんな事誰も頼んでなんかいません。こんな所で散財してあんたの道場潰れるわよ。」
冷ややかな声音も何のその。このお坊ちゃんには通じないのである。
「俺以外の兄弟は誰も遊廓遊びなんてしてねーし、俺の金じゃねーから別にいい。」
さらりと言ってのける所が憎らしい。
「あんたのせいで指名客が減ったんですけど。」
楓は言いながら酒を注いであげる。
「いい事だ。」
「全然良くない。ある事ない事吹聴して、どういうつもり?」
惟宗は涼しい顔をしながら酒を口に運ぶ。
「他の男に愛想を振り撒く必要がなくなるだろ?」
「指名がないと松田屋にお金が返せないのよ!!」
「ああ、そんなことより……。」
聞きたくない事は聞かない所が彼の凄い所である。杯に盛られた酒を一気に仰ぐと、突然真摯な顔で楓を見つめてきた。
「俺はお前と二人になりてえ。その為に松田屋に来た。こいつら置いて揚屋でもどこでも空いてる部屋にいこうぜ。」
彼の整った顔が近づいて来た。あっという間に、軽々と傍らの楓を腕に抱き抱えてしまった。
「ちょっと、なんなの突然!!」
腕の中の楓は明らかに嫌そうである。それを知ってか知らずかの、大胆な行為であった。足をバタバタさせて抵抗しても、ますます彼の抱擁は強くなるばかりだ。
「なんならここで…皆のいる前でやってもいーぜ?」
意地悪な笑みを顔に浮かべる。
「おい、楓さん嫌がってるみたいだぞ?」
「下ろしてあげた方がいいんじゃないか?」
初めて彼らが松田屋を訪れた時の、楓と惟宗の大喧嘩を目撃している友人の青山と大澤は心配顔である。
「そうよっ、下ろしなさいよ、このタコ!!」
暴れる楓を抱えたまま惟宗は無言で、静かな回廊を空き部屋を探してずんずんと大股で闊歩した。
「あんた、頭おかしくなったんじゃないの?何考えてるのよ、このど阿呆!!」
どさっと畳の上に下ろされた楓は、キッと惟宗を睨む。他の客の前では優雅でおしとやかな遊女を日頃演じている彼女からは想像つかない激し方で怒声を発した。
「うるせーよ。周りに人がいねーから“じ”がでたな、オカメ。」
「オカメって言ったわねぇ~~。」
白くて整った顔がみるみる赤みを帯びてきた。
二人は会うたびに、喧嘩をする。それが彼らの“普通”なのだ。この惟宗だけが、楓の本性を見せる事の出来る唯一の客なのである。
「悪かった。」
意外なことに素直に謝ってきたのは惟宗の方であった。
「謝っても許してやらないからねっ。」
やけに素直な惟宗に内心驚きながらも、楓はプイッと顔を背けて言う。
「認めたくねーけど、お前に会いたかった。」
ぞんざいに楓の肩を抱き寄せた。
「こんなオカメのどこがいいのか自分でも分かんねぇけど…。」
そのまま楓を床に押し倒す。
「お前といると落ち着く。」
熱い口付けの嵐を顔中に受けながら、ま、いっか……と、楓もなすがままにされていた。
楓の中には三種類の男がいる。
客として、絶対にお断りしたい男。まあ別にいいかな程度の男。そして、自分からお願いしてでも同衾したい男、の三つである。
幕府も公然と認めている高級遊廓で天神を勤めている楓には、有難い事に客を選ぶ権利がある。天神や太夫は身分や格に関係なく“粋”かどうかで男を選択する。が、禿として物心ついた時からこの松田屋で働いているのに残念ながら未だに三つ目の男には出会った事が無かった。燃えるように好意を寄せる相手に出会ったことはまだ一度も無い。
それでもいつか出会えるような予感がするのは、ただの願望なのだろうか?
仰向けに倒された楓は天井を見ながらそんな事をぼんやりと考えていた。
煌びやかに着飾った楓の小袖を脱がせ自身も襦袢姿になった惟宗は、手馴れた感じで彼女の帯を解いた。
「あんた…遊廓遊びしすぎだよ。」
腰を浮かせて彼の手伝いをしながら、楓は呟いた。
「もう、他んトコには行ってねぇ。お前じゃなきゃ駄目だ。」
帯がするりと解けると、着物のまえを開いた。白く浮かび上がった裸体に、ひんやりとした空気が楓の体に直に触れる。ブルッと身震いした。
「寒いか?」
襦袢を素早く脱ぎとって褌姿になった惟宗は、接吻を繰り返しながら楓の皺の寄りはじめた乳首を指で弄り始める。更に固くなった所で惟宗の唇が首を伝って降りてきた。張り詰めた頂をチュっと吸う。
「ああ……。」
手が楓の反対の乳房を優しく揉んでくる。もう片方の手は無造作に彼女の腹を下りて下腹の茂みの上を撫で始めた。
「駄目…あんたも脱いで…。」
彼女の情熱に近づこうとした惟宗の手を楓は止めた。惟宗を引き寄せて、褌の前垂れをたくし上げて、前袋をさすった。
大きく胸を上下させながら熱い目で楓の行動を見守る。六尺もの褌をするりするりと解いていくと、最後に彼の大きく張った男が顔を覗かせた。
それはもう充分な大きさと熱を帯びていて、そり立っている。
「これで、おあいこだな。…俺もお前も裸だ…。」
惟宗の男を見つめながら、楓は髪を揺らして頭を振った。
「ううん…。次はあんた。」
楓は白い裸体を起こすと、今度は惟宗を床に寝かせた。そろりと彼の男の証に片方の手を伸ばす。滑らかな竿の部分を手で上下に擦った。もう片方の手は彼の内股をさする。
仰向けに横たわった彼の裸の上半身には武士らしく幾つか傷跡が残っていた。道場で真剣勝負もするのかしら?と思いながら楓は上下運動をしている手に微妙に強弱をつけた。惟宗は気持ち良さそうに目を閉じている。
「…雁が首か。舐めてくれ…。」
楓の頬に惟宗の肉の厚い大きな手の平があてられた。楓は返事の変わりに顔を先端に近づけた。
ビクン、と僅かだが惟宗が反応する。先を口に含んで吸いながら、笠の部分を舌でなぞる。太腿をさすっていた手を上に移動させ、彼の濃い目の茂みをまさぐりながら袋の下の、隠花の奥の前立腺のあたりを刺激する。
「…っ。お前も客を相手にしすぎだ…阿呆…。」
苦しそうに低い声音が頭の上から降ってきた。
楓はもっと深く、惟宗の男を含んだ。
長いこと口の中で出し入れしながら巧みな舌使いで舐めていると、
「うっ……。」
惟宗の体が震えた。楓は口を離す。
刹那、白い快感が大量に宙に放たれた。片手で自身を押さえ、全部出し終える。宙を切った彼の液は、彼の逞しい腹筋の盛り上がった腹の上に広がっていた。
楓はそれを花紙で優しく拭き取ってあげると、激しく胸を上下させている惟宗の隣に身を寄せた。
楓が五歳の時、母親は彼女を松田屋の前に置いていった。
母親は戻ってこなかった。
その日から、禿としての楓の生活が始まった。元来の明るい性格と、美しい容姿が手伝って固定客ができ、今では太夫の一つ下の位の天神まで上り詰める事が出来た。
初めての同衾は、禿時代。彼女が月の物を始めて迎えた月の事だった。
相手は名前すら知らない初老の男。大阪から来た商豪だった。彼は大金をはたいて彼女の初夜を手に入れた。
思い出したくもない過去。その男はその後長い事彼女のパトロンとなってくれていたが、ついこの間亡くなったと聞いた。
その初めての日から、彼女にとっての「男」は借金返済の道具でしかないのかもしれない。
悲しい鳥かごの鳥。
この遊廓街、江戸梅山から出て行くことは年季が切れるまでは無理なのだ。
雪のように白い体を横にして傍らで目を閉じている男に見入る。
上下していた呼吸も落ち着いた所で、惟宗は片腕をついて頭を支え、自身も隣の楓を見つめた。他の遊女に比べ薄塗りの白粉にも負けない白い肌、意志の強そうな直線眉と濃く縁取られた黒目がちの瞳。挑発を込めた笑みを口元に称えてこちらを直視している。
「言っとっけど、まだ終わりじゃねぇ。」
つい先ほど果てたばかりなのに、若さゆえか、傍らの美しい女のせいか、再び熱を持って己の男が体積を増すのが分かった。身を起こして横たわっている楓の足元に移動する。
「ちょっとまっ…んんっ…。」
惟宗は彼女の両膝の裏を押し上げ体を反転させた。楓のすでに濡れた秘部が惟宗の目の前で露になる。
「俺が、お前の身請け人になってやる。」
「はあ?…あんっ……な…何?」
先ほど、彼に刺激を与えながらも彼女はいつしか濡れていた。
果実のように熟れた蜜をしたたらせるそこに彼は指を滑らせた。
「ああ…ん…っ。」
声が出る。
「お前を独り占めしてぇから、俺がお前の借金を全部返してやる。そしたら、指名客の心配もいらねーだろ?」
彼の指が怪しく蜜をすくう。ぺろりと糸の引いた指先を舐めると、悪戯っぽく微笑んだ。
「お前、俺に触りながら濡れてたんだな。」
独り言のように小さく呟く。
「…余計なお世話だよ、馬鹿。あんたの助けなしでも自分で返済するんだから…。」
惟宗は無言で楓の小さな真珠に親指を添えた。次に中指が蜜で濡れた禁断の穴に滑り込む。そしてそのまま小指でその下の隠花の辺りを突付いてきた。
「ああんっ、イヤンッ……ああ!」
三箇所をいっぺんに刺激してきた。くちゅくちゅぴちゃぴちゃと卑猥な音をたてながら指を細かく動かす。
「あ…あ…あああ…。」
今度は楓が苛まれる番であった。手で秘部を愛撫しながら、上体を屈めて口付けを体中に浴びせる。
しつこい愛撫はとどまる事を知らない。
再度横になった彼は、楓を抱き起して自分の頭の上に跨がせた。いわゆる岩清水、という体位だ。ぱっくりと口を開いた花園が彼の顔の前にあった。尻を掴みながら蜜の滴る花園を貪った。舌を尖らせて花弁を舐めあげ、小さな穴に入り込む。
「んんんっ…ああ…。」
床についた両膝が、快感でなえてしまいそうだ。
惟宗は顔をグッと花園に押し付けて、その匂いを、溢れ出る蜜を味わった。
「あ…ああんっ…や…。」
「嫌ならやめてやってもいいぞ…?」
「……死ね。」
「お前とならな。」
熱い息を吹きかけ喋った後、彼女の真珠を軽く歯で噛んで吸うのも忘れない。指は彼女の尻を左右に広げ、奥の隠花を弄ぶ。
「お前のここが欲しい。誰も入ったことないんだろ?」
指が一本隠花に挿入された。
「ああっ……痛いから、駄目。そこが好きなら陰間のところにでも通えばいいじゃない。」
「馬鹿野郎。男なんて御免だ。お前のが、いい。」
指と舌がくちゅくちゅと音を立てる。
「ふっ…くっ…ぜ、絶対いや。」
「ふうん…分かった。」
冷たい返事をしたかと思うと、惟宗の口と指の動きが一段と激しくなった。長い事彼女を苛む。
「ああああぁぁ………!!」
言葉に出来ない快感で四肢が緩む。
彼女は白い快楽の底へ落ちていった。
「お前…温い。」
ぱんぱんに熱く滾って膨張いる自身を、楓の蜜で濡れた入り口の部分にあてがった。
ゆっくりと侵入する彼を体内に感じながら楓は吐息を漏らす。
「知ってた?あんたあたしの客の中で一番刀傷がある…。」
奥まで彼でいっぱいになった。惟宗は不快気に眉間に皺を寄せる。
「他の男の話は今するんじゃねーよ……。」
言いながら一度大きく腰を振る。
が、何を思ったか彼は自分を彼女の中から抜き出した。
「抱き地蔵がいい。上に乗ってくれ…。」
と言うが速く、彼女の了解も得ず軽々抱き上げて上に乗せた。楓はそのまま串刺し状態になる。上に乗った彼女を惟宗は熱い眼差しで見つめた。
「嘘でもいいから…好きだと言ってくれ…。」
いつも怒ったような無愛想な彼からは想像できない、辛そうで不安気な瞳が目の前にあった。黒い瞳は彼女自身を映している。
「頼む…。」
「……嘘だけど、好き……。」
我ながら意地が悪いなあ、と楓は思った。惟宗は、特別な客だ。好意を寄せてはいるけど、何かが違う。
「…阿呆。正直に言うな…。」
彼女は彼の首に手を廻し、腰を使って上下運動をし始めた。惟宗は床につけた片手で体を支えながらも、もう片方の手で彼女を強く抱きしめた。
お互いの体から汗が噴き出している。ぱんぱんと音を立てながら白くて柔らかい尻が惟宗の腿の上にあたる。彼も彼女に合わせて腰を振った。
「ん…あっあっあっ……。」
溢れ出る愛液でよく滑った。二人とも目を閉じ、唇を噛み締めながら繋がった一箇所に意識を集中させた。
どれ位たったのか、彼女の爪が惟宗の首に軽く食い込んだ。
「あああぁぁぁぁl!!」
二人の体がビクンと硬直し、そのまま弛緩した。
同時に絶頂を迎えたのだった。
柔らかくて温かいものが自分の腕に包まれていた。同時に、女特有のかぐわしい香りを鼻いっぱいに吸い込んだ。
「楓。」
声を出して名前を呼んだ途端、ゆくりなくも激しい感情の炎が再燃する。離れたくない。
「楓!」
何故か焦燥感を感じた惟宗は、彼女の名を呼びながらガバッと身を起こした。
「何よ、いきなりうるさいわね。……ちゃんと聞こえてるけど。」
眉をひそめながら床の中で楓は惟宗を見つめた。見つめながら、大きく欠伸をひとつする。
「あんたの友達は昨夜帰ったのかなぁ?」
二人は昨晩、何度も交じり合った。お互い、いつ眠りに落ちたのかすら覚えていない。
「だろうな。青山は最近お前んとこの太夫に入れ込んでるらしいぞ。」
「胡蝶姉さまの事?彼女忙しいから昨夜は相手にしてないと思うけど…。」
惟宗はゆるりと唇辺を緩めてもう一度楓を抱こうと腕を回した。
「あーあ、どうでもいいけどお腹減ったね。誰か呼んで何か運んでもらおうっと。」
楓はまるで少年のように、くるりと身軽に体を横に反転させ床から起き上がると、大きく伸びをした。
惟宗の腕は空しく宙を切った。
遊廓を出て行くとき、昨日来たときと同じ場所で、小さな禿は同じ歌を口ずさみながら喜々として道端を箒で掃いていた。
風に揺らめく木の下で
風に揺らめく木の下で
私はあなたを待つでしょう
秋に色付く紅葉の
赤子の手のひら風に舞う
惟宗は眩しい昼の太陽に背を向けた。今さっき別れたばかりの、熱い夜を共にした愛しい女の香と温もりを思い出しながら続きを歌った。
風に揺らめく木の下で
風に揺らめく木の下で
私はあなたを待つでしょう
最後の手のひら舞い散る時
あなたの姿が目に映る
風に揺らめく木の下の
楓道へと歩き出す……
<完>
We Love 木蘭!(シリーズ)
絶世の美人と噂の松田屋の格子、木蘭のぶっとび一話完結日記シリーズ。彼女を愛するあらゆる階層の顧客達。いわゆるラブラブあまあまで、ラブコメ調の逆ハー状態(?!)なのでそっち系が苦手な人は今すぐ回れ右!!不定期更新です
(クソ真面目お侍さんVS木蘭さん)
(豪商の遊び人VS木蘭さん)
(不思議な公家のお坊ちゃんVS木蘭さん)
(怪しい隻眼男VS木蘭さん)
(同業者のお兄さんVS木蘭さん)
(初恋のあの方VS木蘭さん)
番外編
木蘭の先輩でもある楓姐さんと名門有馬家四男坊のお話。
ホテルの最上階は、東京の夜景が360度に渡って見渡せるバー兼レストランになっていた。
ずーっと昔に修学旅行で東京タワーに登って以来、俺はこんなにキレイな景色を見たことが無かった。
そのときは、夜景なんてロマンチックなもんじゃなくって、昼間の東京のビルを高い見物料払って見ただけだけど。
「うをーーーーっすっげーなあ。あれ、HMビルじゃね?東京タワーも見えるぜ!」
俺は窓側の席を陣取り、ビールをオーダーした。
鷹男もTシャツとカーキという、ハッピを脱いだ俺と同じ位ラフな格好だ。
ちょっとはしゃぎ過ぎたのか、隣のカップルが迷惑そうな顔で俺を見た。
鷹男はそれに気づいているのかいないのか、そしらぬ顔でラム&コークをウェイターにオーダーしていた。
まだ疲れたような顔をしている。
「お前は大馬鹿者だな」
飲み物が来て一口グラスに口をつけると、呆れたように鷹男が呟いた。
「人の事馬鹿馬鹿言うな、馬鹿ヤロー」
「俺と紅が親切にお前の借金を帳消しにしてやると言っているのに、だ」
「それを俺の断りも無く決められたのが、腹立つんだよっ」
鷹男は俺の文句を無視して続ける。
「お前は今、人生においての転換期にいる。今まで一番大切だった水泳が出来なくなり、次にやりたい事が見つからない混沌の時期に入っている。だから、迷っているのだ。わかるか?」
鷹男が真剣な眼で、諭すように俺に語りかけた。
「俺はそれにつけこみ、お前を暇つぶしの玩具にした。お前は俺に似ている。手に入らないもの、挑戦できる事にしか、価値ややりがいを見出せない」
『暇つぶしの玩具』とハッキリ宣言され、怒りがふつふつと湧き上がる俺に構わず鷹男は続ける。
「お前が俺を好きだというのならば、ゲームオーバーだ」
「ゲームオーバーって何だよ!これははじめっからお前の中ではっ......」
「ああ。ゲームだった。言っただろう?」
鷹男に、言葉の語尾を遮られた。
......そうだった。
そうなんだ。
一度、鷹男本人からも同じようなことをEFのパーティーの帰りに言われたっけ。
キスのせいで、俺ひとりだけが動揺して舞い上がっていた。
「お前、女に対してすんげーコンプレックスかトラウマ持ってんだろ?女を信用してねえよな」
俺は冷たいビールのグラスを両手に包んで持ちながら、鷹男の表情を観察した。
暗い瞳には、動揺の欠片も見えない。
しばし沈黙した後、鷹男は再度口を開いた。
「昔一度結婚しようと思っていた女がいてな。丁度今のお前のように、怪我をして陸上が続けられなくなった直後の事だ。陸上も止め、門田の家を出て教師にでもなってひっそりと暮らそうと思っていたのだが、あっさり女からは捨てられた。あの女は、俺についてくるパッケージ......すなわち、金と名声だけを欲していた。有名なスポーツ選手か、親父のような新鋭の政治家になるとでも思っていたのだろう。案の定、うちの社名と俺の名が知れ渡った途端、よりを戻そうと迫ってきた」
鷹男が真面目な顔で自分の過去を語るのは、これが初めてだった。
俺はその話を聞いて、つい吹き出してしまった。
「教職免許有るって聞いた事は有る。でも鷹男、あんた女見る目無かったんだな」
鷹男も俺につられて苦笑する。
「俺も若かった。今では笑い話で済ましているが。だがそれ以来、俺の金と名声につられる女には興味を持っていない」
つまり、俺との出会いは最悪だった訳だ。
思いっきり、鷹男の金目当てだったもんな。
俺が頭の中で思っていることを把握しているのか、鷹男は深く頷いたように、顎を引いた。
「俺は女より家族を優先する。紅が傷つくのであれば、お前を消す事も厭わない。そういう男だ」
最後の言葉の矢が俺の胸に突き刺さった。
ああ、もしかしてこれが最終通告......?
失恋って、こういうもんなのか?
俺、今、失恋したのか?
「紅を...傷つけるつもりはねえよ」
容赦ない言葉を受けた胸が、痛い。
ズキズキして、熱を持っているみたいに。
とても熱く、悲しく、切なくじんじんする。
思わず、拳を握り締める。
霞んで潤みだしそうな目頭を、眉間に皺を寄せ歯を食いしばり、耐えた。
ビールで一度潤してから、喉の奥底から再度言葉を吐き出した。
「鷹男の言う事は良くわかった......。もう、女々しい事言って困らせたりしねえ。はっきり言って、俺も自分で自分の行動が分かんなくて、もやもやしたわだかまりがずっと腹ん中にあったんだ......」
詰まっていた言葉を言い終えると、深く吐息を吐いて椅子の背にもたれかかった。
なんか......力が抜けた。
今まで張ってきた気の膜のようなモノに針が刺さって、風船みたいに一気に破れ散ったみたいな、脱力感。
鷹男はそんな俺を見て、やっと表情を崩し口角を引き上げる。
いつもの鷹男の仕草だ。
自信に満ち溢れた、大人の余裕。
男らしくて、強い意志を持った笑み。
......ひねくれ者の笑み。
「俺からのアドバイスだ。お前の将来の目標が何であれ、お前には大きな可能性が広がっている。ここで足踏みして血迷うな。何をしても一番になれ。お前ならなれる。世界を見ろ。世界を見て、俺と対等の女になってみせろ。そしてその時、お前と俺の人生の糸が交差しているのであれば......考えてやってもいい」
鷹男が示唆している事柄が、何を指し意味しているのか、何となくわかった。
俺が黙っていると、鷹男は濃い色の液体を一気に飲み干し立ち上がった。
「俺はもう寝る。次にお前に会うときは、BREEZEの取締役代表としての門田鷹男だ。忘れるな」
まだうっすら泡が表面に残っている黄色い液体を眺めていた俺の目の前に、折畳まれた見覚えのある紙が舞った。
その紙を見て俺が顔を上げようとするのと、鷹男が腰を屈めて俺の上に影を作ったのは同時だった。
しっとりと、鷹男の唇が重なる。
コーラの味と、アルコールの味が混ざり合った大人の味わい。
舌も絡ませて、お互いの味を貪った。
多分、これが鷹男との最後のキス。
最後の接触。
最後の温もり。
唇を離すには、多大なる理性と勇気が要った。
キスの終わりは、俺達の関係の終わりを意味していたから。
体を先に離したのは、鷹男だった。
ああ、やっぱこいつには勝てねえのかな。
まだ、今の俺では.........。
なんとなく、そんな事を思った。
唇を上腕で拭うと、鷹男は今まで見た事もない優しい顔で微笑んで、踵を返した。
鷹男の姿がバーから見えなくなると、俺は折畳まれた紙......鷹男との契約書を掴んで出口に向かった。
ホテルのロビーを抜けようとした所で、後ろから声が掛かった。
何でこいつは、俺の心が壊れ砕け散りそうな時に限って現れるんだ。
いや、前回は俺が会いにいったんだけど。
忌々しげに舌を打つ代わりに、安堵の吐息が口から漏れた。
「何でここに居んだよ」
言いながら、振り返る。
そこには、小さく微笑んで佇んでいる紅の姿があった。
今日は何故か松葉杖をついていない。
「何でって......ここに居るって知ってたから、来た」
「ストーカー」
「何とでもいいなよ。俺が必要な癖に」
「なっ.........」
違うよ、と言いそうになる前に、紅が右足を引き摺りながら俺に向かって歩き出した。
「兄貴が俺に『お前の女を迎えに来い』って連絡をくれたよ」
「鷹男が?」
「でもそれ以上に翠に会いたかったから来た。それだけ」
珍しく、紅の色白の頬が紅く染まっていた。
「送るよ」
照れ隠しなのか、ふいと横を向き顎でエントランスを指した。
紅の歩調に合わせて、俺達は駐車場まで並んで歩いた。
夜なのに、気だるいほど蒸し暑い。
虫の音が、どこからか聞こえてくる。
隣の紅は、少し不機嫌そうに口を尖らせたまま俺とずっと視線を合わそうとしなかった。
「何も聞かねえのか?」
俺は立ち止まって腰に手を当てて紅に訊ねた。
数歩先の紅は振り返る。
「兄貴にさ、好きだって告げたの?」
「ああ。でも......」
「想像つくよ。兄貴がどんな男かって、前に話したことあるよね?」
紅は複雑な表情のまま、口元だけ無理矢理笑みを作った。
「あいつに上手く丸め込まれたらしい。すげえよ、鷹男は。生粋のプレイヤーだな」
俺は肩を大きく竦めて苦笑する。
でも、いつかあいつを負かせる事の出来る女になりたい。
とびきり良い女......すげえ女になってやる。
そう決意を決めると、自然と口元が緩み始めた。
「何笑ってんのさ」
紅が怪訝な顔で俺を見た。
「いや。何かやる気出てきたなと思ってさ」
「ふうん。よくわかんないけど、良かったね」
紅はそう言いながら、俺に手を差し出した。
「翠、ふっきれた顔してるよ」
俺は紅の手を一度見て、そのまま視線を紅のヘイゼル色の瞳に移した。
「俺、ちょっと本腰入れてみるわ」
「何を?」
「モデル業。前はハッキリ言ってああいう職業馬鹿にしてたし興味無かったけど、どこまで行けるかやってみようと思う。やるからには、世界に名を馳せるモデルになってやる。一番になってやる。世界征服だ!」
意気込む俺を見て、紅はやさしく微笑む。
「じゃあ、俺がたくさんポートフォリオ用の写真撮ってあげる。翠なら出来るよ、世界征服」
手はまだ差し出されたままだ。
そして、気恥ずかしげに言葉を紡いだ。
「翠、ちょっと順序間違っちゃったけど、多分『抱いて』ってお願いする前にさっさと言っておけば良かったのかもしれないけど......」
紅は一度そこで言葉を切る。
そして、意を決したみたいに一気に吐き出した。
「俺と付き合ってください。俺、翠の助けになりたい。家が無いなら、うちにくればいい。お金が必要なら、貸す。体も好きにしていい。本当は翠を閉じ込めて、誰ともシェアしたくない。翠は野生児だから......多分手懐けるのに時間かかるかもしれないね。でも、俺と一緒に居てくれるなら、俺を受け入れてくれるのなら、俺は代償を求めないよ」
俺は頭を掻いた。
何度も紅から「好きだ」とは言われていたけど、男から『付き合ってくれ』と告白されるのは、人生で初めてだった。
いや、男に告白して振られたのも今夜が初めてだけど。
少しだけ、突然の告白に面食らった。
慎重に言葉を選んだ。
「俺、人生で初めて好きになった男......鷹男に振られたばっかだし、女の子も好きだし、女の子見てやりてえなと思う時もあるかもしれない。......もちろん紅の事も好きだけど......これから俺の気持ちがどうなっちまうのか、自分でも分かんねえんだ」
「先の事なんて、誰もわからないよ。俺だってわからない。それに言ったよね?俺、翠とは性別超えた仲になりたいって。オトコとオンナ以上の関係になりたいって。欲張りかもしんないけど、親友以上で、恋人以上の仲になりたい」
俺は大きく息を吸って、天を仰ぐ。
腹に一度空気を溜めて、一気に吐き出した。
「東京ってやっぱ、全然星見えねえよ」
小さくボソっと呟く。
今夜がきっと、俺の人生の新たな幕開け。
出発地点。
「行こう、翠」
紅が囁き声で俺を催促した。
俺は手を伸ばして、紅の手を強く掴む。
さらりとして、温い。
紅の、体温。
今までも、きっとこれからも俺を包み込む、体温。
俺は力いっぱい、その温もりを引っ張った。
<完>
「仁神堂。肩が凝ったわ。揉んで頂戴。」
移動中の自家用ジェットの革張りの黒いソファで書類に目を通しながら私は秘書の仁神堂浬(にがみどう かいり)に命令した。
ロスからダラスまで約4時間。
いつもながら今、この空間には彼と私しかいない。
「かしこまりました。」
感情の抑制された低い声。
もう聞き飽きたわ。
この男が私の元で働き出して一ヶ月。
就寝時以外は秘書兼付き人として常に行動を共にしてきた。
秘書としてはこれ以上ない、といって良いほど完璧。
でも、 いつも無口無表情で、この男の脳には「感情表現」という言葉が組み込まれているのか?と、会社では氷の女王と呼ばれている私ですら、眉を顰めるほど人間的に感情が欠如したような、不可解な男であった。
向かい側に座っていた彼は、腰を上げて私の隣に移動する。
8’2……185はあるのだろうか?均整の取れた体に折り目正しくプレスされたスーツを感じよく着こなしている。
ネクタイの趣味も、悪くない。
「社長、こちらに背を向けてください。」
書類から目を離し、左横に座った仁神堂に背を向ける。
両肩に大きな手が置かれ、優しく揉みだした。
最初は張っていた肩に痛みを感じたが、程なく心地よさに変わる。
「案外、上手いのね。前にもやった事があるみたい。」
「敬一郎様がお好きでしたので。」
優しい手つきとは正反対の冷たい声音で返事が来た。
彼は以前、私の祖父の専属秘書をしていた。
「こんな事までやっていたの?まるで雑用ね。」
「……仕事ですので。」
私はマッサージされながら、何気なくリモコンを手に取った。
巨大なモニターが降りてくる。
ソファの正面の壁のスクリーンには暖炉が映し出され、焚き火のように燃え盛る炎が本物の如く揺らめいていた。
知らない間に季節は廻り、冬が近づく。
寝る時とエクササイズの時間以外は四六時中ビジネススーツを着ているので、自宅のクロゼットの中は明らかにスーツの数が私服の数を上回っていた。
「新しいセーターとマフラーが欲しいわ……。」
独り言のように小さな声で呟いた。
どれ位経ったのか、いつの間にか肩にあった重圧はなくなっていた。思った以上にこの男はマッサージが上手い。
止めて欲しくなかった。
「背中も叩いて頂戴。」
「かしこまりました。」
背後でソファが波うち軋む音がした。
仁神堂は体勢を変えたらしい。
彼の温かい息遣いを背中に感じる。
その上、上品なコロンの香りまで私の鼻をくすぐった。
私の中で、悪魔がむくむくと頭を擡げる。
この男を、試してみたい。
この男が何処までやってくれるのかを。
「次は、足をよろしいかしら?」
背中がすっきりすると、靴を脱ぎながら指示した。
仁神堂は何も言わず、ただ私が大きなソファーにうつ伏せになるのを見守った。
幸い、今日はパンツスーツだ。
「痛い所があればおっしゃって下さい。」
言いながら、強弱をつけてズボンの上から両足を軽く叩き出した。
ふくらはぎをマッサージされながらも、私の神経はそこになかった。
どうやったら、この男からいつもと違った反応を得られるのだろうか?その事ばかりが頭の中を占めていた。
考え込んでいると、暫くして仁神堂は手を止めた。
「社長、終わりました。」
「ああ、有り難う。」
私は満面の笑みを浮かべて礼を言った。
彼は眼鏡を抑えながら、
「失礼致しました。」
と低く呟く。
私はソファーに座りなおし、微笑を浮かべたまま仁神堂を直視した。
「仁神堂、眼鏡を取ってくれないかしら?」
「眼鏡を、ですか?」
聞き返す声に驚きの色は全くない。
「これがないと私は殆ど何も見えないのですが。」
仁神堂は多少渋っているように見えた。
私は心の中でしめた、と思った。
「ずっととは言ってないわ。少しの間でいいのよ。」
「かしこまりました。」
そう承諾すると仁神堂は、すっと眼鏡を外してテーブルの上に置いた。眼鏡のせいか、元からなのか、目のほりが深い。
一見、純日本人には見えない整った綺麗な顔立ちをしていた。
薄茶色の硝子のビー玉で出来たような冷たい瞳は、濃くて長い睫毛に縁取られている。
意外と、魅力的じゃない。
一ヶ月もの間気が付かなかったなんて。
私は、もっとこの男を追い込んでやりたい、と思った。
「もし、ここで私がマッサージ以上のことを要求したらそれはセクハラになるのかしら?」
仁神堂の顎の下を軽く手で触れる。
「私が拒否するのを社長が無理やりなされたのなら、それはセクハラになると思われます。」
仁神堂に、動揺という言葉はないらしい。
私の不躾な質問にすら、落ち着いた声で答える。なんて男かしら?
「あなたは嫌かしら?」
私は、真顔に戻って熱い眼差しで彼を見つめる。
そう。これは全てこの男の本性を暴く為の、演技。
「それは、事によりますが。」
「そう。事によるのね。」
私は、ひっつめていた髪の毛のゴムを解いた。
茶色くて長い髪がはらり、と肩にかかる。
髪の毛をかき上げた後、優しく聞いた。
「なら、これはどうかしら?」
ゆっくりと、仁神堂に顔を近づける。
薄くグロスを引いた唇を軽く、彼の右頬に触れさせた。
反応は、ない。
彼の顎に再び手を置きながら、少しずつ唇をずら していく。
口の端ぎりぎりまで来て、顔を離す。
私は彼を焦らそうとした。
だが、彼を見ると先ほどと変わらず、無表情で私を見つめていた。
やがて、口を開 く。
「社長は、これがお望みだったのですか?」
私はその言葉に顔が赤らんだ。
決まりが悪くなる。
が、平静を装って仕事用の営業スマイルを浮かべた。
「ええ、そうよ。」
容赦ない質問は続く。
「気がお済みでしょうか?」
「えっ?」
気がお済みでしょうか、ですって?
済む筈がないじゃないの。
私はまだ、何も見ていない。
このロボットのような男の心の中を探るまでは…。
「いいえ。済んでないわ。」
そう素直に答えてしまう。
「そうですか。それでは…。」
それは一瞬の出来事だった。
気が付いたら体は引き寄せられていて、私は長くて熱い口付けに応えていた。
丁寧に、味わうように、舌を絡ませる。
恋人とも、 こんな熱いキスをしたことがなかったかもしれない。
もしかして、焦らされていたのは、私の方?
体が意思に反して火照りだす。
が、突然、仁神堂は顔を離した。
眼鏡をテーブルから拾って再度かける。
何事もなかったかのようにいつものポーカーフェイスで服装の乱れを正し、腕時計を見た。
「後、40分弱でダラスに到着です。社長はご支度に取り掛かられた方がよろしいでしょう。」
私は、その一言で我に返った。
私も、氷の仮面をつけて、心の中の動揺を隠す。
声が上擦らないように気をつけながら、
「テーブルの書類をまとめておいて。」
とだけ伝えて、化粧室へ向かった。
狭くて小さい機内のシンクでソープを泡立てながら、崩れかけていた化粧を熱いお湯で洗い落とした。
タオルで拭った後、携帯用の化粧水をつける。
手馴れた作業をしながら、ずっと考えていた。
この私が、動揺している。
冷静さでは、誰にも負けないと思っていたのに。
「社長」という肩書きが有る以上、同情や不必要な感情を捨て割り切ろうと努力していたのに。
やはりあの男は、只者ではない。
でも、いつかは。
いつかは、仁神堂浬の面の皮を剥がしてみせる。
一通りの事を終えて化粧室を出た私は、横目で向かい側のラブシートで何事もなくノートパソコンの画面に見入っている仁神堂を見つめながら、傍らのエアフォンに手を伸ばす。
慣れた手つきで番号をダイアルした。
……ロスにいる恋人の声を聞く為に。
後で気付いた事なのだが。
テーブルの上の書類は全て綺麗に片付けられていて、代わりにそこにはJC〇ニーからデ〇オールの専属顧客用冊子まで、冬のファッションカタログが何冊も積まれて置かれていた。
翌日、ダラスからニューヨークに戻った晩、私は一ヶ月ぶりに恋人と会うことが出来た。
お互いにスケジュールを調整しても、彼とは月に二度会えたら良いほ うなのである。
いわゆる青年実業家で、全米にある日本食レストランチェーン「KISHI」のオーナーである彼は、私と同じくらい多忙な生活を送っていた。
マンハッタンの高層ビルの最上階にある、美しい夜景が堪能できる彼のコンドで夕食を済ましワインを飲みながら談笑していると、突然真顔で溜め息混じりに彼が洩らした。
「君の声はいつでも聞くことが出来るけど、会いたいときに会えないからね。俺はたまに気が狂いそうになるよ。」
熱い抱擁を受けながら私の頭は別な所にあった。
彼のように気が狂いそうになるほど彼に会いたいと熱望した事があったかしら?
…無いかもしれない。
けれど、彼を安心させる為に嘘をつく。
「私もよ、岸さん。」
彼の抱擁は次第に激しくなって、気付いたら私は彼の寝室で横になっていた。
頭のすぐ上には彼の男らしい精悍な顔があった。
「俺は久々でかなり溜まってるんだけど…。」
と言いながら首筋と胸元にキスの雨を降らせる。
私は熱く迫ってくる彼に応えながらも欲望が点火するその時まで、頭の中で仁神堂(にがみどう)は明日何時に迎えにくるのかしら?
今、あの男は何をしているのかしら?などと考えていた。
翌朝早朝。
朝の四時ぴったりにテーブルの上の私の携帯が鳴った。
案の定、仁神堂からであった。
シーツを体に巻きつけベッドから這い出る。
まだベッドで眠っている恋人に背を向けて小声で電話に出た。
「仁神堂?」
「おはようございます。社長、今下で待機しておりますので、失礼ですが三十分以内にご用意を済ませて下りて来て下さい。九時までにボストンに着かなければなりません。」
相変わらず感情のない低い声だった。
「分かったわ。すぐ行きます。」
そう短く答えて電話を切る。
話を終えて振り向くと、ベッドにはまだ子供のようにすやすやと寝息を立てている恋人の姿があった。
私はなるべく音を立てずに すばやく身支度をする。
大理石で出来た浴槽でシャワーを浴び、洗面所で濡れた髪を乾かしていると、首の後ろに薄くピンク色のキスマークが出来ているのに気 付いた。
いつものように長い髪を1つに結わず、ブラシで梳かして垂らしたままにする。
薄い化粧をして、服を着た。
そして『今夜電話します』と書いたメモを 残し、玄関先の執事に軽く会釈をして彼のコンドから立ち去った。
まだ朝の四時半だというのに、リムジンの中で私を待っていた仁神堂は、スーツ姿で髪の乱れ一本もなくビシッと決めていた。
このロボット男はたとえ早朝であっても、真夜中であってもその風体を崩さずこんな調子だ。
私の、
「早朝から爽やかね。」
との言葉を無視して真面目な顔で、
「コーヒーはお飲みになられますか?」
と聞いてきた。
「オレンジジュースでいいわ。」
とだけ答える。
恋人は一晩かけて何度も私を欲した。
私は昨夜の激しい運動で身体的な疲労がまだ取れていなかった。
その上、低血圧の私に今頃になって大きな睡魔が押し寄 せる。
不本意ながら大きな欠伸をしてしまう。
そんな私に気付いているのかいないのか、仁神堂は車内に設置された冷蔵庫からジュースを取り出してグラスに注 いだ。
そして、
「社長、これが今日の会議の概要です。まあ熟知しているとは思いますが、ボストンに着くまで必ずもう一度目を通しておいてください。」
と事務的に言いながら、私にオレンジジュースと共に分厚い書類を手渡してきた。
「仁神堂、昨夜は何をしていたの?」
書類に目を通しながら私は何気なく聞いてみた。
あのことがあって以来不思議な事に、何故だかこの男の謎めいた私生活が気になり始めた。
「昨夜は、家で映画を観て寝ただけですが…。」
新聞を読んでいた仁神堂は顔を上げた。
映画?
この男は映画なんて観るの?
「何の映画を観ていたの?」
私は興味を引かれて聞いてみた。
が、冷たい仁神堂の、
「題名は存じ上げません。」
の一言でこの話題はあっさりと終わりを告げた。
私は再び書類に目を落とした。
暫く集中して書類を読んでいると、今度は新聞をめくりながら仁神堂が口を開いた。
「きょうは…。」
「?」
何が言いたいのか解らず私は小首をかしげる。
「少し雰囲気が違いますね。」
言葉の意味を悟るのに数秒を費やしてしまう。
ああ、髪型のことを言っているのかしら?
まさかキスマークがあるから隠しているとは言えないので、
「今日は久々に髪を下ろしてみたのよ。似合うかしら?」
とにっこり微笑みながら聞いてみた。
仁神堂は無表情で眼鏡を指で抑えながら抑制した声で
「よくお似合いですよ。」
とだけ言って、さして興味もなさそうにコーヒーに口をつけた。
どれくらい経ったのだろうか。
静かな車内で長い間分厚い書類の小さな英活字を目で追っているうちに、私に再び大きな睡魔が襲いかかった。
もう限界だわ…。
書類を傍らに置いて仁神堂に、
「少し休みます。ボストンに着いたら起こして頂戴。」
とだけ断って、目を閉じた。
熱があるのか、私は真っ白な広い部屋の、柔らかい白い大きなベッドの上で仰向けに寝かされていた。
とても心地が良い。
ベッドの隣では今は亡き父親が、昔 の思い出の姿のまま私の看病をしてくれていた。
長いこと無言で私の髪の毛を指で梳いている。
私はなぜだか嬉しくなって、小さな子供のように父親に抱きつこうと腕を伸ばした。
首に手を回して力いっぱい抱きしめるが、父親は昔のように大きな手で私を抱き上げてくれなかった。
その代わり、私の額に優しくキスをしてきた。
何故かしら?
不思議に思って顔を覗き込むと、父親であるはずの傍らの男は逞しい恋人に代わっていた。
彼は情熱的だった昨夜とは異なり、一つ一つ確認するような、丁寧なキスを額に繰り返す。
やがて優しいキスは頬を降りて首筋に移動した。
時間をかけてその辺りを探索している。
この時点で、私の体の欲望 が疼きだした。
自分から恋人を引き寄せて潤った唇を重ねる。
その甘さをもっと味わいたくて、舌を差し入れた。
しっとりとした甘味を味わいながら情熱的に応えてくる恋人の名前を、堪えきれずに思わず呼んでしまった。
「岸さん…。」
呼んだ瞬間、恋人は固く身を強張らせ、唇を離した。
そのままベッドの上で金縛りにあったように身動きのとれない私を置いて、柔らかい羽毛が雪のように散っている白くて濃い霧の中へと背を向けて歩き去ってしまった…。
「!?」
私は、車の急ブレーキで目を覚ました。
額を抑えながら意識を集中させる。
夢…、夢を見ていたのだわ。
「お目覚めですか。丁度良かった、もうボストン市内です。」
聞きなれた感情の無い声が何処からか降ってきた。
私は向かい側で涼しげな顔をして座っている仁神堂に気付く。
「えっ?ああ、そうね。」
ハンドバッグの中から小型の鏡を取り出して、衣服と髪の乱れを直し始めた。
「夢を見られていたようですね。」
仁神堂のその言葉に鼓動が大きく鳴った。
嫌だわ。
もしかして、寝言を聞かれていたの?
鏡から顔を上げて、
「ええ、そのようね。疲れているみたい。」
と余裕の笑みを浮かべてみた。
持っていた鏡に視線を戻しながら、意地の悪い私の中の悪魔が、
「ああ、そうそう。東京の御爺様にダラスでの調査の報告書を今日中に送っておいて。あと、今日は何故か昼食にアンパンが食べたいのよね。どこかで適当に見つけて買っておいて頂戴ね。」
と氷のような冷ややかな声で言い放った。
仁神堂は、
「かしこまりました。」
と短く答えて再び新聞を広げた。
この男はどんな状況下に置いても決してメモを取るという事をしない。
だが私の言葉を一語一句覚えていて、完璧に仕事を片付ける。
きっと昼までには、この 国で入手困難であろうアンパンを日本の食材屋かどこかで仕入れて用意している筈だ。
私も負けてはいられない。
何故か早鐘を打つ心の奥で、今夜本社に電話してこの男の身元調査を頼んでみよう、と心に決めていた。
私はその時、首の後ろのキスマークが更に濃くなっていたことなど、露ほども知らなかった。
「オフィスにこのようなものが届いたのですが。」
ノックをして社長室に入ってきたのは仁神堂(にがみどう)だった。
私は、サインしていた書類の山から顔を上げる。
その手には茶封筒が握られていた。
私は嫌な予感がした。
仁神堂の顔はいつもながら無表情だったが声音がいつもと違っていた。
どこがどう違うのかと聞かれても上手く説明できないが、いつもより低くて、なんとなく怒りを秘めたような、そんな声だった。
私の予想通り、その茶封筒の中から『仁神堂 浬(にがみどう かいり)に関する調査書』と書かれたレポートを取り出して私に見せてきた。
しまった。
どうして私が手に入れる前にこの男の手に渡ってしまったのだろうか?
「ああ、それは…。」
と言いかけた私を
「社長が私にご興味をお持ちだとは思いもしませんでした。」
という言葉で制してしまった。
仁神堂は強い声音で続ける。
「私のレジュメ(英文履歴書)はもう既にお手元に有る筈です。」
彼のレジュメには何度も目を通していた。
東京大学の社会学部を卒業した事やハーバード大学大学院で法科の LeD を取得した事。その上、ニューヨーク州公認弁護士資格すら有している事実も知っていた。
「ええ。持っているわ。」
でも、この頼りない二枚の紙切れを読めば読むほどこの男の過去について興味を持った。
「私はそれで充分だと思いますが。」
と言いながら大きなデスクの前に座っている私の前に立ちはだかる。
「従業員について…特に、四六時中行動を共にする個人秘書についてもっと良く知りたいと思うのは、上司として当たり前の事だと思うのだけれど。」
私の口をついて出たのはこんなにも説得力の無い、弱々しい言葉であった。
「それならば、直接私にお聞き下さった方が早いのではないでしょうか。」
今日の仁神堂は無表情ながらもいつもより言葉が攻撃的だ。
恐らく、怒っているのであろう。
「聞いたら答えてくれたの?私の質問に?いつも無口で無表情の貴方が?」
あはははは、と声を上げて笑い出す。
私はこの冷血漢が怒っているという事実が無性に可笑しかった。
仁神堂は方眉をあげる。
「質問さえしてさえいただければ。…何なりと。」
と言った後、
「これは、要らないでしょう。」
と踵を反して部屋を大股で横切り、手に持っていた調査書を全部片隅に置いてあるシュレッダー機にかけてしまった。
「あっ。」
驚愕した私は、声も出なかった。
いままでこんな突拍子も無い行動に出た仁神堂を見たことが無い。
仁神堂は腕時計に目をやりながら、
「鈴木様がいらっしゃるまであと十分ほどあります。丁度いい機会ですので、ご質問がおあでしたらさあどうぞ。」
と言って私のデスクの前の椅子を引いて腰を下ろした。
さあどうぞ、と言われても……。
私は冷静に考えた。
調査書なら、この男の手を介さずまた手に入れることが出来る。
今度は極秘で。
だけど今は、仁神堂とこのやりとりが楽しめそうだった。
私は口の端を引き上げてニヤリと微笑んだ。
こんなチャンスは二度とないかもしれない。
「そうね…。出身はどこなの?」
とりあえず、英文の履歴書に書かれていない事から聞こうと決めた。
「生まれはシアトルです。家は横浜にありますが。」
声音はまたいつもの冷たい感情の無いものに戻っていた。
眼鏡の奥で茶色い瞳が真っ直ぐ私の目を射る。
「幼少時代はシアトルで過ごしたの?」
だから彼の英語は流暢なのだろうか?
日本語訛りは一切無い。
「まあ、そのようなものですね。」
「歳は?」
「三十三になります。」
私よりも年上だとは思っていたけれど、三十を過ぎていたなんて…。
「家族構成は?」
仁神堂は長い睫毛を落として低く唸るように答えた。
「両親は既に他界しました。兄弟も、おりません。」
なるほど。
これで何となく仁神堂という男の概観が掴めて来たように思えた。
「それは…。ごめんなさいね。」
「いいえ。昔の事ですので。」
しばしの沈黙。
突然、『質問しろ』と言われてもそうなかなか質問など思いつかないものだ。
仁神堂は再び時計に目を落とす。
「あと八分ですね。もう質問はないのでしょうか?」
「えっ?あ、ああ。えっと、何故うちの会社に入社したのかしら?弁護士の資格まであるのに。」
これは以前から不思議に思っていたことだ。確かに会議中、私は仁神堂の法律的な助言によって何度か救われた事があった。
「それは既にレジュメの方に書いておりますが、私は、貴方の祖父の敬一郎様の経営方針と人間性に幼少の頃から憧れておりました。このような素晴らしい方の下で働いてみたいと。」
「そうなの…。」
学歴の無い私の祖父は一代で財を成した。
戦後町の小さな電気屋、國本電気をゼロから始めて世界に誇る日本の電気機器会社、KUNIMOTO JAPAN にまで広げた男である。
その経営手管と人間性に惹かれて人が集まりここまでになった。
私も祖父を誰よりも尊敬している。
「他には?」
仁神堂が沈黙を破った。
私は考えを巡らせる。
「そうね…仕事が休みの日は家で何をしているの?」
もう彼の私生活についてしか聞きたいことはなかった。
「エクササイズをしたり、本を読んだりしています。」
「あなたには苦手な物とかあるのかしら?」
この冷徹男に苦手なものがあるとしたら、是非とも聞いてみたい。
「さあ、考えたこともありませんが…あえて言うならば日本語の敬語でしょうか。」
なるほど。
こっちで育っていれば敬語を使いこなすのは難しいかもしれない。
別に気に留めたことも無かった。
またしばしの沈黙。
私は意を決して、遂に一番聞いてみたかったことを聞いてみる事にした。
「仁神堂、あなた結婚はしているの?」
三十三歳であれば、結婚していてもおかしくない。
子供もいるかもしれない。
何故今頃になって私はそんな事に興味を持ったのかしら?
聞いたからってどうするつもりもないけれど…。
「ぷっ。」
空気が一瞬揺らいだような気がした。
仁神堂が私の下で働き出して一ヶ月ちょっと。
私は、今、この瞬間、初めてこの男が笑うところを見た。
この質問の何が面白かったのだろうか?
口元に拳を置きながら突然ふきだした。
形の良い唇の両端を引き上げ、皺をつくって仁神堂は顔を崩す。
くっくっく、と小さく笑い声を上げる。
不思議だわ。
何故だかその破顔した顔と柔和な薄茶色の瞳から目が離せなくなってしまった。
「しておりません。今は対象になりそうな相手すらおりませんので。」
「そ、そう。」
こんな男の笑顔がなんだって言うの?
私は氷の女王、私は氷の女王…。
と呪文のように唱える。
そんな冷静になろうとする頭の中とは裏腹に、胸の中は熱く締め付けられた。
仁神堂はまだ顔に笑みを称えながら、視線を腕時計に下げる。
と、その時仁神堂の携帯が鳴った。
「社長、失礼致します。…もしもし?」
私に背を向けて電話に出た。
「かしこまりました。お通しください。」
と、言って電話を切った仁神堂はいつもの仁神堂に戻っていて、
「もう鈴木様がご到着なされました。すぐ社長室へいらっしゃる事でしょう。」
と、振り向きながら私に伝えた。
「ねえ、仁神堂。」
そう。
こんな男なんとも思っていない。
私は彼の上司。
ただ、それだけなのだから。
だから......この質問だけはしなければ。
「最後の質問。あなたはこの間の、ジェットでのキスをどう思ったの?」
椅子に深く腰かけ、足を組みながら私は不敵に笑って見せた。
部屋の明かりが彼の眼鏡に反射して表情を読み取ることが出来ないが、仁神堂は再び方眉を上げながら、
「どう思ったか、ですか?」
と聞き返した。
私は頷く。
暫く間を置いて仁神堂はゆっくりと口を開く。
「それは…。」
コンコン。
言いかけた仁神堂の言葉を消すように大きくノックがした。
仁神堂はドアを振り返る。
席を立ち、
「…ご到着なされたようですね。社長、お通ししますよ。」
と言ってドアを開ける。
私は彼の返事を聞き逃した事に少し落胆しながらも、頭をいつものビジネスモードに切り替えた。
顔に笑みを称えて席から腰を上げる。
鈴木氏との退屈な個人会議中、始終私の隣で黙って立っていた仁神堂は、話も退屈の極みに入って私がそろそろ打ち切ろうかと思い始めた矢先、
「社長。」
と言って突然私の耳元に顔を寄せてきた。
いつものように小声で経済的な助言をしてくれるのかと思いきや、彼は低くて感情の無いいつもの声音で一言呟いた。
それを聞いた私の体の温度は一気に上昇する。
仁神堂はその後も、何事も無かったかのように無表情で私たちの会話を聞いていた。
私はまたしてもこの男にやられた。
仁神堂は鈴木氏と談話中の私に、
「あのご質問のお返事ですが、もう一度試してみたい、と私は思いましたね。」
と涼しい顔で答えたのであった。
クリスマスマジックを信じていたのは子供の頃の話。
感謝祭が過ぎると、何処も彼処も赤と緑に街は染まる。
あの頃、小さかった私はサンタさんが読めるようにと、毎年欲しいものをクリスマスカードに書いて、ツリーの下に置いておいた。
カードはクリスマスの朝、プレゼントに代わっていた。そしてサンタさんからの
「ありがとう。メリー・クリスマス!」
との置手紙を見る瞬間が楽しみで、その日だけは早起きした。
で、今はというと、私はクリスマスだというのにオフィスでの残務に追われていた。
あと三十分でこれを終わらせたら帰宅し、用意をして八時には 『ニューヨークエブリデー』の社主、サリンジャー女史主催のクリスマスパーティーに行く事になっていた。
この国ではクリスマスは家族と一緒に過ごすのが一般的なので、恋人の岸さんもカリフォルニアの家族のもとに戻っていた。
「仁神堂、もう帰っていいわよ。」
国民の休日の夜までつき合わせたら悪いような気がして、私は午後から彼に半日休暇を与えた。
この男が、今夜どこで誰と何をするのか知った事ではないけれど、彼は潔く、
「そうですか。有り難う御座います。」
と軽く一礼して帰宅した。
家に帰ってパーティーの支度にとりかかった私に、一つ目の悪夢が襲った。
寝室の鏡台の上を片付けようとして、隅に置いてあった香水を肘でぶつけて落としてしまったのだ。
板張りのフロアーに、紫色をした硬そうな硝子の容器は意外にも脆く砕け、ベッドルームの鏡台のあたりに強烈な匂いを充満させた。
いつものように使用人を呼ぼうとして、休暇を与えたのだと思い出す。
仕方なく自分でガラスの破片を拾い、雑巾を探し出して板張りの床を拭いた。
微量で香りの丁度よい液体は、大量だと匂いが強すぎて人を酔わせる。
時間が無いので、適当に水拭きしておいたのがまずかったらしい。
「きゃあっ。」
今度は立ち上がろうとしてコントのお約束の如く、無様に自分で拭いたばかりの床に滑って転んでしまった。
その刹那、右足首に激痛が走った。
二つ目の悪夢であった。
「……なんてついてないのかしら…。」
パーティーまであと二時間半。
シャワーを浴び、化粧をして、イブニングドレスに着替えなければならないのに、私はどうやら足を痛めてしまったらしい。
自分の情けなさに脱力し、そのまま暫く床から起き上がれなかった。
「どうしよう。」
私は頭を巡らせた。
日本にいる祖父の代わりに会社を代表してこのパーティーに出席するのは今年が初めてだ。
サリンジャー女史を初め、各界の著名人やその家族も顔を出す。
出席できなければ、会社がどれだけ損をするだろうか。
冷静に考えなければ。
私はよろよろと立ち上がり、びっこを引きながらも歩いて数歩先のベッドの上に腰を下ろした。
三十分後。
結論が分かりきっている事を考えるのも億劫になって、腫れだした足首を放置したまま私は仰向けに寝転がり、高い天井を眺めていた。
用意にとりかからなくてはならないのに、時間だけが容赦なく過ぎていく。
と、突然ベッドの横の電話が鳴った。
家にいるはずの仁神堂の携帯からであった。
「もしもし。…何かしら?」
どうせ用件は残務についてか、明日以降のスケジュールについてなのだろう。
仕事以外で私に電話してきた事など一度もなかった。
私は暗い声で電話に出る。
今は誰とも話す気分にはなれない。
特に、仁神堂とは。
「社長、突然のお電話申し訳ございません。ただ、明日のNY発成田行きのJNAのフライトが雪の為キャンセルになりそうですので、明後日に変更した事だけをお伝えしようと思いまして。」
案の定な用件だった。
わざわざ休みを与えたのに、この男は家で仕事をしている。
「…そう。…分かったわ。」
力なく答えたが、仁神堂は続ける。
「明後日帰国してからスケジュールがやや過密にはなりますが、その分明日はごゆっくりお休みください。」
「…有り難う。」
暫しの沈黙。
「…それでは社長、失礼致――。」
と電話を切ろうとした仁神堂を、何故か頭より先に口が、
「ちょっと待って!」
と言って止めてしまった。
ああ、私は何をしているのかしら?
「……何か御用でしょうか?」
訝しげな響きを持った声が電話先で問う。
今、私の周りで頼れる人間はこの男を置いて他にいなかった。
私の足首について、何か良いアドバイスをくれるかもしれない。
「ちょっと…十分だけでいいから、来てくれないかしら。」
一か八かで聞いてみた。
セントラルパークの傍のホテルを家代わりにして住んでいる彼の所から、私のブロードウェイ沿いにあるコンドまで車でそう遠くは無い。
仁神堂は何故わたしが呼び出すのか理由も問わずに、
「……畏まりました。すぐに参ります。」
と静かな声で電話を切った。
「どうなされたのですか、社長。」
私の姿を見た、仁神堂のやけに落ち着いた開口一番の言葉であった。
私は足が痛くて何もやる気が起きず、家着姿でずっと右足を投げ出し、左膝を抱えたような体勢のままベッドの上でうずくまっていた。
急いで来たからなのか、仁神堂はいつもの埃一つ無いカチッと決まったスーツ姿とは異なって、 黒い髪は無造作のまま、大きめの白いTシャツとスェットパンツにジャケットを羽織っている。
心なしか息が弾み、肩がいつもより忙しなく上下しているように見えた。
「仁神堂…。」
もしかして、私の為に急いで駆けつけてくれたのかしら…?
いや、そんな筈はないわね。
「足を、どうかなされたのですか?」
言いながら仁神堂は大股で近寄ってきてベッドの前でひざまずき、確認するように腫れ上がった私の足首に手を触れた。
外の冷気で冷えたらしい、脈の通っていないような冷たい指先が何度も私の足首の上を這った。
軽く押されると、耐え難い激痛が走った。
「つっ。」
「捻挫…よりひどいですね。でも、折れてはいないようです。脱臼なされたのかもしれません。」
「脱臼…?。」
「氷は、台所にありますね?」
「ええ…。あの――。」
「まず冷やします。お話は、その後で。」
仁神堂は私が言いかけた言葉を落ち着いた声で遮り、立ち上がってキッチンの方へと姿を消してしまった。
「今夜は、確かサリンジャー女史のクリスマスパーティーでしたね。」
仁神堂は私に氷の入った袋を渡しながら真顔で聞いてきた。
私は無言で頷く。
「御出席なさるおつもりでしょうが、その足では無理ではないでしょうか。」
「でも、私が行かなかったら会社が…。」
「社長。私が今から女史に連絡を入れておきます。ドクター松山にも明朝一番に足をみて頂くよう予約を入れておきますので、明日からの日程の為にも、今夜はどうか安静にしていてください。」
「そんな事出来ないわ!」
と口に出す暇もなく。
手で素早く私の動きを制して、仁神堂はジャケットから携帯を取り出し電話をかけに私の寝室を出た。
ベッドに再び取り残された私の目の裏には、初めてみる仁神堂の私服が焼きついていた。
普段着の仁神堂は、私が今まで感じた事もない強い男の精気を匂い立たせていた。
一部の隙も無いスーツ姿に比べ、ラフな格好の彼は実に男らしい精悍さに溢れていて、私好みの苦味走った魅力的な男に映った。
嫌だわ、私った ら…。
「眼科に行かなくちゃ。」
苦笑し声を出して、自分を否定してみた。
数分後。
「明日朝九時に予約を入れておきました。ドクター松山のオフィスはご存知ですね?あと…キッチンを勝手に詮索いたしました。赤ワインはお嫌いでしょうか。」
豊かに香る赤い液体が、指紋一つない透明に輝くグラスに半分注がれてある。
ベッドの上の私の手に持たせながら、仁神堂は聞いてきた。
「いいえ。ありがとう。」
一口つけると、その濃厚な葡萄の香りが口いっぱいに広がった。
「ごめんなさいね。クリスマスだっていうのに呼び出してしまって。しかも雑務までさせてしまって。」
ベッドの横に設置された円形テーブルの椅子に腰を下ろしながら仁神堂は自らもワインに口をつけた。
「これも仕事ですし、今夜は別にこれといった予定は御座いませんので。」
……沈黙。
この男とはどうも仕事以外の会話が弾まない。
でも、そういえば、この間家族はいないと言っていたわね。
…ついでに恋人も。
今年、クリスマスを独りで過ごさなければならないのは私も同じだけれど。
「……社長。質問をしてもよろしいでしょうか。」
ワインをテーブルに置いて、静かに仁神堂が訊ねてきた。
顔は、いつも通り真剣。
ただ、ラフな格好が違う雰囲気を醸し出している。
「えっ?ええ。何かしら?」
「私の顔に、何かついているのでしょうか?」
「は?え?いや、いつもと仁神堂の雰囲気が違うから…。」
私は指摘されるまで、自分が仁神堂を凝視していた事に気付かなかった。
魅力的に見えるだなんて口が裂けても言えないわ。
仁神堂は再びワインに口をつける。
「それは…、どういう意味なのでしょう?」
意味深に方眉を上げて、仁神堂は問う。
「どういう意味も何も、そういう意味よ。」
私は苦笑しながら肩をすくめて言った。
仁神堂は何故かかけていた眼鏡をはずして、テーブルの上に置く。
「社長は先日……。」
言いながら額にかかっていた前髪を無造作にかき上げ横を向く。
「私にジェット機内での出来事についてお訊ねなされましたね?」
何を言い出すのかしら、この男は?
「そんな事聞いたかしら?」
と、しらを切った私を無視して仁神堂は続ける。
「その時の私の答えを、覚えておられますか?」
端正な顔の、茶色くて澄んだ二つの怜悧な瞳に射られて、私は一瞬、瞬きを忘れてしまった。
今夜の私は、何かがおかしい。
いつものように強がりや皮肉で言い返すことが出来ないなんて、絶対におかしいわ。
「お、覚えてないわ。」
「そうですか。」
また一口ワインに口をつけて仁神堂は優雅にグラスをゆする。
やはり仁神堂は眼鏡が無い方が似合っている。
この見慣れない普段着も、彫りの深い整った顔立ちも、この寝室という空間にこのシチュエーションも、足を痛めて精神的に弱っている私の心を惑わせるのに充分な要素をもっていた。
…なんて言い訳じみているわね。でも……。
「仁神堂。」
「はい?」
「実行…してもいいわよ。」
仁神堂は無言で小首を傾げる。
私の苛立ちが募った。
分かりきっているくせに、この男は…。
「だから、その、セクハラに値しないのであれば、もう一度試してあげてもいいわよ。」
「……。」
仁神堂はワインを置いて、私を見下ろした。
硝子細工のような薄茶色の瞳が艶めいている。
それでも、何も言わないでじっとしていた。
「だから、こう!」
と、私は仁神堂のTシャツの胸倉を掴んで引き寄せた。
微量ながらに、あのコロンの匂いが漂う。
仁神堂の匂い。
それは、この間のジェットの時のような、優しくて、丁寧で、心地好いキスだった。
でも、今回ばかりは私の理性がそれだけで済ましてくれそうになかった。
足首は痛いのに、体の他の部分は快楽で疼きだす。
首に回した手からは仁神堂の、微かに湿っている熱い体温が伝わった。
「今回は…これだけでは済まないかもしれませんよ…?」
息も切れ切れのキスの合間、仁神堂は顔を上げた。
その顔には、複雑な色が浮かんでいた。
無口、無表情の奥には感情があるという事実に、今更ながら気付いた。
「……やめないで。」
もう、どうでも良かった。
ただ、やめて欲しくなかったから。
三つ目の悪夢。
クリスマスの今夜、私は秘書の仁神堂 浬と一夜を共にしてしまった。
注:仁神堂の聖夜バージョンをご覧になりたい方のみ下(↓)をクリックしてください。
『聖夜XXX』へGO
何ヶ月ぶりかに降り立った東京は、雪は無くともニューヨークと同じくらい寒くて乾燥していた。
幸いな事にあの夜から特に変わった様子も無く、仁神堂は私と普通に接していた。
たった一夜の迷いごとで悩む年頃じゃないじゃない、と自分に言い聞かせても、やっぱりあの日以来私の彼に対する言動は微妙にぎこちない様な気がする。
今回、私は東京本社の祖父に呼ばれて七日間だけ里帰りをした。
その間、日本各地で重役会議やら日本女性の世界的活躍に関する講演(私は出たくなかったのだが、仁神堂が勝手に決めてしまった)やら、経済雑誌のインタビューなど年末にも拘らず予定は目白押しだった。
「お爺さま!!」
久々に実家の門をくぐった私が一直線に向かった先は、祖父のいる書斎だった。
松葉杖をついて不便この上ないが、しょうがない。
書斎の大きな机で仕事をしていた祖父は、顔を上げた。
もう七十を過ぎているのに新しい事が大好き、その歳で去年スノーボードまで挑戦してしまった飽くなき好奇心が、彼を実年齢より十歳は若く見せているのだろうか?
顔は皺くちゃで髪の毛は見事な銀髪なのに、背筋はピンとしていて老いを感じさせない。
去年会った時とまるで一緒であった。
祖父は眼鏡を外して私を見つめる。
「おお、英恵(はなえ)か!!久しぶりじゃな…。??どうしたんじゃ、そ
の足は?」
そう言いながら戸口の私の方へ来て、暖かいエネルギーに満ちた大きな抱擁をしてくれた。
「この間転んでしまって…。お爺さまは全然変わりないようで何よりだわ。」
ププッ、と自嘲気味に噴き出した私を庇いながら、祖父は私を傍の椅子へ座らせた。
「元気じゃぞぅ。今日はお前が帰ってくるからオフをもらったわい。お前も元気そうでなによりじゃ。ちょこっと痩せたみたいじゃがな。慈英は今研究所に篭っていて留守だが、夕飯までにはもどってくるじゃろ。」
慈英とは、私の弟だ。
私とは正反対で会社の経営には一切興味を持たず、研究所に篭って電気系統の研究をしている。
「では、夕飯の時会えるわね。」
祖父は深く頷いてから、口を開いた。
「秘書の仁神堂くんはどうしている?」
彼の名前が出てドキリ、とする。
「彼は…成田からそのまま横浜の実家に向かいました。」
「ほう…そうかね?彼も帰国したか…。ふーむ。」
祖父は顎に手を置いて暫く考え込んだ。
「日本の方はどうですか?」
私は沈黙を破って仕事の話を始めた。
途端に柔和だった祖父の顔が厳しくなる。
「お前も知っての通り不景気でな。クリスマスの売り上げも散々じゃった。まだ大きな煽りは受けておらんが、下請け会社は幾つか潰れてしもうたしのう。まあ、お前もこっちの状況は耳にタコが出来るほど聞いておろうが…。」
「ええ…。」
「実は英恵。今夜の夕飯の時に言うつもりなんだが、大事な話がある。それまで風呂に入ったりしてゆっくりしておいで。檜風呂は久しぶりじゃろ?」
ニコっと表情を和ませて祖父は深刻になりそうだった話を打ち切った。
「そうですね。」
私も松葉杖をついて席から立ち上がった。
「久々にお爺様に会えて、実家に戻れて嬉しいです。」
最後の祖父の言葉が気になったが私も祖父に笑顔を向けた。
「堅苦しいのは嫌いじゃ!!」
との祖父の我が儘で、私の実家の敷地内には和風の建物と洋風の建物の二つが建っている。
もちろん祖父は日本庭園風な屋敷の方が落ち着くのか、そっちの方に住んでいて、私と弟と今は無き両親は、洋館の方で生活をしていた。
もちろん弟はまだそっちで生活しているし、今夜の「夕食」というのは祖父の家の方で、という意味である。
時差ぼけで生じた眠気は、広くてゆったりとした香り良い檜風呂に入った後消え去った。
洋館の方の自室で秘書達や重役達に電話で指示を与えていると、メイドが呼びに来た。
夕食の用意が出来たので和座敷に来るように、との事だった。
「慈英!!久しぶりじゃないの!!」
人見知りが激しく(というより人嫌いで)滅多に顔を見せない慈英は、暫く見ない間に立派な若者になっていた。
姉の自分が言うのも何だが、顔は悪くない。
悪くは無いのだけれど…。
「お久しぶりです、お姉さま。」
端整な顔に品の良い笑みを浮かべて、慈英は挨拶した。
これで極度の電気オタクでなければ…といつも思う。
電気関係以外の事に関して、彼は何も興味を持っていないのである。
「相変わらず研究所に篭っているようね。」
「仕事ですからね。」
「彼女は出来たの?」
彼の人生二十五年。
女の「お」の字も聞いた事が無い。
絶対におかしいと私も思って昔こっそり調査をさせたけれど、そういう気は一切ないという。
「先日生まれて初めてお見合いをしてみました。」
「ええっ??女の子とまともに付き合ったことも無いのに、お見合いしてしまったの?あなたまさか…?」
驚きと不安は的中した。
「面白い方でしたので、結婚を前提にお付き合いしてみる事にしました。」
はあぁ、と私は深いため息をつく。
よく相手が承諾したものだわ。
いや、相手もお金に目がくらんで弟を落とし入れようとしているだけのかもしれない。
世間知らずの弟を持つとこういう事になるのね、などと思いながらも苦笑混じりに
「では、今度その方に会わせて頂戴ね。」
と言っておいた。
「おおっ、二人とも揃っていたか!!」
上機嫌で部屋に入ってきたのは祖父であった。
「今日は久々に家族が揃った事だし、料理長に頼んで飛びっきりのを作ってもらったからな。」
豪快な笑いと共に、国本家の晩餐は始まった。
「実はな、近い将来…まだいつとは言えんが、わしが持っている KUNIMOTO の株と経営権を半分お前に譲ろうと思っておる。」
食事も終わりに近づいたとき、祖父は単刀直入に切り出してきた。
「ええっ?」
私は驚いて箸を落としてしまう。
「いやな、まだ続きがあるんじゃが、そのあともう半分を……。」
そこで祖父はもったいぶるように間をあけた。
「仁神堂くんに譲ろうと思う。」
ガッチャーン!!と今度は持っていた茶碗まで落としてしまった。
辺りにご飯が散らばる。
仁神堂ですって?
今、仁神堂って言ったわよね?
何故そこであの感情欠落男がでてくるのかしら?
「お爺様!!何を考えていらっしゃるの!!!!」
私はダンッと両手をついた。
久々に、感情的になった。
「何って…会社の将来のことじゃが?」
「それなら…それならもっと真剣に考えてください!!なんでそこで赤の他人の仁神堂の名前がでてくるのですか!!」
「何故そんなムキになっとるんじゃ?お前も彼は仕事が出来ると褒めておったではないか?」
「それは…それは秘書としてであって…お爺様の気が違ったとしか思えないわ!!」
「お姉さま、一体どうしたのですか?そんな取り乱してみっともないですよ。」
落ち着いた慈英の声も耳に入らなかった。
祖父は一瞬口をつぐんだ。
言葉を選ぶように時間をかけながら、声を出す。
「家族経営なんてしてると、会社は今に潰れてしまう。そんなのは常識じゃ。わしは、仁神堂君の事は彼が小さい頃から知っとる。英恵はヘンリー夫妻を覚えておるか?」
「ヘンリー夫妻?」
昔、今は亡き父の元で働いていたアメリカ人のヘンリー氏とその日本人妻の事はうろ覚えにだが、覚えている。
数えるほどしか会ったことがないが、彼は父が祖父を助けてKUNIMOTO USA を立ち上げていた頃、個人秘書兼通訳をしていた。
でも確か父が飛行機事故で亡くなった時、同乗していて彼も亡くなったような…。
「母方の姓名を名乗っとるが、仁神堂君は彼の子じゃ。ミスターヘンリーは義一と一緒にあの日死んでしもうた……。申し訳なくってなぁ。あの事故以来わしがあの母子の経済援助をしていたんじゃ。」
今度は、私が口をつぐむ番だった。
大きな和室に、たとえようもない不気味な沈黙が広がる。
そういえば仁神堂は、両親はいない、と言っていた。
ならば…
「は、母親は?彼は両親は無くなったと…。」
何故こんなにもあの男の事が気になるのだろう?
内心そんな自分に苛々しながらも、聞かないではいられなかった。
「彼が高校生の時、亡くなられたよ。元々身体の弱い人だったからのう。生活の面倒はわしが見てあげたが、彼は頑張って自力で奨学金を得て大学、大学院へと進んだよ。」
「………。」
私は暫く言葉を呑んで祖父を熟視した。
「…でも、だからってそれが彼に経営権を与えるのと何の関係があるのですか?ただの同情じゃない!」
「彼の性格は熟知しておる。あんな頭の切れる男には滅多に出会るもんじゃない。TOPになる資格を充分備えておる。わしも一目置く男じゃ、お前だって理由くらい言わなくともわかっとるじゃろ?」
祖父は鋭い眼差しを私に向けたまま、続けた。
「我が社の将来には、どんな状況下においても冷静で正しい判断を下し、先を見る力を持っている人間が必要じゃ。お前には先を見る力があっても、今のように感情的になり過ぎる所がある。」
「でも!!!」
私は納得がいかなかった。
何故、仁神堂なのか。
そんな事、絶対に許せないわ!
私の中で怒りがふつふつと込み上げてきた。
祖父は小難しげな眉間皺を深く刻んだその顔を、軽く横に振った。
「その為に彼をわざわざ一時的にお前の秘書にしたんじゃないか。彼のお陰で色々助かっとるじゃろ?まあ今すぐという話ではないし、仁神堂君にもお前にもこれから何年もかけて学んでもらう事が山ほどある。しかし…彼もお前にはまだ何も言ってなかったとはなぁ。まあ、言うなと口止めしといたのはわしじゃが…。」
私は息を呑んだ。
あの男は、この事を知っていた。
知っていて、私に黙っていた。
馬鹿な私はそんな事も知らずに、一線を越してしまって……
「私は、嫌です!!断固反対です!!」
そう言い切ると、私は傍らの松葉杖を引き寄せ立ち上がった。
そのまま無言で部屋を横切って出て行く。
「お姉さま!!」
長い回廊にどすどすと杖と足音が響く。
出来るだけ早歩きで闊歩したけれど、この不自由な足が憎らしかった。
「お姉さま!!」
慈英が追いついてきた。
玄関を出た所で、私は立ち止まった。
「どうしたんですか、あんなに取り乱してらしくないですよ?」
私は洋館へと続く砂利道を慈英に支えてもらいながら歩き出した。
胸が苦しい。
「なんでもないのよ。ただ…お爺様のお言葉が信じられなかっただけだわ。」
足元の砂利を見つめながら微かな声を出す。
「あの、仁神堂さんの事ですか?話を聞く限りでは…凄い方のようですね。お爺様もかなりその方の事を高くかっているようですし。」
垂れていたこうべを上げて傍らの慈英の綺麗な横顔を顧みた。
「何考えてるんだかわからない腹黒い男よ。絶対認めないわ。」
「…僕はお会いした事がないので何も言えませんが…。」
慈英はそのまま口角をきゅっと結んで、無言で私を部屋まで送ってくれた。
仁神堂の日本の携帯に電話をしたけれど、圏外だった。
これは、驚き?悔しさ?それとも、怒り?
何故こんな気分になるのか分からない。
ただ分かっているのは…
仁神堂は知っていた、という事実。
私は翌朝彼を呼びつけた。
彼女がオフィスに入ってきただけで、その場が華やかになった。
上品に着こなしたスーツも、スラリとした高めの背丈も、整った目鼻立ちも、歩くたびにサラサラと揺れる長い濃茶の髪の毛も、一見虚勢を張った動物のように人を容易に寄せ付けないその冷たそうな容貌も、自分を捉えて放さなかった。
いや、自分だけ でなくその場に居た全ての人間の双眸が彼女を追ったに違いない。
「わしの孫じゃよ。英恵というんじゃ。」
じっと自分の瞳が彼女を追っているのに気づいたのか、傍らの会長はにこやかに呟いた。
「そうですか。お綺麗な方ですね。」
お世辞でもなく素直に口からこぼれ出ただけなのだが、会長は深く頷きながら
「かなり負けん気の強い頑張り屋じゃよ。じゃじゃ馬じゃ。まだ学生じゃが、会社に入ればかなりの切れ者になるじゃろうな。」
と告げた。
そのまま彼女は薄化粧の上に鮮やかな花のような笑みを称えながら、オフィスを横切って自分らのいる奥のデスクへやって来た。
「お爺様、仰っていらっしゃった書類を取りに来ましたわ。」
会長からファイルを受け取りながら、ふと傍らの俺に気がつく。
「こちらは、秘書課の仁神堂君じゃよ。」
「初めまして。」
俺は彼女に片手を差し出した。
こういう社交辞令はよくあるのか、手馴れた感じで俺の手を取り握手しながら
「初めまして、祖父がいつもお世話になっております。孫の國本英恵です。」
と自然な笑顔を浮かべて会釈をしてきた。
成る程、社交術には長けているようだ。
「お忙しいところお邪魔してごめんなさい。とりあえずこの書類を家に持って帰って卒論を書かなければならないので…多分徹夜だわ。だから早々とお暇致しますわね、お爺様。」
そしてちらり、と俺を顧みて
「お会いできて光栄です。」
との決まり文句を言ってから長いロングヘアをフワリと揺らして踵を返した。
國本英恵。
その日以来何故だか彼女の名前が、その人を引き付けるスラリとした容貌が、身のこなしが、俺の頭から離れなかった。
彼女は覚えていないらしいが、これが俺と社長との始めての出会いだった。
午後八時。横浜駅西口にある『チャーリー』という名のバー。
駅を出てすぐ傍のビルの地下にあって、昔から隠れたスポットして利用してきた。
何年ぶりかの日本出張早々。
両親の墓参りを済ました後、自宅でゆっくりする間もなく俺は呼び出された。
薄暗いバーをコツコツとハイヒールの音を立てながら、肩で風を切って闊歩する女。
足音だけで誰だか分かった。
案の定バーで一人ウイスキーの水割りを飲んでいる俺の隣で足音は消え、椅子を引きながら無言で隣に座った。
「一年ぶりの帰国じゃない、浬(かいり)。」
手馴れた感じでバッグからタバコを取り出し、一本火を付ける。
「そうか?」
俺は真っ直ぐバーカウンターで働くバーテンダーを見ながら答えた。
本当は、敬語は苦手な方である。
もともと英語が母国語だし、会社と社長達の前ではかろうじて使用しているが、それ以外ではあまり使わない。
いや、上手く使えない。
「今回は、連絡すらくれなかったのね。いつも冷たいけれど、最近更に冷たいわね。ニューヨークに行ってもなかなか会ってくれないし。」
そう言われて初めて隣の女の顔を顧みた。
寺内祥子。
女優。
色っぽい女や悪女の役をやらせたら右に出るものはいない、影をもった感じの官能的で鋭い美貌の女。
KUNIMOTO 入社当時、政界やら芸能人やらが集まるとある大きなパーティーで知り合い、関係を持った。
それ以来、ずるずると続いている。
彼女には色々と他に男がいるようだし、俺の中ではきっぱりと体だけの関係なので、何故彼女がそこまで自分に執着するのか解らない。
「で、何の用だ?」
彼女の自棄気味な言葉を無視して、俺は単刀直入に尋ねた。
時差ぼけなのか、体がだるい。
「あら、ただ会いたいって理由だけじゃ会ってくれないのかしら?だって一年ぶりじゃない?」
言いながら毛皮のコートを脱いで椅子にかける。
豊満な肉体に、これでもかという程強い香水の匂いが辺りに漂った。
彼女の好きなディオールのデューンだ。
「…そんなに経ったのか。早いな。」
細い指でタバコを挟み煙を燻らせながら、茶目っ気のある笑顔をこちらに向ける。
「あなたのとこの社長さん、聡明な若い美人だそうじゃない?この間雑誌で読んだわよ。オイシイ仕事じゃない、そんな美人と四六時中一緒だなんて。私を避けてるのと、美人の社長と案外関係があったりして。」
彼女は俺を試しているのだろうか。
横目でチラリと彼女の顔を伺った。
「関係なんて全然ない。これは仕事だと割り切っている…。」
俺はウィスキーに再び口をつけた。
……。
本当に関係がないと言い切れるのか?
この間、遂に一線を越えてしまった。
彼女にとってそれは一時の気の迷いだったのかもしれないが、自分の中では来るべきときが来たような気がした。
不思議な事に初めて彼女に出会ったあの日から、なんとなくいつかそれは起こるような気がしていた。
付き人のように秘書としていつも行動を共にし、同じ空間にいながら、彼女は自分が放つ色香に気づいていない。
あの、ベッドの上でしなやかに動いた体と普段とは全然違うあどけなさを秘めた表情を思い出すだけで、今でも体が火照るのだ。
「ねえ…。」
祥子は体を寄せてきた。
「ちょっと私のマンションへ寄ってかない?年代モノのワインもあるし、話したい事も山ほどあるから…。」
彼女の意図する事は一つである。
俺は持っていたウイスキーのグラスをカウンターに置いた。
「タバコを…一本くれないか?」
いつもなら絶対タバコには手をつけない。
普段は別に吸いたいとも思わない。
社長はタバコの臭いを極度に嫌っていたし、健康には人一倍気をつけているつもりだ。
なのに今、衝動的にあの肺を満たす煙さと脳への刺激が欲しくなった。
祥子から一本タバコを受け取ると、無言でそれに火をつけた。
「どういう事か、話して頂戴!!」
東京本社に出社した俺を会議室へ呼び出した社長は、どういうわけか物凄い剣幕で怒っていた。
怒声が会議室中に響き渡る。
「どういう、とは?失礼ですが、私には社長がなにについて怒っていらっしゃるのか皆目見当がつかないのですが…。」
彼女が感情的に怒るのを見たのは、久しぶりであった。
「知ってるくせに…私を利用して、欺いて、楽しかった?」
利用?
欺く?
一体彼女は何の話をしているのだろう?
黙って彼女を見つめていると、大きく息を吸いながら黒目がちの目を細めて自分を睨んできた。
「仁神堂、貴方お爺様の持ち株と経営権譲歩のお話を知っていたんでしょう?」
……成る程。
敬一郎様がとうとう彼女に打ち明けたらしい。
俺は深く頷きながら、
「……ええ。存じておりました。」
と答えた。
「全部知っていて私と寝たのね?何が望みなの?私を巧く丸め込んで株を全部手に入れたかったのかしら?これは何? KUNIMOTO へのささやかな復讐?貴方のお父様が亡くなったのは私の父のせいだから?」
社長はそこでハッとしたように口を噤んだ。
流石に言い過ぎたと思ったらしく、口を手で覆って顔を背けた。
俺は一つ、溜息をついた。
そして、きっぱりと言い切る。
「…父が亡くなったのは、ただの事故です。同時に社長のお父様もお亡くなりになられた。でもそれからずっと、敬一郎様は私と母の面倒をみてくれていました。…復讐心など一度も考えた事はありません。逆に敬一郎様に対して、感謝の気持ちで一杯です。社長が仰っている事は見当違いもいい所ですよ。」
彼女は唇を噛み締めながら俯いている。
相当、ショックだったに違いない。
彼女が利用されていると思うのは、無理もない。
きっと金持ちの令嬢、という肩書きだけで利用された事が過去に何度もあったのだろう。
あの夜は…本当に何も深く考えずに行動しただけだった。
不覚だが、会社の事や、株、経営権、更には秘書という立場すら忘れて、ただの男女として夜を過ごしただけに過ぎない。
だが……。
顔は見えないが、社長の細い肩が小刻みに震えていた。
誤解を解かなければならない。
そう思いながら無言でハンカチを手渡した。
彼女は下を向いたまま、ハンカチを受け取り握り締めている。
「私は……。」
と言いかけた時。
バタン、と会議室のドアが開いた。
「おっと……お取り込み中でしたか?」
洗練された身のこなしに鋭利な笑みを浮かべて部屋に入ってきたのは、これから社長が取引会議をする予定だった筒井グループ社長代理の筒井眞人氏であっ た。
彼は今、日本の経済界を担う若手のホープとして全世界に名を知らしめている凄腕の人物であった。
その彼が予定より少し早く、付き人を伴って部屋に入っ て来た。
「ここに直接来るようにとの事だったので。お邪魔でしたか?」
社長は泣いていた涙をさっと拭いて、顔を上げた。
目元は少し赤かったが、それはいつもの厳しいビジネスをする社長の顔だった。
「筒井様ごめんなさい、目の中にごみが入ってしまって…。どうぞお掛けになって。仁神堂、お茶を入れて頂戴。」
目を合わせようせず、彼女は筒井氏に穏やかな笑みを向けながら言い放った。
「………畏まりました。」
俺は軽く一礼してから会議室を出た。
彼女はきっと当分の間俺を避けるだろう。
暫くあの情熱的な双眸が見られないだろうと思うと、自分の中でたとえようもない苛立ちが募った。
注:(文字を反転させてください)にがみどう視点です。筒井グループの筒井眞人氏は、旧サイトで大変お世話になっていた『ddb』管理人ゴロさんの小説『秘密の部屋』の主人公です(只今サイトは休止状態)。大好きな作品で、旧サイト運営当時作者の許可をいただき、脇役で登場させちゃいました。読む人を惹き付けてやまないゴロさんの文章、尊敬です!
⇒『dark deep blue』へGo!
“仁神堂の告白”
「英恵さん、急に呼び出したのに来てくれて良かった。ちょっと聞きたいことがあったから。」
日本で倒れるのではないかと思われた過密スケジュールを無事終えてアメリカに到着した今日、私は日本からの帰国がてらLAに寄った。
許された時間はたったの二時間。
その後はすぐにN.Y.に移動しなければならない。
LAXから直行し、サンタモニカにある岸さんのレストランで久々に彼と会い、食事をした。
和風テイストの青で統一されたシンプルなデザインのレストラン内の寿司バーで二人並んで、お寿司を食べる。
午後四時三十分。
「とりあえず、頼んで。好きなもん好きなだけさ。」
ほぼ一ヶ月ぶりの岸さん。
相変わらず日焼けして、サッパリ爽やかな雰囲気で男らしい。
全米を駆け回る実業家。
そして、一応私の恋人。
今日の彼はカリフォルニアの住人らしく、ラフなT-シャツとハーフパンツにサンダルといういでたちだった。
実業家なのに、スポーツが趣味の体躯の良い彼はこうやって目の前にいるとやはり物凄い存在感がある。
なのに、すっかりその存在を忘れていた。
いや、あの仁神堂との一件があって以来、どうしたらいいのか解らなくて、必然的に避けていた。
岸さんは日本酒を片手にこちらを振り向く。
「君はさぁ、俺に会えない時とか電話で話せない時とか心配にならない?」
やはり、私が避けているのが分かったのだろうか。
努めて笑顔で彼に振り向く。
「……。そんな、ティーンネイジャーのような関係じゃないはずよね?」
「最近…得にクリスマス休暇以降、俺ばっかり君に連絡してるし、電話してもそっけないし、なんか…俺の事避けてる?」
切れ長の目の中の熱い瞳が真摯に訴えてくる。
私の良心が痛んだ。
この人は、嫌いではない。
でも正直、もう前のように熱い何かは無かった。
前のように、寂しさを紛らわす為に彼を求めなくなった。
それに、この間は、結果的に彼を裏切ってしまったのだから…。
岸さんは寂しそうにフッと微笑んだ。
「君はビジネスしてる時は鉄火面なのに、こういうプライベートの事になるとすぐ顔に出る。」
そんな驚いた顔をしていたのかしら?
「ごめんなさい。」
「いや、謝らないでよ。でも、俺、何かした?」
「岸さんじゃないわ。私に問題があるの。…色々と。」
言いながら深いため息が出た。
「あのさあ、俺じゃ助ける事出来ないのかなぁ?一応俺たち付き合っている訳だし、君がいつも一人で頑張ってるのは知ってるけど、俺は君に苦しんでもらいたくない。俺ってそーんな頼りないのか?」
サーフィン焼けした浅黒い顔が心配そうに伺っている。
「俺は、なんというか…君といると安心するんだよね。手放したくなくなるんだ。」
安心…。
そうか、彼は私といると安心しているのね。
私は…彼に安らぎを求めることが出来ない。
逆に…彼といると緊張してしまう。
こんないい人に、嘘はつきたくない。
それは、私の我侭なのだろうか?
時機を見て、彼に全てを話そう。
そしてその上で別れる事になるのならば、しょうがない。
「岸さん。都合がいいとは分かっているわ。でも、もう少ししたら全てを話すから、その時まで待っててくれないかしら?…自分の中で整理がついたら、きっと話すわ。」
岸さんはむっつりとした顔で
「分かった。君を悩ませているものが仕事に関係してると祈るよ。」
とだけ言った。
レストランの駐車場にとめられたリモの中で、仁神堂は私を待っていた。
私が岸さんに見送られながらレストランを出ると、彼も携帯を片手にリモの中から出てきた。
隣に佇んでいる岸さんが、少し怪訝そうな顔をする。
「あれが噂の仁神堂とかいう秘書?…何度か電話で話したけど俺が想像してたより若いね。」
「そうかしら?」
と返事をした刹那、強引に引き寄せられた。
「岸さ…んんっ…。」
一瞬だけだったけど、唇が重なった。
明らかに、見せつけ。
「こんな所でしなくてもいいじゃないの!!」
岸さんは至近距離で私を覗き込みながら、笑い声を上げる。
「ははは。威嚇、威嚇。英恵さん、俺、待ってるから。君が忙しいのは充分承知だけど、君の力になりたいし、俺は何があっても君を諦めないからね。」
手を振る岸さんに背を向け俯きながら私はリモに向かってパーキングロットを歩き出した。
顔が火照っているのは自分でも分かっている。
まだ痛めた足を庇うようなびっこだったが、ひたすらリモまで歩いた。
きっと仁神堂に見られただろう。
電話を終えたらしい彼は何も言わず黙ってリモのドアを開けた。
私は車に乗り込んだ。
フリーウェイを走っているLAXまでの道のりは、重苦しい沈黙に包まれていた。
この所私はずっと仁神堂を避けていたから、下手に話さなくて済むのを喜ばなくてはならないのに、彼の様子が気になって報告書を読む振りをしながら上目遣いで向かいに座っている彼を見てしまう。
仁神堂は無言で新聞を読んでいた。
メガネが邪魔して表情は読み取れない。
「何か私にご報告がおありなのでしょうか、社長。」
ふと私の視線に気づいた仁神堂は、新聞を置いて顔を上げた。
「ええ、あれが岸さん。」
彼は頷く。
「…存じ上げております。彼は…こちらの日系社会では有名な方ですので。」
「そうなの。知らなかったわ。」
それは、初耳だった。
仁神堂が既に彼を知っていたなんて。
「電話で応対も何度か致しましたし。…社長。」
彼はメガネの縁を押さえながら低く私を呼んだ。
私は返事をせずに顔を上げる。
「もう、私を避ける必要はないのですか?」
「え。」
「私はあれからずっと社長と腹を割ってお話したいと思っておりました。」
私は報告書に再び目を落とし、低い声で答えた。
「別に、私が話すことはないわ。」
「それならば、聞いてくださるだけで結構です。」
私が無言でいると、仁神堂は続けた。
「社長がここ一週間以上、私との会話を避けていらっしゃるのは知っております。そしてその原因も。私は…貴女を騙そうと思っていたわけではない、という事実を理解していただきたい。」
仁神堂は珍しく早口で、熱く語った。
彼の言うとおり、私はずっと意識して彼を避けてきた。
それは、怒りとも、嫉妬とも、悲しみとも言えない複雑な想いが私を飲み込んでいたから。
仁神堂はゆっくりと言った。
「あの夜は、少なくとも私の方は本気でしたよ。」
その言葉に私は動揺する。
心臓が跳ね上がった。
体をぎこちなく動かした弾みで、膝の上の書類が一枚足元にヒラリと落っこちた。
屈んで拾おうとしたら、向かいに座っていた仁神堂に先を越されてしまった。
慌てて引っ込めようとした手を、強く摑まれる。
「社長。」
「仁神堂、離して。」
「いえ…。」
息が吹きかかるほど至近距離で、彼のメガネとその奥の薄い瞳の中に私が映っている。
「離しなさい。」
「まだです。」
「仁神堂!!」
言葉は彼によって阻まれた。
甘くて上品なコロンの匂い漂う逞しい胸に抱き寄せられて、唇を熱く塞がれた。
あの夜以来、何度も想い出したこの香り。
温もり。
口腔内をくすぐる彼の舌に私も思わず答えてしまう。
この男は、キスが巧い。
この男にキスされる度に、拒絶という単語は頭から吹っ飛んでしまう。
いや、頭が真っ白になる、というべきかしら…。
「社長は後悔をしておられますか?」
やがて唇を離した仁神堂は私を抱いたままの体勢で訪ねる。
真っ赤な顔の私は俯きながら聞き返す。
「何を…後悔しているというのかしら?……経営権と株のお話なら…お爺様のご判断だもの。私が何を言っても無駄な事だわ……。」
それは、私の理性が私に教えてくれた。
「私と関係を持った事を、後悔しておられますか?」
低くて心地よい声が、私の耳元で囁く。
仁神堂の鼓動が聞こえた。
私以上に彼の胸は早鐘を打っている。
「ぶ、部下と上司だもの。当たり前じゃない!」
「……そうですか。」
さっと、彼が身を離した。
茶色い瞳が私を見下ろす。
「後悔しておられるなら、これから社長はどうなさりたいのでしょうか?」
その冷たい言い方に私はカッとなった。
「どうもこうも、あれは一夜の気の迷いで――」
「何も無かった振りをしろ、というのですか?」
言い返そうとした私の言葉を、仁神堂は遮る。
「……そうよ、忘れて頂戴。私も忘れるように努力するわ。」
仁神堂を見上げると、彼は初めて私から視線を逸らした。
気のせいか、ふっと寂しそうな表情だったような…?
いいえ。
気のせいだわ。
私は自分を強引に納得させた。
彼はそのまま横を向く。
「…この話題は、当分避けた方が無難でしょう。それよりそろそろ空港に到着致します。社長は化粧をお直しされた方がよろしいかと。」
仁神堂はそのまま新聞をたたんでブリーフケースにしまっている。
私は茫然とそれを見つめていた。
手を伸ばさずとも彼の体温をヒシヒシと感じる距離なのに、彼は私との間に見えない壁を作ろうとしていた。
そうだわ。
これが私の望んでいたこと。
今までのことは無かった事として目を瞑ればいい。
なのに、気づいてしまった。
彼の二の腕を掴む。
「仁神堂。あなたは何を私に望んでいるの?言ってくれないと分からないわ。」
ブリーフケースを閉め終えた仁神堂は静かに顔を上げて私を見返した。
「私は…お爺様が仰るこの会社の未来の事は、お爺様にお任せするわ。でも…。」
真っ直ぐに私にふりかかる彼の視線を、目を逸らさずに受け止める。
「でも、私には貴方の助けが必要。」
仁神堂は口角を引き上げてふっと小さく微笑んだ。
ゆっくりと、言葉を選びながら彼は語りだした。
「私は、貴女が思っているような感情欠落人間ではありません。ただの男です。部下として社長をお慕いしていると同様、初めてお会いした日から一人の男として貴女を意識しておりました。会長のご決断において社長がご納得できないのであれば、謹んで辞退しようと思っております。……今の私の望みは……。」
そこで彼は、一呼吸ついた。
私は熱い眼差しを受けて動悸が激しくなるのを感じながら、次の言葉を待った。
「…秘書としてではなく、私を一人の異性として社長に見ていただくことです。」
無表情は、感情を隠すための仮面。
私は…本物の彼をもっと知りたいと思った。
真剣で、少し強張っている仁神堂を見つめながら私は一言溢した。
「もう、とっくに見ているわ。」
「それは…存じ上げませんでした。」
久しぶりに仁神堂は私に笑顔を見せる。
「LAXに到着したようです。…社長、足元に気をつけて。」
仁神堂に強く手を引かれながら私はリモを降りた。
これから、仁神堂との関係はどうなっていくのだろうか?
この男を失いたくないという想いに気づいてしまった私がいた。
「それは傍から見たらただの我侭よ。」
久々に半日のオフがあった私は、今日久しぶりに学生時代からの友人、弘美の家に招待された。
彼女は大学卒業後、こちらの不動産王と結婚して幸せな家庭を築いていた。
「我侭…かしら?」
私はブルマン100%のコーヒーを一口口につける。
でも、正直その一言に胸が一瞬締め付けられた。
弘美はシフォンケーキを頬張りながら続ける。
「そうよ。二兎追うものは一兎を得ずって諺、もちろん知ってると思うけど、あなたの美形の秘書さんの事も、岸さんの事も遊びならいいのよ。でもね、どちらもキープしていたいなんて、そんな虫のいい話は無いわよ。」
「そう…よね。」
苦々しく頷いて、コーヒーをカップに置いた。
弘美は身を乗り出す。
「ね、貴女最近日本の週刊誌読んだ?私気になった記事を見つけたんだけど。」
「そういうものにはあまり興味がないの。読むだけ時間の無駄だわ。」
とあまり興味を示さない私などお構い無しに、弘美は部屋を横切って雑誌を置いたラックから一冊本を取り出した。
「…有名女優の恋愛スキャンダルの話なんだけれどね。ここ、ここ。この写真に写ってる男の人の顔…目元のモザイクがジャマだけど、誰かに似ていない?」
『人気女優寺内祥子(38)、深夜の密会!!彼女の若いツバメの正体は?!』
と大きな見出しの横に載っていた男女の写真に私の目は釘付けになった。
思わず息を呑む。
そこに映っていた男性は。
スーツ姿では無くとも、目元のモザイクが無くとも、私には一目瞭然だった。
「仁神堂…。」
何処かのバーの前で周りを気にしながらその女優と車に乗り込もうとしている彼の姿があった。
私は目で記事を追う。
「若いツバメの正体は、一流企業勤務のNさん。もう、これだけでも誰だかバレバレじゃない。」
弘美の言葉を無視して、一気に私は記事を読み終えた。
雑誌が刊行された日を確認すると、仁神堂が私について日本へ帰国した週の丁度一週間後だった。
ドキドキと動悸が早まっているけれど、それを億尾にも出さず私はそっと雑誌を閉じる。
「…ショックだった?」
弘美は私を気遣ってオズオズと声をかけた。
「こういう事、英恵に知らせるべきかどうか迷ったんだけど、貴女彼の事本気になり始めているみたいだし、そうでなくとも上司としてこういう部下のスキャンダルは知って置くべきなんじゃないかと思って…。私、余計な事してしまったかしら?」
私はクラクラと眩暈を感じる頭を抑えて頭を振った。
「いいえ…そんな事無いわ。…教えてくれて有難う…。」
弘美は、ほうっと溜息をつく。
「英恵が本気になってしまって、後で傷ついて欲しく無いのよ。もしかしたら…向こうはただの遊びだと思っているかも知れないし。ほら、貴女昔からそういう野心家の男に利用されてたじゃない?私は…。」
「ええ。分かってるわ。昔から私は弘美に心配ばかりかけてたわね。でも、大丈夫よ。仁神堂との事は別に本気でも何でも無いから…。私も、割り切っているし…。」
私は弘美の言葉を遮って、身支度を整え始めた。
そろそろ時間だ。
「久々に弘美と会えて楽しかったわ。でも、また社に戻って仕事をしなければね。貴女の家もニューヨーク郊外にあるんだから、たまには私のコンドにも遊びに来て頂戴。」
他愛ないお喋りが気まずい話題で終わってしまうのに罪悪感を感じたのか、弘美はまだやり切れない表情をしていた。
「あのね、英恵。私は貴方がどんな決断を下しても味方だけど…。でも、もう傷つかないでね。ちゃんと自分の気持ちに正直になって頂戴。」
自分の気持ちに正直に。
そんな彼女の言葉をかみ締めながら、私は笑顔で友人に別れを告げた。
社に戻った私は、早速仁神堂と鉢合わせしてしまった。
社長室に戻ろうとしていた私を、彼は呼び止めた。
「社長、お帰りなさいませ。例の取締役会議の件ですが…。」
「あ…。」
振り返ると、書類を抱えた仁神堂と目が合った。
途端に、目を逸らしてしまった。
「………。」
「わ、分かったわ。今から目を通します。」
そのまま社長室のドアを開けて中に入った私を追って、彼も無言で入ってくる。
彼は書類を私のデスクの上に置くと、そのままデスクの前に立ち尽くした。
「……あの、もう用は無いはずよ。何かしら?」
私は平静を装って書類を読んでる振りをしながら、彼に問う。
「それは、私の台詞です。何かあったご様子ですが?」
仁神堂は、私から納得の行く答えを聞くまで梃子でもここから出て行かなさそうな雰囲気だ。
「午前中のオフに何か?社長はまた何かに動揺していらっしゃるようですね?」
私は俯いたまま、考えた。
彼は知っている。
めったに動揺しない私が動揺する理由が一つである事を。
この男が絡むと、本当に調子が狂う。
彼に、あの雑誌について問い質そうかどうか迷ったが、鎌をかけてみる事にした。
「あの…。日本の週刊誌を読んだのよ…。」
私の頭の上から小さな溜息が聞こえた。
私はそのまま続ける。
「私は上司として、貴方の行動や私生活にとやかく言うつもりはないけれど…。」
「無いけれど?…何でしょうか?」
意外にも冷静で、落ち着いた声音の仁神堂に内心舌打ちする。
私に知れたので開き直っているのだろうか?
「でも、ああいった記事は社の信用にも響くから自粛してもらわないと困るわ。」
そう早口で言い放って、彼を見た。
仁神堂は真面目腐った顔で私を見下ろしていた。
そして、フッと表情を緩める。
「な、何かしら?」
私は真っ赤になって彼を上目遣いで睨んだ。
「いや、社長があの様な記事をお気になさるとは…私としては意外で驚いているのですよ。」
「それ…は、どういう意味かしら?」
私は彼の優しい瞳から目が離せず、じっと見つめた。
「社長ほどの方が、あのようなくだらないタブロイド誌を信用なさっておられるのには驚きです。確かに、私はあの方と過去に関係を持っておりました。だが今は只の友人です。」
過去に関係…。
今は只の友人…。
その言葉が私の頭の中でこだまする。
仁神堂は、
「他にご質問は?」
と訊ねると、眼鏡の縁を押さえた。
「信じる信じないは社長のご自由にどうぞ。もうあのようなヘマをするつもりもありませんが、社長にご迷惑がかかるのであれば友人であっても彼女とは以後会いません。」
以後会わないなんて…。
何もそこまで彼の生活を規制する権利は私には無い。
けれども、もう彼女と会って欲しくないと願うもう一人の自分がいて…。
「それより。」
仁神堂の一言で私は我に帰った。
「?何かしら?」
私は小首を傾げながら仁神堂を見上げる。
仁神堂はまた無表情で真剣な顔になっていた。
「今夜お時間がおありでしたら、一杯如何でしょうか?」
そのまま彼は私に熱心な視線を向け、私の答えを待った。
これは…誘い、なのかしら?
クリスマス以来、彼と仕事外で会っていない。
仕事が忙しく、私生活に全くゆとりが無かった。
「いい…わよ。何時になるか分からないけれど。」
と私が返事をした途端、
「そうですか、それではまた後で。失礼致しました。」
仁神堂は顔に笑みを浮かべて、そのまま踵を返して部屋を出て行った。
久々に見た仁神堂の笑顔だった。
ニューヨークは地下鉄を利用した方が、車を使うより早く目的地に着く事が多い。
だから、ニューヨーカーはあまり車を持っていない上、徒歩を好む。
久々に出張も残業も無く帰宅が許された私に、
「私が運転しますから。」
と、愛車のメルセディスベ〇ツのキーを振って見せた仁神堂は、会社のビルの前で私をピックアップすると、そのまま車を走らせた。
案の定…と言っては何なのだけれど。
私の推定どおり、彼の車はセントラルパークのすぐ傍の某ホテルの地下駐車場の中に入っていった。
彼は最上階から二階下のセミスイートを住居として生活していた。
「どうぞ、お入り下さい。」
と通された部屋は彼らしいと言うか、隅々まで無駄を省いたシンプルなデザインの装飾が行き届いたお洒落な所で。
ガラス張りの窓で覆われた部屋からは、ニューヨークの夜景が堪能できる。
眼下にはセントラルパークの緑溢れる風景が広がる。
きっと仁神堂はここでジョギングをしているのだろう。
「素敵な所ね。」
私は思わずそう口に出していた。
彼は私をリビングに通すと、スーツを脱ぎ捨てシャツの袖を捲くり、ネクタイを緩めて隣に設置されているバーカウンターへ向かった。
「有難うございます。社長は赤と白どちらの気分ですか?」
まだ部屋のなかをキョロキョロしている私に仁神堂が声をかける。
「あ…どちらでもいいわ。」
私は彼のリビングの床に置かれている、ノーマン・ロ〇クウェルの絵に釘付けになった。
「これは…本物ではないのですが、とても気に入ったので購入しました。彼の絵は…こう、テーマがハッキリしていて、細部にまで気を使っていて、好きなんです。」
「そうね。」
彼の絵の説明を聞いていて、仁神堂みたいだわ、と私は思った。
きっと彼を絵に表現したら、こんな感じなのだろうか。
隅々まで気配りが行き届いていて、テーマ性のある…。
そっと私の目の前に赤ワインが出された。
私の前のソファに彼は腰掛ける。
「貴方とは…。」
「社長とは…。」
二人同時に声を出してしまう。
「…。社長からどうぞ。」
仁神堂はワインそう言ってワインに口をつける。
「え?ああ、あの、貴方とは殆ど毎日顔を合わせているけれど…こうやって仕事以外でゆっくりするのは久しぶりだと思っただけよ。」
「私も、同じ事を言おうと思っておりました。」
私は無言でワインに口をつけた。
暫しの沈黙の後、仁神堂は単刀直入に切り出した。
「今日、カリフォルニアの岸様から本社にお電話がありましたよ。」
突然彼の口から零れ出た岸さんの名前に、私はワインを噴き出しそうになった。
「え…?」
仁神堂は、そっとワインをガラス張りのテーブルに置く。
「社長はこの所彼の電話にあまり出ないそうですね。」
仁神堂の言う通り。
私はここ数週間、岸さんを意図的に避けていた。
岸さんの声を聞くと、私の心の良心が痛むから。
弱虫で意気地なし。
私は彼を傷つけるのが怖くて、未だ持って別れ話を告げる事が出来ないでいた。
きっと彼は心配になって本社に電話してみたに違いない。
「それは…私と岸さんの問題で…。」
貴方には関係ない。
と言おうとすると、
「自惚れてもよろしいのかと。」
との言葉に遮られた。
仁神堂はもう一度ハッキリした声で言う。
「それは、私に分があると思って宜しいのかと。」
途端に、私達の間に緊張感が漂った。
「私は、こう見えても独占欲の強い男なのですが…。」
仁神堂はテーブル越しにワインを持っている私の手に触れた。
指先から、彼の脈動を感じる。
それは、私の鼓動と同じくらい速く打っていて…。
私は彼の薄い瞳に宿る熱情の炎を直視する事が出来なかった。
でも、確信をもって彼に一言告げることが出来た。
「岸さんとは…もう多分会わないと思うわ。だから…。」
だから、焦らせないで。
仁神堂は無言で私の手の中のグラスをとってテーブルに置く。
そしてまた唐突に、唇を塞がれた。
角度を変えて侵入してくる、彼の暖かい舌を感じながら…。
「あの夜から、ずっと貴方とこうしたかった。」
耳元で彼の切なそうな声が聞こえたような気がした。
私が今まで見過ごしていた、彼の独占欲の強い男としての一面を初めて見た夜だった。
“仁神堂と社長”
いつも通り朝早い出社後の慌しいスケジュールをこなした私は、何気なく私用のEメールをチェックしていた。
私が唯一私事に費やす事の出来る、短い朝食の時間。
朝、食欲が出ない私はフルーツで軽く済ませている。
コーヒーを片手にすっと新着メールに目を通していると、その中の一件に釘付けになった。
Subject:今NYにいます。
差出人は、岸さんだった。
仁神堂と関係を持ち始めてから、ちゃんと話をつけて別れる事の出来なかった彼。
実際、数ヶ月も連絡をとらず、こんな状態の私達がまだ付き合っているとは向こうも思っていないだろう。
多忙なスケジュールで頭が一杯になってはいても、片隅では分かっていた。
いつかちゃんと彼と話をつけなければならないと。
開いて読もうかどうか、何度か無意味にマウスを動かして迷った末、クリックしてみた。
短いメッセージ。
“仕事で数日間NYに居ます。会って話がしたいので、今夜Bennigan’sで待っています。
貴女が来る事を願って。
岸”
饒舌な岸さんらしからぬ、短い文章だった。それだけに、緊張感が走る。
そっと、ウィンドウを閉じた。
コーヒーを啜って一息つくと、目を瞑った。
Bennigan'sは私達がよく行っていた馴染みのレストランだった。
彼と初めてデートをした日、そこで付き合ってくれと言われた。
何年前の出来事だろうか?
でも、もう、私の心は決まっていた。
今夜の予定をキャンセルしてでも、彼と話が出来るのは今夜が最後だと思ったからだった。
マンハッタンのど真ん中にあるこの高級レストランの名前を知らない人は居ない。
ドレスコードが厳しいので、いくらなんでも仕事のスーツ着では行けなかった。
ホストに名を告げると岸さんはもうとっくに到着していたらしく、案内された奥の席に座っていた。
「よかった、英恵さんが来てくれて。」
私の姿を確認すると、岸さんは一瞬目を瞬かせ、大きく息を吸ってから席から立った。
私の為に椅子を引きながら、そう一言呟く。
彼の邪気の無い、精悍な顔立ちを見つめながら、私は自然と強張りそうになる顔を緩めて笑顔を作った。
そして、喉の奥から搾り出してやっと一言告げる事が出来た。
「大事なお話があって来たの。」
私の堅苦しい言葉を聞いて弱々しく微笑んだ後、岸さんも再び口を開いた。
「うん、分かっていたよ。」
と。
秘書課の部下から連絡があった。
社長の代理で朝から同じ東海岸のワシントンDC支社へ赴いていた俺は、用も済ませホテルへ向かう途中一本の電話を受け取った。
どうやら社長は今夜の会食の予定を、知人とBennigan'sで会う為にキャンセルしたらしい。
彼女のスケジュールを調整し、会食を他の日に埋め合わせておくよう指示した後、電話を切った。
眼鏡の縁を押さえて暫し考える。
彼女の生活は手に取るように分かっているつもりだった。
社長はプライベートな事は滅多な事が無い限り優先しない。
それ程の仕事人間だ。
その彼女が、夜時間を空ける理由は?
そういえば、岸氏率いるKISHIグループが経営困難に陥っていたNYの大手日本食レストランを買収したと、今朝読んだ新聞の経済欄の見出しに載っていたのを思い出した。
フウッと小さく一つ溜息をついた。
可能性は、大いにある。
そうであっては欲しくないと願う自分と、それは仕方の無いことだと思う自分がいた。
時計を見る。
午後の6時。
社長に電話を入れてみたが、電源を切っているのか留守電にかわった。
何度かけ直しても出ないので、諦めて電話をしまう。
フリーウェイを走っている車の窓の外に何気なく目をやると、滞在先のホテルが遠目ながら見えてきた。
「今夜はあそこで宿泊か。」
ボンヤリとそのまま空を眺めると。
陽が傾きかけた空に聳え立つホテルの上を飛行機が飛び、白い建物に影を落としていた。
それを目にした途端、何かが俺の中で弾けた。
もしかしたら、今からでもNY行きのフライトに空きがあるかもしれない。
出来る限り早くNYに帰らなければ。
気付くと俺は、再び携帯を取り出して各航空会社の番号を呼び出していた。
そして、運転手に指示を出した。
「空港へ向かっていただきたいのですが。」
ブロードウェイ沿いのコンドの前でリムジンを停め降りようとすると、コンコンと窓を叩かれた。
「仁神堂…」
今日は朝から出払っているはずの仁神堂が、リムジンの窓を覗き込んでいる。
ドライバーは仁神堂を知っているので、即座にドアを開けてくれた。
「どうして―――」
ここにいるの、と聞き終える前に、引っ張りあげられて強く抱きすくめられる。
もしかして―――?
「会社で何かあったのかしら?緊急?」
「いいえ。」
力一杯私を抱き寄せながら、仁神堂は否定した。
ああ、そうだわ。
考えてみれば当然だ。
今夜の予定をキャンセルするには、秘書に言う必要がある。
たとえ伝えた秘書が仁神堂でなくても、私のスケジュールの全責任は彼にあるのだから、彼の耳に届かない筈は無いのだ。
四季が日本にどことなく似ている東海岸の春は、とても清々しくて気持ちがいい。
爽やかな春風に吹かれて垂らしていた長い髪が、ゆらりと踊った。
「……戻って来られたのですね。良かった。」
全身に仁神堂の体温を感じながら、私は驚きで目をパチクリさせる。
「ずっとここでお待ちしておりました。」
あまりに突然な抱擁に今更ながら我に帰った私は、体を捩って彼の体を離そうと試みる。
が、彼の力は逃すまいと強くなるばかりだった。
「もう少し、このままでいて宜しいでしょうか?」
「え?」
ブロードウェイの歩道のど真ん中で。
ニューヨーカーは道端での抱擁には慣れっこらしく、私達の横を素通りしていく。
傍からすれば普通の恋人同士に見えるのだろうか。
私は抵抗するのをやめ、力無くまだスーツ姿の仁神堂の逞しい胸に体を預けた。
「もし今夜戻って来てくださらなかったらどうしようかと…。」
静かに。
感情を押し殺した低い声で呟く。
彼は知っていた。
私が岸さんと今夜最後に会った事を。
それを知っていて、私を待っていた。
「どうしてここにいるの?私が明日仕事を休むとでも思っていたのかしら?貴方に迷惑をかけたりはしないわ。」
冗談めかして彼に聞く。
この男は。
鉄仮面なのに似合わないことをやってくれるじゃない、と心の中で呟いた。
あのクリスマスの夜もそうだった。
寒い中、息を切らせて私の所へ来てくれた。
気付けば、傍にいて欲しい時、頼りたい時、すぐそこに居てくれた。
私の鼓動と同じくらいの速さで走る、仁神堂の鼓動。
いつものコロンの匂い。
「お帰りが遅いので心配しました。もし、社長が岸様とよりを戻すような事があれば、今までの私の苦労が無になってしまいます。そしたら私はもう、自分の感情を抑える自信がありませんからね。」
あくまでも静かに、けれど熱っぽく仁神堂は語る。
この男も…苦労なんてしていたの?
意外な言葉に戸惑いながらも。
「岸さんとはちゃんと別れたわ。もう、会うことも無いと思うの。」
私は俯いたまま、言葉を選ぶようにゆっくりとそう告げた。
彼の顔を見て話す事が、何故か出来ない。
きっと今顔を上げたら、私はリンゴの様に真っ赤になっている事だろう。
「社長は、それで宜しいのですか?」
感情の抑制された声。
私は仁神堂でいいのだろうか?
「社長はやめてほしいわ。名前で呼んで。」
質問をはぐらかすように、ついまた余計な事を言ってしまう。
両腕を広い彼の背中に廻すと、フッと頭上で忍び笑いが聞こえた。
「社長も、私を名前で呼んでくださるのなら。」
「いいわよ。二人で居る時は対等でいたいから、もう敬語を使わないで頂戴。」
私もつられて笑いながら答えた。
彼の広い胸に頬を寄せる。
お爺様は全て知っていらっしゃった。
私達がこうなる事も承知で、彼を私に遣したのだから。
これからの長い将来、私にはずっと仁神堂が必要なのだから。
「私は…浬がいい。」
「愛してる。貴女がいれば、何も要らない。」
オレハ、英恵ノソバニ居テイイノカ?
器用な男の不器用な質問に、私はイエスと答えた。
朝の光がカーテンの隙間から零れた。
俺の顔に直撃したその光を防ごうと腕で目を覆おうとすると、二の腕をつかまれた。
「おはよう、浬。」
社長である。
ホテルのバスローブ姿のまま、化粧ッ気の無い、けれど爽やかでソープとボディーローションの匂う艶やかな美しい顔が、俺を覗き込んでいる。
「遂に貴方の寝顔が見れたわ。」
茶目ッ気のある笑顔で微笑む。
「貴方血圧高いんじゃない?いつも私より遅く寝て、早く起きるんだから。今日は私頑張って早起きして貴方を起こそうと思っていたのよ。」
上機嫌な笑みを浮かべたまま社長は、バスルームへと姿を消した。
社長レベルのビジネストリップとなると、ほぼ数日置きにある。
NYで仕事を終わらせた後そのままジェットで他州へと飛び、その翌日またNYへとんぼ返りなんてザラだ。
社長…國本英恵と男女の仲になってから…いや、普通の恋人同士とは少し異なっているが、正確には男女のように付き合い始めてからも、その生活はあまり変わらなかった。
社内では社長と個人秘書という体面を辛うじて保っているとはいえ、プライベートな時間は二人で過ごす事が多くなったが。
それに、旅先ではこのように同室で朝を迎える事もある。
俺は、ムックリと体を起こした。
昨夜の熱情で、体が心なしか疲れている。
関節を鳴らして軽くストレッチすると、俺はベッドの下に落ちていたバスローブを拾い上げて袖を通した。
彼女の後を追って静かにバスルームに向かう。
社長は、装飾が凝って広々とした洗面台の鏡と睨めっこしながら化粧をしていた。
俺は開けっ放しの戸口に肩をつけて立ったまま、暫く無言で彼女の作業をジッと見つめた。
「おはよう。」
彼女は俺の眼差しに気付かないほど真剣だったので、声をかけてみる。
「また英語なのね。」
不満そうな声を出し、彼女は俺の立っている戸口へと振り返った。
「やはり社長とプライベートな会話は英語の方が楽ですね。」
つい、いつもの口調に戻って説明してしまう。
敬語をつかわないで、との彼女のリクエストに答えるには、どうやら英語で会話するのが一番自然で楽だと気付いた。
あの日の、あの言葉以来、俺はプライベートな時間の会話の殆どを英語で済ませていた。
「でも、まあ、それでもいいわ。」
彼女は持っていたフェイス用のブラシとパウダーをカウンターに置いて、俺の方に向き直る。
やはり今日は機嫌がいいらしい。
「ふふっ。寝癖がついている貴方を見るのは初めてだわ。」
社長は俺に近づいてきて、俺の髪の毛に手を伸ばしてきた。
小さい子供のように、手櫛で梳く。
とても、気持ちがいい。
こういう時、彼女は大会社の社長という仮面を脱いで、無邪気な一人の女としての顔を見せる。
気付くと俺は体を屈め、血色のいい彼女の唇に自分の唇を押し付けていた。
社長は一瞬驚いたように体を硬直させ、そして俺に応えてきた。
「社長。時間があまりございませんので、ルームサービスでも頼みましょうか。」
名残惜しいと思いながら自制心を働かせ、俺はやっとの事でその一言を搾り出す。
「…わかったわ。」
拗ねたような表情をして、社長は体を離す。
そのままやりかけていた作業に戻ろうとして、ふと、まだその場に立ったままの俺を顧みた。
目が輝いている。
「ねえ。今度時間があったら、バケーションでビーチに行きたいわ。貴方と二人で、会社の事も忘れてゆっくり過ごすの。」
「恐らく、向こう半年は無理だと思われますが…。」
幼い少女のように無邪気にそう提案する彼女の言葉に苦笑し頷きながら、俺は思った。
いつか、まとまった休日が取れたら彼女を誘ってジャマイカにでも行ってみようか、と。
カウンターの俺の目の前に、濃茶色の液体が3分の2程注がれているグラスが置かれる。
炭酸の泡がまだブクブクと立っているその飲み物に視線を移すと、ボウタイ姿のブロンドのバーテンダーが
「あちらのお客様からです」
と俺の後ろを指差した。
またどこかの女か。
又は物好きな男か。
独りでバーにいると、よく知らない人間から飲み物を奢られる。
「有難う」
一口その液体を口につけて、俺はハッとした。
「日本のビールは有るか?」
大概のバーならば、ここNYでも日本のビールは容易に手に入る。
それだけ、日本人観光客やビジネスで利用する輩が多いからなのだろうが。
アジアンフュージョン的な雰囲気が売りのこのバーならば、色々と取り揃えているはずだ。
「ASA〇Iですか?KI〇INですか?それとも、SAP〇RO?」
案の定な返答。
「何でも良い。軽めなビールをこれを俺に出したご婦人に出してくれないか」
「かしこまりました」
俺は出されたラム&コークを嗜みながら、その『ご婦人』とやらに想いを馳せた。
もう4年以上になる。
噂は四方八方から聞くが、まさかNYに来ているとは思わなかった。
「こんにちは。お隣、空いていますか?」
グラスの中の液体を凝視していると、懐かしい声が後ろからかかった。
「こんばんは、だろう?」
基本的な英語のミスを直してやる。
が、口元は緩んでいた。
「何だよ!かっこよく決めよーと思ってたのによ!」
途端、相手の女は日本語の、男のような言葉遣いに切り替わる。
「相変わらずな口の利き方だな、お前は」
俺は人影の出来た横に視線を移し………。
息を飲んだ。
スキニーなのは相変わらずだが、ワンレングスのように切ったセミロングのストレートの茶髪の彼女に、一瞬頭が混乱した。
多少ながら化粧を施しているようだ。
いや、記憶にある佐々木翠のままの筈だ。
ままの筈なのに、何かが違う。
俺は目を細めた。
「あんたも相変わらずだな。門田社長。あ、CEOだったけか?」
撮影かパーティーの後なのか、コルセットのようなドレスを身に着けている佐々木翠は、昔の言葉遣いのまま、俺の横のチェアにさっと腰をおろした。
「ビールありがとな。よく分かったな。日本人……いや、俺だって」
「勘、だな」
そう、勘だ。
隣の女が日本を代表するスーパーモデルとなり、世界各国のランウェイで引っ張りだこなのは知っていた。
今日も5番街を通り過ぎた時、ヴィ〇ンの店頭広告にでかでかと写っていた。
あの、銀色の双眸が通行人を捕らえる。
そして、俺もその姿に一瞬で捕らわれた。
「NYの春コレが開催中だとは聞いていた」
が、まさかここで……このホテルのバーで会うとは思いもしなかった。
偶然にも程が有る。
「お前はここに泊まっているのか?」
俺は肌理の細かい翠の肌を観察しながら訊ねる。
最近は、肌の手入れもしっかりとされているらしい。
化粧のせいか、前あった薄いそばかすも見えなくなっている。
「ああ。月曜までな。ショーが終わり次第、パリに戻る」
人懐こい笑みを浮かべながら、佐々木翠も同じように俺を観察していた。
「紅は元気か?」
「今アフリカに行ってる」
「雑誌の撮影か」
「多分そう」
弟の紅がファッション関係のフォトグラファーから、元々興味の有ったネイチャー系の写真家に転身したのは、2年以上前の話だ。
動物やら、植物やらの写真を撮ってはそれらをナショナル・ジ〇グラフィックなどの各国の雑誌社に寄稿したり、日本の雑誌社の取材にカメラマンとして同行したりしている。
パリに引っ越した佐々木翠と、日本がベースとなっている紅とは遠距離のようだ。
「毎日電話かけてくるけどな」
照れたように頭を掻く仕草は前と変わっていない。
俺は目の前の女をまじまじと不躾に眺めながら、訊ねた。
「どうして俺がここに居ると分かった?」
「調べたから」
彼女は悪びれも無くあっさり答える。
「この上のスイートに住んでるって聞いたからな」
俺と佐々木翠の視線が直にぶつかり、絡まる。
「ほう。わざわざ俺に会いに来たのか?」
喉の奥から唸るような声が漏れる。
ご苦労な事だ。
「あんた忙しいし、いっつもNYに居るわけじゃねえって知ってたから、探すの大変だったぜ」
彼女は照れたような表情を浮かべ、そして真面目腐った顔つきになった。
「最後にあんたと会った日から……あんた俺にさよならも言わねえでさっさとNYに移っちまったし、ずっとどーしてんのか、って思ってた」
「紅からは俺の話を聞かないのか?」
「たまーに聞くけど」
「上手くやっているのか?」
「相変わらずだよ。紅は小姑みてーに煩いけど、多分一生俺の事が好きで、俺から離れらんねえよ」
思わず、フッと鼻を鳴らした。
「大した自信だな。なら何故お前はこんな所で俺に油を売っている?」
俺はずっと、彼女の銀に輝く双眸から逃れられないで居た。
どんな女を抱いても、この挑むような冷たい眼が離れなかった。
4年間ブランクだったものを埋め合わせるかの様に、脳裏に焼き付けるかのように、彼女の姿を食い入るように見つめる。
俺の視線を静かに受け止めながら、翠はビールを一口あおる。
「紅によると、俺は飼いならされた鷹なんだってさ。大空を飛び回って獲物を見つけても、帰る場所はひとつなんだと」
「鷹、だと?」
俺はグラスの中の氷を揺らしながら、口をつける前に聞き返した。
「そう。そんで、今夜の獲物は……門田社長、あんただよ」
「ほう……」
俺は隣の女に向き直る。
「鷹が鷹を狩るのか。面白い」
佐々木翠は椅子から立ち上がり、バーカウンターによりかかりながら俺の前に立ちはだかった。
そこで俺は彼女が膝上のミニスカートを穿きこなしているのに気づいた。
ダボダボのTシャツにパンツ姿の佐々木翠を思い出して、大きな進歩に思わず噴き出した。
「喋り方に変わりは無いが……あの男のような服装はどうした?色気づいたようだな」
「洗練された、って言えよ」
口を尖らせながら、翠は一歩俺に近づく。
いつか見た、挑戦的な笑みを顔に湛えて。
いつだったか……。
ああ、そうだ。
最後に交わった、あの夜だ。
目の前の女のあまりの変貌に、俺の頭が鈍っていたらしい。
いや、この所立て続けに出張に出ていたから、時差で脳内の感覚が上手く作動していないのだろう。
俺も歳か、と自嘲する。
「俺、来年は日本に戻るよ。そんで、覚えてるか?ジムをOPENしようと思ってる」
「ああ、覚えている。駅前に展開するとか言っていたアレか」
つまり、進歩はしてきたらしい。
それは、今目の前に立ちはだかるこの女を見れば一目瞭然か。
佐々木翠は「そうだ」と頷くと、手を伸ばし俺のネクタイを掴んだ。
不意を、つかれた。
薄くグロスが塗って有る彼女のリップが俺のそれを覆った。
荒々しく舌で結ばれた唇をこじ開け、俺の中に侵入してくる。
彼女が啜っていた甘くて苦い液体の残り香が俺の鼻腔を征服し、肺を満たす。
4年ぶりの、彼女との接触を味わった。
「キスは本気の相手だけと言っていたのではなかったのか?」
唇が離れると、俺は逃がすまいと彼女の腰に片手をまわし引き寄せた。
座っている俺の脚の間に、彼女の体が収まる。
「た…社長も、俺を拒絶できたはずだろ?」
「そうだな。だが、しなかった」
彼女の2つのシルバーが、より一層輝きを増した。
ゴホン、と仰々しく咳払いをして、腰に手を当てる。
「社長。あんたに告ぐ。俺はあんたの金も名誉も地位もいらねえ。そんなもんは俺自信がもう既に手に入れた。けど、俺はあんたの心が欲しい。俺は、お前の金目当ての昔の女とは違うからな」
彼女の言葉に、体中の血流が熱く滾るような錯覚に陥った。
つまり、最後に会話を交わした夜から4年という歳月をかけてそれを証明する為に、この女はここまで登りつめたと言おうとしているのか。
厳しい顔つきをしていたのだろう。
佐々木翠が俺の顔を見て、息を潜める。
俺は低い声で訊ねた。
「紅は……どうする?」
「紅には言ったよ。あんたに会いに行くって。紅は知ってたから……。俺がずっとあんたの事想ってたって。悪いけど、俺の気持ちは誰にも止められねえ。あ、心配すんなよ。自傷行為らしきそぶり見せたら もう一生会ってやんねえ、って伝えといたから。失恋が原因で自殺でもしやがったら、俺の孫の代まで呪ってやるって言っといた」
俺が無言でいると、翠は続けた。
「……鷹男あんた、過保護過ぎるぞ。あいつも三十路まっしぐらないい大人なんだ。自分の行動に責任が持てなくて、この先の人生どうすんだよ」
過保護すぎる、か。
そうだな。
そうかもしれない。
つまり、紅を手のひらで転がしているのは。
上手く手懐け教育していたのは、こいつの方か。
彼女の体温が、幾重もの布地を通して俺の内腿に伝わってくる。
腰の手に力をいれ、更に引き寄せる。
「お前はまた、俺と弟と二股をかける気なのか?」
訊ねながら、俺を見下ろす彼女を捕らえながら、熱くなった場所を擦り付けた。
「それは、あんた次第だよ。鷹男」
翠は目を優しく細め、囁いた。
鷹男。
久々に聞く、自分の名。
この女が俺の名を呼んだだけで、中心のものが更に堅くなる。
「ならば……」
俺は立ち上がった。
もっと強く火照りを押し付ける。
「俺の女になれ」
十年以上も告げられた事の無かった言葉が、するりと自分の口から零れ出た。
我ながら、驚く。
翠が俺の首に手を回してきた。
「つー事は?」
耳元に熱い息を吹きかけながら、囁く。
「俺以外の男を抱く事は、許さない。無論、女もだ」
「鷹男、あんたも同じこと約束出来るか?……」
「勿論だ」
「ディール!」
翠の唇が、俺のそれを再度覆う。
俺は、待っていたのだろうか?
この、俺に熱い抱擁を求めてくる女の成長を。
シルバーの瞳に隠された、強い意志。行動力。忍耐。
自分が何年も前に仕掛けたゲームは、俺の知らない間も続いていたようだ。
そして勝者は、佐々木翠。
いや。
そう簡単に勝たせてやるつもりはない。
翠が自室のルームキーらしきカードを2本の指の間に挟んで振る。
「バイ〇グラが必要かどうか確かめてやるから、俺の部屋に来いよ」
バイ〇グラだと?
笑わせる。
俺は彼女に押し当てているモノを意図的になすりつけ、唇が重なりそうな至近距離で囁いた。
「スイートルームでなければ、俺には狭すぎる」
「贅沢者。でも安心しろ。あんたの隣の部屋だ」
「ならば……」
続きはお前のスイートで。
俺は翠を掻き抱き、激しく口付けた。
「す、すんません!!」
静寂を破る大声。
小鳥がちゅんちゅんとさえずる日曜日の早朝。
ベッドの上で、タバコをふかしている女。
そして、誰が見ても笑ってしまうであろう、ベッド脇でがたいの良いマッチョマンがトランクス一丁で土下座している滑稽な姿。
「何を謝っているのかしら?」
タバコの火をベッド横の灰皿で揉み消して、女は無表情で冷たく聞き返す。
いや正確に言うと無表情なのでは無く、元々彼女は普段の表情が乏しいだけなのだが。
男は俯きながら頭を掻く。
「いや、その、あの、自分、昨日の夜の事全然覚えていなくって……えーっと、覚えているのは昨日6ヶ月ぶりに酒が解禁になってバーで飲んでて、それで…。」
「覚えてないの?私達あんなに熱い夜を過ごしたのに?」
マッチョマンの言葉を遮る鋭い一言。
腕組みをしながら、女はベッド下の男を見下ろしていた。
俯いていた彼は、うっ、と言葉に詰まらせた模様。
「私を知ってる?」
「……えっと……。」
しどろもどろ。
唸りながらマッチョマンは男っぽく荒っぽい作りの顔を上げて、ぎこちなく筋肉の隆起した首を傾けた。
答えるのに約1分を要した。
「………。モ、モデルさんか何か?」
困った表情を浮かべながら疑問形で答える男を見て、女はプッと噴出した。
「モデルがこんな歳な筈ないじゃない。」
途端に男の顔が真っ赤に蒸気しだす。
「す、す、すんませんっ。自分、ホント酔ってて、何にも思い出せないっす!!」
男は深々と頭をフローリングの床につけて、土下座する。
「もう、いいわ。私もあなたの名前知らないし。」
「はっ?」
間抜けな声で男は返す。
「私もね、ちょっと嫌な事あって自棄酒飲んでて、昨夜マネージャーとバーに飲みに行ったのは覚えてるんだけど、今朝起きてからずーっとどうやって家に帰ってきたのか、何故あなたが私の横で寝てたか考えていたのよね…。」
「そ…そうなんすか…。」
男はまたも筋肉質な腕を上げて頭を掻きながら、力なく返事をした。
「じゃあ、自己紹介するべきよね?…こんな状況で何なんだけど…。私は寺内祥子といいます。」
ベッド横の灰皿でタバコの火を消して、男にキラキラした笑顔を向けた。
30代後半だというのに、手入れの行き届いたその素顔は20代前半と言っても過言ではないほど若くて艶々している。
「自分は、佐藤不比等っていいます。」
不比等は祥子の眩しい笑顔にたどたどしく言葉を詰まらせながら、名前を名乗った。
「ふ・・・ひとさん?変わったお名前ね。それより、風邪引くから何か羽織った方がいいんじゃないかしら?それに・・・そのままだと・・・ほら・・・その・・・それが・・・。」
祥子は、視線を逸らしながら、正座している不比等を指差した。
「えっ?あ、あああ!!!お、お恥ずかしい!!!すんません!い、今から服着ますから!」
寝起きの早朝。
そして隣に下着姿の妖艶な魅力の女。
健康な男子たる不比等は、自分の失態に顔を赤くした。
「貴方の服は、そこに落ちてるわよ。あ、トイレはキッチンの横だから・・・。」
どたどたと、まるで喜劇役者の演技のような慌てぶりで自分の衣服をかき集めると、不比等はがに股でどすどすと歩きながらキッチンの方に消えていった。
「んで、どうしたんですか、寺内さん?」
女優、寺内祥子のマネージャーは、待ちきれないといった表情で彼女の話を聞いていた。
その日、バーで獣のような男と姿を消した祥子をマネージャーの山本は心配していた。
それでなくともゴシップが多いと有名な祥子に、事務所としてもこれ以上悪いイメージをつけたくなかった。
が、男という男を通り抜けて行った祥子の次なるターゲットがどんな人間なのか、多少なりとも興味があるらしい。
「そのまま、真っ赤になって謝りながら帰って行ったわよ。」
髪の毛先を弄りながら祥子は答えた。
「あの、祥子さんの事、“あの”寺内祥子と分かっていたんですかね、その男?」
「それがね、全然知らないみたいだったのよ。」
クスッ、と上品に噴出すと、そのまま祥子は笑い続けていた。
彼女がこんなに幸せそうに笑うのは珍しい事だった。
あの後、
「自分、昨夜の事で何かあったら、ちゃんと責任取るんで、あの、番号残しますっ。携帯なんすけど、えっと・・・。」
自身の着替えを済ませ、リビングのソファで寛ぎながらテレビを見始めた祥子に、不比等はオズオズと声をかけた。
「え?あ、わかったわ。ありがとう。」
隣に佇む大きな男を一瞥して、また視線をテレビに戻した。
熱中している振りをする。
本当は、全神経が、広々としたマンションがちんまりと見えるほど、圧倒的な存在感を主張しているこの男に反応していた。
「いや・・・だから、あの、祥子さん・・・に何かあったら何なんで、その、もし良ければ自分に番号くれたら・・・助かりますんで・・・あっ、それかやっぱし自分の番号ここに置いていきます、うん、そうっすよ、それがいい。んで、あの…何かあったらすっ飛んできますから…。あ、でもやっぱ祥子さんのも一応もらっといた方がいいっすね・・・。」
クソっと、言葉を上手く表現できない自分に苛立ちながらも、不比等はすっぽりと手の中に納まってしまいそうな小さな携帯をポケットから取り出した。
楽屋の鏡越しに、自分の顔が緩んでいるのに気付いて祥子はフッと表情を引き締めた。
「変わった男だったわ。あれは新種のナンパかしらね?若い子の間ではああいうのが流行っているのかしら?」
祥子は小首を傾げながら呟いた。
眉根を寄せた祥子を見つめながら、マネージャーの山本は目をパチクリさせている。
「ねえ、寺内さん。僕、昨日の彼・・・あの、不比等さんとかいう人?あの人どっかで見たことあると思ってたんですけど・・・。もしかして、彼、体中に傷痕とかありました?」
「え?」
突然の質問に小首を傾げながらも、祥子は思い出そうと顔を顰めた。
「ああ・・・そういえば、なんかいっぱいあったわね…。」
痛々しい傷痕よりも、その並みじゃない隆起した男らしい筋肉の方が印象的だった。
だが、うろ覚えだったが、確かに彼の腕や足や背中に幾つか瘡蓋や痣があったような気もした。
「あの、もしかして、今話題の不比等じゃない?」
「話題?」
「ほら、あの、日本最強って言われてるK-1ファイターの。」
「K-1ファイター?」
男のロマンと豪語して熱く語る格闘技オタクの山本と違って、祥子はあまりそっち方面の知識が無かった。
もちろん、K-1位は聞いた事がある。
でも、観た事も、観たいとも思った事も無かった。
「キックボクシングと空手のテク使って、ロウキックでチクチクと相手を蹴って弱らせるのが得意なんですよ。長期戦の不比等って呼ばれてるんだから。すっごいですね!!祥子さん、あの不比等と寝ちゃったんですか???」
「え、えぇ。」
あの、情けない格好で土下座をしながらひたすら謝っていた言葉足らずの青年と、リングの上で戦うファイターというイメージが頭の中で一致せず、祥子は飲んでいたミネラルウォーターを置き腕を組んで暫く考えた。
二日後。
結局お互いの番号を交換した、例の彼から電話が来た。
「あのっ、た、単刀直入に言います。あのっ、この間のお詫びに・・・祥子さんのお休みの日…で、で、ディナーなんてどうっすか?」
いきなり大声で。
しかもかなり緊張していたらしき彼は、どもりながら本当に単刀直入に祥子を誘った。
「ごめんなさい、休日は外食を控えているの。」
彼女の言葉を聞いて落胆したのか、電話越しでも彼の気の抜けた溜息が聞こえた。
「それなら、あの、えっと、何でもいいんで、また会っていただけないっすか?」
熱心に誘ってくる彼に、今度は祥子が驚く。
「え?えっと…。」
どうしたというのだろう?
バツ2で男という男と付き合ってきたというのに、こんな若い男の子の誘いに戸惑っているなんて。
「し、し、祥子さんの家にまた行っていいっすか?」
どもって声を裏返しながらも、不比等はそう一言吐き出した。
緊張していたのか、言い終わった後ハアハアと息を切らせている。
その姿が容易に想像できて、祥子は思わず噴出してしまった。
「いいわよ。週末はロケがないから…そうねえ…日曜日の午後はどう?あの、あなた…有名人のようだから…その、パパラッツィには気をつけて。」
「え?!祥子さん、自分の事知ってたんすか?嬉しいなあ~~。そりゃあもちろんっす。楽しみっすっ。」
「それじゃあ、また何かあったら連絡を頂戴。」
祥子はそのまま、浮かれて喜んでいる不比等との電話を切った。
約束の日曜日。
不比等は道場かジム帰りなのかTシャツに短パン、シューズというラフな格好で訪れた。
手に箱を抱えている。
「いらっしゃい、どうぞ入って。」
どうやらコチコチに緊張しているらしき不比等をリビングに導いた。
「これ、あの、自分、今朝ジム行く前に焼いたんすけど…。」
大事そうに抱えていた箱を祥子に手渡す。
「これ…貴方が作ったの?」
箱の中にはとても野獣のような容姿の男が作ったとは思えない、可愛らしく装飾された手作りのマドレーヌが入っていた。
「もももももし、ダイエット中とかだったらすんませんっ。でも、自分、お菓子作るの趣味っていうか、好きなんすよ。それに祥子さん細いし、ちょっと位カロリーあってもいいかなって思ってバターたっぷり使って作ったんすけど。」
不比等はまたしても顔を真っ赤にしている。
暫く箱の中のマドレーヌを見て放心していた祥子は、ハッと顔を上げて微笑んだ。
不比等の顔が更に赤くなる。
「ううん、カロリーは気にしていないわ。こう見えても甘味に目がないの。ありがとう、とっても嬉しい。良かったら一緒に食べましょう。そうね、お茶にしましょうか。紅茶で宜しい?」
「いや、水でいいっす。」
そのまま祥子は箱を手に抱えてキッチンへと向かった。
「あの、不比等さん。聞きたいのだけれど、貴方は一体何が望みなの?私と関わってもいい事ないわよ。だって私…。」
リビングルームでお茶をしながら、祥子は不比等に話しかけた。
「私、業界の人間なのよ。」
自分で作った手の平サイズのマドレーヌを3秒で平らげた不比等は、コップ一杯の水を飲み干すと祥子に向き直った。
ソファーから下りて膝をつく。
そして、深々と頭を下げた。
「すんませんっ。自分、嘘ついてました。実は祥子さんと始めて会った夜から祥子さんの事知ってましたっ。ずっと、憧れてて、ファンだったんっすよ。祥子さんがアイドルだった頃は自分、ファンクラブの会員番号3052番でしたっ。し、小学生の頃は、会費とブロマイドでお小遣い使い果たしてたっすっ。」
「あら…。」
いつもクールでポーカーフェイスの祥子の顔が赤くなった。
彼女が10代の頃アイドルとしてデビューしたという事実は、今の若い人は誰も知らない。
自分ですら長い芸能生活に埋もれて忘れかけていたのだ。
「だから、祥子さんとこうやってお近づきになれて、んで、あの、ああいう風にだけど想いを遂げることが出来て、すっげー嬉しくて…。」
感極まっているのか、照れているのか、耳を真っ赤にしたまま俯いている。
「でも、あの日朝になって後悔しちゃったんすよ。自分、もしかしたら祥子さんの事騙して傷つけてるんじゃないかって…。そう思ったら、居た堪れなくなっちゃって……。もし良かったら、あの、自分…俺、償う為に何でもするつもりっす。だから、また祥子さんに会いに来てもいいっすか?」
不比等は茹蛸のような面を下げたまま、上目遣いに祥子を伺う。
祥子は暫く黙って彼を見下ろしていたが、やがてゆっくりと口を開いた。
「そうだったの……。それなら、私の噂や醜聞は色々と知っている筈よね?魔性の女と言われているのよ。それに貴方まだ20代でしょう?私と関わって今が旬の貴方の格闘家としての名前を汚して欲しくないわ。」
年上の女らしく、諭すような口調である。
静かに聞いていた不比等は大きく息を吸うと、頭を上げた。
先ほどとは異なり自信に満ちた眼差しで彼女を射る。
その目は、どことなく、あの男を連想させた。
長い事彼女の心に居座り、その上彼女を振った、あの憎たらしい男。
「自分、27っすけど。でも、そんなの関係ないんすよ。祥子さんのそんな過去は黒く塗りつぶせる位の自信あるんで。振り向かせる自信ありますから。」
不比等の声は、“最強の男”に相応しく若い自信に溢れた力強いものだった。
「それで、どうしたんですか?」
山本は運転しながらバックシートの祥子に話しかけた。
「どうもしないわ、その後二人でお茶しながら、お互いの仕事や世間話して、マドレーヌ全部食べつくして、その日はそれでお終い。」
ふふっ、と幸せそうに笑う。
「信じられないなぁ~~。あの、“最強の男”が祥子さんにお菓子つくるなんて。」
「私も、男の人から手作りのお菓子をプレゼントされたのは初めてよ。毎週毎週私の休みの日には何かしら持ってくるのよ。レアチーズケーキだとか、大福だとか、シフォンケーキだとか。それで一緒にお茶して、お話だけして、何もしないで帰って行っちゃうの。」
苦笑しながら、祥子はふと外を見た。
高速のビルボードに、よく知った男がでかでかとファイティングポーズをとっている。
『日本最強の男、佐藤不比等 VS 黒い闘牛 ゴリ・サップ 8月12日東京ドームにて対決!!』
通り過ぎるビルボードを眺めながら。
今週末彼は何のお菓子を作って来てくれるのだろうか、などと考えている祥子は
「彼の甘い罠にはまったみたいね。」
と優しい表情で独り呟いた。
<ひとこと>
仁神堂に振られた薄幸そうな女の幸せな話を書きたくて書いてしまいました。なにせハッピーエンド推奨派なもんで。男運のなさそうな彼女に春が来ますように!
風も無いのに仄かな匂いがした。
置いてある香炉は今日一度も使用された形跡がないのに、微かな伽羅の芳香が揚屋の室内に漂っている。
上客の男達の話の相手をしながら白い手で静かに酌を汲む女の頭には、小鈴のついた鼈甲の歩揺が挿してあった。
彼女が動くたびに豊かな黒髪からは伽羅枕で染み込んだ薄い香りが男達の鼻を擽る。
禿や他の遊女達と他愛ない世間話をしながらも、客の双眸は全て一点に注がれていた。
木蘭。
江戸の三天女の一人。
胡蝶太夫にも負けない作法と教養、そして絶世の美貌を兼ね備えている。
着物から覗く白い肌と、優雅な身のこなし。
目を合わせればその妖しく艶を帯びる黒い瞳から憑かれたように目が離せなくなる。
花びらの様な赤く潤んだ唇から零れ出る声は、か細いながらも良く通って男達の耳に心地よく残った。
彼女の客は皆、その細い指で奏でる琵琶で心が洗われ、散りゆる春の桜の如き儚い舞で一時の夢を見ることが出来た。
儚き夢と幸福をを与える、美しい梅山の遊女。
松田屋の格子、木蘭にはそんな噂がたっていた。
なーんていうのは全く持って仮の姿。
もちろんそれは最高遊女としてのあたしの「演技」なのだ。
噂って言うのは怖い。
だって実物のあたしは、巷が噂しているようなおしとやかな美人でもなんでもないんだもん。
顔なんて化粧をちょっとすれば何とかなるし、作法なんてちょっと優雅な振りしてれば良いだけだし。
本物のあたし、木蘭は巷の男達が夢見ている姿とは全然違うと思う。
だって、趣味は脱走(もちろん見つかったらこってり絞られるけどさ)して江戸の町を散策する事だし(苦笑)。
あと禿達や、あたしの本性知ってるお客様との気楽なお喋りとか、囲碁やら百人一首とかのゲーム遊びも好きだしね。
あ、誤解しないで!
もちろん、身売りされた日からたまりにたまった借金返済の為に明るく毎日頑張ってるわよ!!
禿時代は嫌々ながらも毎日色々習い事をさせられたしさっ。
まあ、頑張ったお陰で二十になった今は客を選ぶ事が出来る格子まで登りつめられたし。はっはっは。
これも才能かしらん??
なんて独り言言っていたら隣であたしの髪を直していたあたし専属の禿のおりんが冷たい目でひとこと…。
「それは木蘭姉さまじゃなくてお客様のお陰でしょっ」
って。
うっ……図星。
修正修正。
これもひとえにあたしのお客様のお陰なのよね。
だからはっきり言ってこの仕事は嫌いじゃない。
もちろん、最初は男の人のお酌やお喋り、それに同衾なんて行為が嫌で嫌でたまらなかった。
でもある日、今はもういないけれど尊敬していた楓姉さまが、お客様は心のケアを欲しているのよ、ってアドバイスしてくれたんだよね。
あたしに会いたくて、普通の人だったら家が破綻しちゃうくらいの大金をはたいて来るのよ?
あたしなんかと擬似恋愛(っていうのだろーか?)をしたくてわざわざ遠くからやってくるのよ?
どう考えたって邪険には出来ないでしょ?
それに、皆が皆エッチ目的のお客じゃないって事も分かったし。
だから、ね。
彼ら、パトロンとも言えるあたしの大切~なお客様の事をこれから日記につけようと思っているの。
もちろん内緒で、ね(ウインク☆)。
だって、彼らのお陰で今のあたしがあるから。
一人一人が、あたしにとって大切な人達なんだもん。
あ、新造が呼びに来た。
今日は誰が揚屋に来たんだろ???
ちょっと今から行ってきまーす!!!!
それでは!!
あたしはルンルン気分でお茶を点てていた。
あたしの目の前には色男が一人。
顧客の一人で、公方様こと徳川家直属の重臣松本家嫡男の重里さんこと重さんだった。
実は禿時代からの古い常連さんの一人だったりする。
性格は実直で真面目な典型的な武士。
美形で剣の腕も立つし、もう既に二十を超えているのにずっと縁談を断っているんだって。
「まだ私は半人前ですから、生涯の伴侶を得る準備が出来ておりません。」
と断り続けているらしい。
お金さえあれば誰だって多妻が許されるのに、変わった色男と評判だった。
その上、この梅山には何食わぬ顔で頻繁にやってくる。
もちろん、あたしに会いに。
周りは当然のことながら噂をたてているようだけど…。
あたしがまだ十三歳の禿だった時。
当時天神だった(今は格の名前が変わって格子になったんだけど)楓姉さんについて揚屋にあがった、秋のある日の事だった。
父親について登楼した十四、五歳の少年の隣について酌をしていたのが始まりだった。
少年はキリッとした感じの美少年で、元服したてといった感じの初々しさを漂わせていた。
そのうえこういった所ははじめてらしく、顔を真っ赤にして俯いたまま最初は誰とも目をあわせようとしなかった。
あたしが彼に話しかけるまでは。
楓姉さんはさっさと他の客に呼ばれて行ってしまい、ここの常連らしい彼の父親は端の桜花姉さんと消えてしまって、この部屋には彼と従者数名と、あたしのような禿数名が彼らの酒の相手をする為に取り残された。
久々に同じ年頃の子供が来ている事が嬉しくてあたしはその子に話しかけた。
「ねえ、あんた名前は?」
あたしが突然話しかけたのに吃驚したのか、少年は体をビクリと硬直させてこちらを見た。
「……重里。」
小声で答える。
「そっか。重里さん。うーん、重里さんって言い方硬いから、重さんでいいやっ。重さん、ここは初めてなんでしょ?」
重さんは、顔を真っ赤にさせて、横を向いた。唇を尖らす。
「こんな所、来たくは無かった。でも、父上が…。」
こんな所って…。
そこで働いているあたしの立場は??
ま、いっか。
彼は元服祝いか何でここへ無理やり連れて来られたのかな?
なんてあたしは小さい頭で考えながら、少年を見た。
武士らしく、凛と胸を張って堅苦しく正座している。
「つまんない?」
あたしは、重さんの顔を覗きこんだ。
彼はあたしの突然のドアップに、ちょっと腰を引いた。
「なっ、やめっ/////////」
途端に赤かった顔が湯気出るんじゃないかって位もっと赤くなって、あたしを押しのけた。
武芸をたしなんでいるからか、その力は以外に強くて。
「きゃっ。」
と体勢を崩して、あたしは畳の上にずしゃぁぁ~~~っと無様に倒れてしまった。
「ハッ。も、申し訳ないっ。大丈夫でしょうかっ、あの…。」
重さんは、今度は真っ青になってあたしを抱き起こしてくれた。
あたしはふるふると肩を揺らしていた。
「もう乱暴はしないので、お、怯えないでいただきたいっ。あの、わたしは貴方に危害を与えるつもりだったのでは無く、ただ…。」
あたしは俯きながら更に体を震わせた。
だって、面白かったんだもん。
赤かった綺麗な顔が一気に青くなって。
「あははははっ。重さんあなたおもしろーい。顔の色がコロコロ変わって。あのね、あたしね、木蘭っ。」
あたしはまだ小さくて細い重さんの腕に抱え起こされながら、言った。
「?木蘭?」
「あたしの名前。」
「…いい…名前ですね…。」
彼の隣に座りなおしながら、あたしは笑顔で一礼した。
「そうっ、松田屋の木蘭。覚えといてねっ。今度お父さんと来た時は、一緒に遊ぼうっ。」
あたしは、そう言って重さんの手をとってフリフリ(←握手)した。
「う、うん。木…蘭殿。」
その日あたし達は、彼の父親が戻るまでずーっとしりとりや巷で流行り
の歌遊びをして時間を潰した。
彼はそれから父親と来る度に、あたしを指名するようになったのだ。
シャカシャカシャカシャカ……
お茶をかき混ぜながら、あたしはちらり、と重さんを盗み見た。
今思えば、あの時は彼がこーんな逞しいいい男になるなんて思ってもみなかった。
顔を上げると、重さんの優しい双眸とばっちり目が合ってしまう。
やけに大人しい(っつってもいつも静かだけど)と思っていたら、人間(←あたし)観察をしていたんですか…。
重さんは目が合った途端サッと長い睫毛を伏せて顔をちょこっとだけ赤らめた。
うおっ、照れてる???
とか思いながらあたしもさっとお茶を差し出した。
「はい、重さんどうぞ。略式でゴメンなさいね。」
重さんはハッとしたように目を上げて、
「ああ、有難うございます。」
とお茶を手に取った。
あたしは、美形はお茶を飲んでるだけでサマになるんだなぁ…とか思いながらボケーっと見惚れていた。
重さんと最後に会ってからもうかれこれ一ヶ月。
最近幕府でのお仕事が忙しいらしく、なかなか時間が取れなかったようなのだ。
だけど、彼からマメに「あなたをちゃんと想っております」みたいな内容の文は届いていた。
でも、筆不精のあたしはあんまり返事を書いていなかったけど…。
いや、正直一回も書いてない(苦笑…たら~っ)。
ってそんな事言ったら店の主人に
「客を舐めとるのかぁぁぁ!!」
って怒られそう。
ま、いいや。
だから、今日久々に重さんが遊びに来てくれたのはすっごく嬉しかったりする反面、ちょっと会うのが心苦しかった(手紙書かなかったし)。
「美味しかったですよ。」
いっきに飲み干すと、重さんは湯飲みを置いて笑顔であたしを見た。
「今日は何をして遊びます?重さんは囲碁が強いから、囲碁でもいいし、そうだな~、和歌でも詠んでみます??あっ、最近巷で流行ってる狂歌でも作りましょうか??」
あたしが独りでうーん、と頭を捻っていると、
「わたしは木蘭殿のお話が聞きたいのですが。」
と色気のある低い声で呟いて、あたしの手を取り自分の両手に包んでしまった。
うわぁぁぁぁぁ~~~っ!!
チョットまって、あたしまだ心の準備が/////////
重なり合った手は、あたしのか重さんのかかわからないほど熱くドクドクと脈打っている。
「わたしはずっとあなたの事を考えていましたよ。」
なんてちょっと恥ずかしい台詞を、恥ずかしげもなくさらりと言ってのけた。
梅山では悪名高い(って何の!)木蘭さん、遊女なのに実はこういうのにめっちゃ弱いんですぅ~~~。
未だ持って慣れない。
あたしはシドロモドロで話題を転換しようと試みた。
「えっ、あ…あの、あたしは…さっきまで初めて重さんと会った日のことを考えてましたっ。」
重さんは握っている手に力を込める。
「わたしは今日まであなたと始めて会った日の事を一度として忘れた事がありませんが?」
熱い息があたしの首筋にかかった。
やばっ。
この方発情ムードだわっ。
「わたしがいない間、何人の男を相手になさったのですか?」
といきなり抱き寄せられる。
力強く、ギウ~~っと。
「それを思うと眠れない夜がありました。どうして、貴方は強情に…素直に私に身請けさせてくれないのですか?私だけのものになれば苦労はさせないのにっ。」
……。
同じ台詞を言われた事がある。
あたしたちが始めて男女の行為をした時。
多分、重さんが五回目にあたしを指名した時だったと思う。
あたしも重さんも極度に緊張していて。
でも、行為が終わった後ずーっと褥であたしを抱いて、
「あ、あの…私のものになって下さい。苦労はさせるつもりはありませんっ。その為に、わたしも頑張って働きますからっ。」
って言ってくれた。
その頃は、まさか彼が現在に至るまで長い間あたしのパトロンとなってくれるなんて思ってもみなかったけど。
「駄目駄目っ。」
あたしは心地よかった重さんの胸を押しのけた。
「…?何が駄目なのです?」
「あたしの借金はあたしの問題だから…。もし二十七になっても身請け人がいなかったら、憐れなあたしの為に重さん考えて頂戴。それまでは、出来る限り自分で返済するんだからっ。重さんもその時に備えてお金を貯めておいてっ。わかった??」
重さんは睫毛をまた伏せて、フッと寂しげに微笑んだ。
「…貴方らしいですね。でも、もう少し私に頼ってくれてもいいのですよ?…男として、武士として。」
そして、顎にそっと長い指が置かれた。
ひぇぇぇ~~~っ、重さんの綺麗な顔がドアップっす。
せせせせせ接吻の準備、開始!!!
あたしは、固く目を瞑った。
一秒経過…。
ん?何も来ないぞ?
片目をそぉーっと開けてみると、重さんは横を向いてくっくっくと忍び笑いを漏らしていた。
「し、重さーーーんっ、酷い!!!」
「いや、木蘭殿が…あまりにも愛らしかったので…。」
えええ?フェイントですか???
あたしがムッとなって横を向こうとすると、顎にかかったままの長い指で再びクイっと持ち上げられて、今度は重さんの形の良い唇が重なった。
「…あなたが欲しい。今日は私だけの恋人になってくれますね?」
「ん…。」
とろけそうな接吻を繰り返しながら、重さんの手があたしの着物の襟にかかった。
→ここからの二人を読んでみます??
(上下のHOME横の>>をクリックしても読めます)
めくるめく快感に襲われた行為の後…。
あたしは重さんの逞しい腕の中にいた。
重さんたら、行為の後もあたしを方時も離すまいと、ぎゅうぎゅうに抱いていて。
でもその間、あたしはなんでこんな美形の色男がお嫁さんをとらないのかずぅ~っと考えていた。
あたしみたいな遊女と一緒になったって、卑しい女を娶ってと他の人たちから一生白い目で見られるだけなのに…。
「何を考えていらっしゃるんですか…?」
耳元に熱い吐息がかかって、あたしは一瞬びくっとした。
「いや、あの、みみ、三宅屋の桜餅の事とか…。あっ、今は食べられないけど、春の名物じゃないっ、ね?!!」
ああ、あたしったら嘘つき!!!
「桜餅?!」
重さんは眉根を寄せて複雑な顔をした。
「それは…貴方らしいというか何と言うか……。」
その後で、はあ~っと深い溜息をつく。
「分かりました。今度手土産に持ってきます。」
「え?あ、そんな意味で言ったんじゃなくって…。」
あたしは手を振って否定する。
重さんは切なそうに顔を歪めてあたしを掻き抱いた。
「今度、という言葉がとても憎いです。貴方の体に私の印をつけて誰の目にも晒さないでいたいっ。他の男など相手にしていて欲しくないと思うのは私の身勝手でしょうか?毎日貴方を見ていたいのにそれが許されないこの身…いっそ貴方を奪って逃げたい程です。」
「あ…。」
その気持ちありがたいけど、勝手に遊郭を逃げ出して一生お尋ね者となって生きるのはちょっとね…。
な~んて、やけに現実的なあたし。
でも。
「なら、借金を返して年季が明けたら迎えに来るって約束して。」
あたしの言葉を聞いてか聞かずか、聞き取れないほどの小声で重さんは呟いた。
「もちろんです。(愛しております・・・ボソッ)木蘭殿。」
「は??」
「いえ、なんでもございません。次会う時まで…この重里の事を想っていてくださいますね。あの…他の男の相手をしていても…。」
「もちろん。」
あたしは重さんの切なそうな瞳が耐えられなくって、そう答えてしまった…。
その晩、夜が明けるまであたしは何ども重さんの激しい情熱に応えた(応えさせられた、の正解)。
翌朝、来た時と同じように、女達の黄色い声とボンビーな徒歩の男達の妬んだ視線を浴びながら、籠に乗って梅山を後にした重さんでした。
「初めて貴方にお会いした日…まだ子供だった私ははじめて恋というものが何であるか知りました…。」
本当に、昔はあたしと変わらない背丈だったのに、なんでこんなでっかくて、かっこいい色男になったんだろ?
とか考えていると、優しく、あくまーで優しく重さんの手があたしの襟元にかかって、そのまま首筋に熱い唇を落とした。
「ん…。」
ちゅうぅぅ~っと痕ががつきそうなくらい熱く吸ってくる。
ちょっ、痕が残ったら商売にならないっ!!!
と思っていると、重さんは愛しげにあたしをみつめて(ぎゃあぁ~~//////)
「悪い虫除けです…。」
と言いながらあたしを抱えて柔らかい布団の上に寝かせた。
自分もその隣に横たわって、片手で頭を支えながらもう片方の手であたしの体を、着物の上から優しく触りだした。
時は五ツ時。
辺りはもう既に暗くて、燭台と共に、外の白い月明かりがあたしたちの部屋の中を照らしている。
「初めて貴方にお会いした日…わたしはまだただの餓鬼でしたが…子供ながらにこの木蘭という花に触れてみたい、傍にいたい、そして…この手で手折って我が物にしてみたい、という欲求に駆られました…。」
そーっとあたしの頬を撫でながら、あたしが言葉を発する前に形の良い唇であたしの唇を塞いだ。
舌であたしの口腔内を隈なく味わうと、今度はその生暖かい舌で首筋を舐め上げる。
「あんっ…。」
っつーかいつからこんな上手になったの??
初めての時なんか…全然いろはが分かってなくって、もう無我夢中で自分の欲求を満たしてたって感じだったのに…。
「ひゃあっ!」
あたしの上に圧し掛かってきた重さんは、筋肉質の腕で体を支えてあたしに体重をかけないように気を使いながら、もう片方の手で幾重にも重ねられた着物の袂に侵入させる。
…あたしの顔中に接吻の雨を降らせながら…。
この人はいつだってそう。一旦欲望の火がつくと、もう止まらない。
「……っ!」
あっという間に、彼の手はあたしの胸の頂を捉えた。
ビクンっと体を震わせたあたしに気づいて、着物の裾の間に袴を履いた足を一本差し入れる。
「もう、私は…貴方が欲しくて堪らない…っ!!」
胸を揉みしだき、覗いた肩口にあつーいあつい接吻を繰り返しながら、下半身をぴったりと密着させてきた。
あのぉ~…。
存在を主張し始めてるあそこが、あたしの太腿の上辺りに当たっているんですけど…。
鎖骨に沿って唇を落としながら、左手で袂を広げてあたしの白い胸を露にした。
熱い舌は手で覆われた胸の先を捉えて…。
「ああんっ…。」
軽く吸われて思わず声が出る。
「もっと…貴方の声を聞かせてください…。」
頂を捉えながら、上気した顔を僅かに上げて切なく声をかける。
「私に…聞かせて欲しい…。貴方が…私を…欲する声を…。」
接吻の合間に声を漏らしながら、悪戯な手はどんどん下へと降りていく。
「ちょっ…重さ…まって…ひゃあっ!」
熱い中心を避けて、あたしの内腿に到達した重さんの手は、円を描きながら焦らす様に刺激を与えた。
「何を…待つ必要があるのですか…?もう、こんなになっているのに…?」
ぴちゃっと。
あたしの花弁に宛がわれた指は、あふれ出している蜜をさっと掬った。
「あ……ふっ…重さん!!」
「ああ、もう…貴方が私の名前を呼ぶと…耐えられません…。」
目を瞑って甘美な表情をしながらも、あたしの花弁の重さんの指が卑猥な音を立てながら侵入してきた。
そして、指をもう一本。
「いやっ…ふ…くっ…ああ…!」
二本の指で弄りながら、あたしの花弁の奥を探検する。
親指で、花弁の上の芽を擦り始めた時にはもう我慢の限界だった。
「重さん…お願い…ああんっ…。」
重さんも限界に達していたらしくって、あたしがお願いすると
「私の…木蘭…。」
と独り言のように呟きながら、いつの間にか袴と褌を下ろして熱く火照った彼の中心をあたしの花弁に宛がった。
「ああああ!!」
感じやすいあたしは、重さんが一突き入れただけで四肢がグニャリとなってしまって。
それなのに、重さんは何度も何度もあたしの奥へ腰を突き上げる。
「…っ……木…蘭…!!!」
「重っ…さんっ……はあっ…あ…!!!!」
熱い塊があたしの奥にぶつかる度にあたしも口から零れ出る喘ぎがとめられなかった。
「もっと…私を…感じて欲しいっ。」
そう言うと、重さんは腰を打ち付ける速度を速めた。
「あん…あぅ…あっ…あああ…!!」
それは、いつもながら唐突に訪れた。
あたしが快感でブルッと体を震わせた時。
首筋に接吻を繰り返していた重さんが、
「木蘭…殿っ……もう…私もっ!!!」
と苦しげな声を漏らした。
重さんは熱く繋がれた場所から自身を素早く抜き取って、花紙を先端に宛がった。
目を瞑ったまま恍惚感を味わっている重さんを見詰める。
なんか、すっごく…色っぽい…。
つーっと。
溜まっていた重さんの白い欲望は、花紙だけでは押さえられずに彼の怒張していた男を伝い落ちた。
「木…蘭……殿っ…。」
半放心状態のまま肩で息をしている重さんが可愛らしくって、あたしは彼を抱き寄せた。
「木蘭殿っ…今私を抱き寄せたらお着物が汚れてしまいますっ。」
と焦っている重さんを無視してチュっと彼のおでこに口付けた。
→さっそく読んでみます??
「お前の綺麗な顔を俺の色で染めたかった。」
悪びれもなくハハハと笑うこの男。
顔を洗ったあたしは、目の前の男を睨みつけた。
米屋十兵衛なんていかにも商人らしい名前の彼はそんな名前の持ち主とは思えないほど、不思議な美貌の若旦那だ。
彼の実家は大阪から来た江戸でも有名な酒造の老舗で、遊郭に来るたび散財を惜しまないいわゆる豪商の嫡男だった。
主である父親が、北方の蝦夷地に住んでいた異国の女を買い取って妾にして出来た子だと自分で言っていた。
だから彼は透き通った肌と、巷では珍しい亜麻色の瞳と髪の毛を持っていて。
彼の実の母親は彼を生んですぐに亡くなってしまったらしいけど、幸いなことに本妻さんに子供が出来なくて、実の子の様に可愛がられたそうな。
そして、散々甘やかされてこんな助平男に育ってしまったらしい。
「それは、俺に対してしつれーじゃねぇか?」
さっきからずう~っとあたしの隣で、あたしのうなじのほつれ髪を弄っているこの男。
色っぽいと勘違いしているのか、袂を広げてド派手な金色の虎模様の入った着物を着崩している。
その体には嫌というほど香油をつけているらしくって、こいつが動く度にぷんぷんぷんぷん匂いが漂って来る。
「ああ~~もう、忌々しい!!!行為が終わったらさっさと帰ってよ!!!」
あたしが振り払おうとした手を、こいつはいとも簡単に掴んでしまった。
「い・や・だ・ね!!それが客に対して言う言葉かよ??あともう三発くらいしねぇと払う金の元がとれねーよ。最近お前はつめたいからよー。俺が浮気して梅山の他の女に手ぇ出すと怒る癖に、勝手なもんだよな~っ。」
この男は。
黙っていればとてつもない美貌の持ち主なのに、その顔に合わない饒舌な口調と馴れ馴れしい喋り方でいつもあたしを苛々させていた。
「あんたね、浮気も何も、この間梅の屋のお鶴ちゃんと会ってたって新造が言って来たわよ。あ、誤解しないでね。あたしはあんたみたいな女好きの客は大っ嫌いだし、他の女の所に行ってくれたらあたしだって万々歳なんだから!!」
あたしの言葉に十兵衛さんはニタニタしながら答える。
「へ~え、そうなのか。俺が浮気しても松田屋の木蘭さんは構わねーんだ?」
彼は掴んだあたしの腕を引き寄せて、半むき出し状態の胸の中に閉じ込めた。
「お前は浮気し放題なのに、いいご身分だな??」
「は?」
手で彼を押し退けようとしても、あたしを包んだ腕は力強くて放してくれない。
「お前に比べたら俺のなんて浮気にも入んねーよ。俺が身受けして自由にしてやるっつってんのに、意地張って聞かねーだろ?そこまでして他の男とやり続けてーのかよ??」
「なっ!!!」
何その言い方!!!激ムカだわ!!!
と言おうとして彼の胸から顔を上げると。
いつものふざけた彼とは大違いの、真面目くさった表情をした十兵衛さんの真摯な視線とぶつかった。
なに、その顔…?
ちょ、調子狂うじゃんか!!!!
「し、仕事だもん。しょうがないじゃないっ。それにね、あたしは誰にも頼りたくないの。自力でお金を返し終えるか、二十七で引退するかまでは一人で頑張るんだから!!!」
フンッとあたしは横を向く。
「一人で、ね。まあお前らしいっつたらお前らしいけどよ、そんな事言って年明け過ぎて貰い手が無くっても泣きつくなよ。俺は知らねーぜ?三十過ぎて現役なんて恥ずかしーよなぁ。」
亜麻色の髪の毛を掻き上げながらフフンッとせせら笑う。
ガーッ!!!ムカつく!!!
「人の心配より自分の心配しなさいよっ。女遊びも過ぎるといつか痛い目にあうんだからねっ。」
横を向いたまま言い放ったあたしの顎に、グッと手が置かれた。
そのまま、唇が重なった。
荒々しく角度を変えて、彼の舌が深々と侵入して来る。
そのままあたし達は二回戦に突入した。
「美味しかったぜ。」
長い夜を経て、や~っとあたしの体が開放された。
あたしは疲労でもう腰が立たなかった。
なのに彼はフラリと身軽に立ち上がって、身支度を始める。
っつーか…。
なななな、何なのこの男は!!!
「そんな寂しそうな顔すんな。また明日遊びに来てやるから。それまで体休ませとけっ。なっ?」
ド派手な着物に、これまたド派手な羽織を羽織ると十兵衛さんはチラリと後ろを振り向いて、まだ布団の上のあたしに声をかけた。
はっ!?
明日って…。
冗談じゃない、こんな事毎日してたら体が持たないわ!!!!!
「それじゃ、また明日♪」
と元気にあたしに一声かけ、悠然と立ち去る奴に向かって。
「に、に、二度と来るな、好色絶倫バカ男ぉぉぉ~~~~~!!!!!!!!」
との、あたしの叫びが揚屋中に響きましたとさ。
ちゃんちゃん♪
「はっあっあっあっ……。」
あたしは朦朧とした恍惚感に浸っていた。
この男はの技術(テク)は、半端じゃなくて。
遊び人として有名なだけあって、どの客も凌ぎダントツで女の体を知り尽くしていた。
だから、どこがあたしの弱点かもとっくのとうに知っていて、わざとそこを攻めてくる。
寝床に俯いて膝を立てた鵯越えの格好(バックの事)のあたしは、恥ずかしげも無く花弁を彼の目に曝け出していた。
あたしの入り口から指三本先の快感のツボを狙って、わざと熱い自身を擦ってくる。
後ろから繋いであたしを攻めながらあたしの胸を掴んだほっそりとした手は、もちろん桃色に尖った先端に刺激を与えるのも忘れない。
「はぁっ……どう…だ?降参…しろ、よ??」
「バ…カ。そ…簡単に…は……イってやん…な…あんっ!」
彼はさっきから何ども体勢を変えてあたしを攻めていた。
最初は二つ巴(69)。
お互いの秘部を貪るように味わった。
彼の男は、ちょっと普通の人より大きくて太めで。
まあ、そんな事本人に言ったら天狗になるから言わないけど、それを口に頬張って飴玉のように舐めるのは嫌いじゃない。
あたしが絶妙な舌使いで吸ったり舐めたりしてあげると、彼も負けじとあたしの花弁の芽に歯を立てたり隠花を舐めたりして刺激を与えてきた。
小さな蕾の隠花に指を添えられたときは、あたしも負けじと彼の小さく襞の寄って萎んだ禁断の蕾を刺激した。
「あ…あ…ん…あぁ…。」
「くっ……つっ……挿れるぞっ…。」
お互いの唾液で秘部が濡れ、準備が整うと、彼は遠慮なくあたしの中に入ってきた。
深山の体位で、仰向けのあたしの両足首を抱えて深々と自身を差し入れる。
「お前、すげ…濡れてるぜ…中……熱くて千切れそうだっ…。」
「あ…んただって……!!」
ただの出し入れではもちろんなくって、微妙に腰の角度を変えて攻めてくる。
暫くすると、あたしの片足をさげて松葉崩しで攻めてきた。
彼の男が根元まで入っているようで、奥深くにあたる。
もちろん、あたしも彼に攻められてるだけじゃなくって。
イキそうになる手前で体勢を変えた。
あたしは得意の百閉(騎乗位のことね)で、主導権を握ろうと試みた。
腰を動かし、上から下に仰向けに寝そべっている彼を見下ろすと。
あたし達が繋がれている場所に薄い瞳を空ろに漂わせていた。
亜麻色の長い髪がフワリと広がっていて、汗ばんで桜色に染まっている体が色っぽい。
広い胸を上下しながら息をしている彼は、あたしと目が合うと余裕のウインクをかましてきやがった!!
「お前をイかすまで……俺はイクつもりねーからな…。」
言いながら、大きく揺れているあたしの胸に手を置く。
「他の奴ら…なんて…目じゃねーほど…快感…与えてやる……。」
半身を起こして、あたしの胸の先端を赤子のようにチュっと吸ってきた。
「あんっ……!!あたしだって…負けない…もんっ!!」
あたしも手をのばして彼の小さな胸の先を指で擦った。
いつも、こんな感じだった。
どちらかが我慢できず先に果てるまで続ける。
大したことじゃないけれど、負けず嫌いのあたしはこの男に負けたくなくて。
これで何度目かの同衾だけど、この男が先に屈した事は未だ持って無かった。
それもあって、今回の木蘭さんは気合が入っていた。
腰を振り続けていると、あたしの足がだんだん疲労で疲れてきた。
それを察してか、たんなる偶然か。
彼は自身を抜き出しもせず、繋がったままクルリとあたしの体を反転させて仰向けにし、そのまままた後ろ向きにした。
っつーか、すごい技!!すごい速さだわ!!!
何度も体勢を変えて辿り着いたこの鵯越えの格好のまま、彼はあたしの桃尻を掴んで広げながらすごい勢いで突き上げてきた。
「はん…あっ……んっ……。」
二人の愛液で卑猥な音を立てているそこを突く速さが増してくる。
やばっ…も…だめ。
負けたくないけど、あたしも理性の限界が近づいていた。
それでも唇を噛んで我慢していると。
突然彼が熱い塊を抜き出した。
ええ??!!
とか思っていると、もの凄い力で体を仰向けにされて。
「なっ!!!」
と言葉を発する間もなく、あたしの目の前に怒張した彼の男が突き出され…。
「………っあ。」
先端からゆっくりと、白くて暖かいものを吐き出した。
噴出を繰り返すドロドロとしたそれをあたしの頬や口元に浴びせかける。
全部出し終えると、自分の欲望がついているのも気にせずこいつはあたしに熱い接吻をしてきた。
「いっぱい出たなぁ。」
唇が離れると、あたしはのん気に小さくなった自身で遊んでいる男を睨んだ。
「この……バカ野郎。タコ、ボケ、死ね。」
そんなあたしの暴言にはちっとも動じず、顔射しやがったこのおたんこ茄子はスッキリした顔で
「今日はお前の勝ちだ。」
なんて言いながら笑っていた。
その日は、人手不足でずっと他のお客様の相手をしていた。
だから、その人が待っているその部屋に着いたのはもう六ツ時で。
身分が保証されている方だし、明日の七ツ時までお相手するのは目に見えていたので、あたしはその人を待たせていた事をさして悪いとも思っていなかった。
その人は、部屋の奥に独り佇んでいた。
そうっと侵入してきたあたしに気づいているのかいないのか、庭に面した戸を開けて茜色の空を熱心に眺めていた。
赤い夕日はその人の中性的な美貌を美しく照らしていて。
冷たい隙間風が部屋に入り込んで、悪戯にあたしの頬を掠って通り過ぎた。
「っくしょっ!!!」
思わずクシャミがひとつ出る。
「……遅い。案じていたぞ。」
空を見上げたまま感情を押し殺した声で呟くと、その人はゆっくり部屋の襖戸近くのあたしを振り向いた。
赤い光に照らされているせいもあって彼のすらりとした細身な身体は儚げで。
ほうっと、思わず溜息が零れ出た。
こんな綺麗な男の人も世の中にはいるものなんだと、あたしは会う度に驚く。
この方とはもうかれこれ二、三年の付き合いだった。
京都に住んでおいでだから、滅多に会えない。
でも、江戸に来るたびにあたしの所に連泊する。
朝廷の帝と縁故のある由緒正しき九条家の方だから、常連でさえ滅多に許されない連泊もあたしと店が許可すれば可能なのである。
それはいいとして。
確かそれは三年前の秋。
幕府に呼ばれた朝廷や公家の公達が、彼らの接待を受けて江戸の梅山に遊びに来た時に、このお方が混じっていた。
九条夕雲。
兄である九条家の主の代理で、江戸に来ていた。
その時その人は。
エロ根性丸出しでうわついていた他の客連中の中でただ一人、冷たく侮蔑した眼差しで彼らを見つめていたのを覚えてる。
お客の中で一人異彩を放っていた美人さんだったから、他の遊女も放ってはいなくて。
なのに、お酒を注ぎながら彼にしなを作って見せる女達の色香攻撃にも眉一つ動かさずに、ただもくもくとお酒を飲んでいた。
その日の宴が盛り上がりのピークをみせた頃、彼は誰にも断らずに無言でスッとその場から消え去った。
それに気づいたのは、あたしだけで。
他の方のお酌をしていたあたしは、何故だか彼の様子が気になって持ち場を離れ揚屋中を探し回った。
彼は中庭にいた。
丁度今日の九条様のように、一人、腕を組んでぽかんと宙を見上げていた。
あたしは声をかけてみた。
「夜風は体に良くないですよ~~~っ。」
しぃーーーんっ。
無視っすか。
あたしは大声でもう一度言ってみた。
「よ~か~ぜ~は~か~ら~だ~に~―――。」
「そのように大声を出さずとも私には聞こえる。」
袴を履いて刀を差していなければ女と見まごう美しい顔の、長い睫毛に縁取られた色の薄い瞳が空ろに彷徨ってあたしにたどり着いた。
「なんだ、聞こえるんじゃない。なら一緒に中に入りましょっ。」
あたしは彼の着物の裾をひっぱった。
「……。お前は遊女か?」
「は?」
彼はいきなり、不可解な質問をぶつけて来た。
つーか君。
今自分が何処に居るのか分かってるの??
「お前は遊女かと聞いている。」
あくまで無表情のまま、感情の無い声で聞いてくる。
「あの~、あたしさっきまであなた達のお酌をしてたんですけど…。」
「…そうか。気づかなかった。あのようなやかましい所によくいられるな。」
彼はまた宙を見つめながら独り言みたく小さく呟いた。
「んまあ…仕事ですから…ねぇ…。」
「同じだと思ってな。」
ポツンと呟く。
「は?」
「夜空の星は、ここも、京も、私が幼年時代を過ごした吉野も同じだと思って見つめていた。」
あたしもつられて夜空を見上げる。
青い天に白い絵具を振りまいたような星がキラキラと輝いていて。
でもそれ以上に、星の光に照らされた隣の男の人の顔が言葉で表せないほど非人間的というか、美しくて息を呑んでしまった。
どれ位経ったのか。
あたしはじーっと彼の顔を見つめていたことに気づいて赤くなり、彼の手を引いた。
「さっ、そろそろ中へ入りましょう。」
一瞬その人はビクッと震えて、そして思いっきりあたしの手を振り解いた。
「わ、私に触るなっ。」
「は??」
触るなって…。
突然の大声にこっちが驚いた。
でも、彼の顔を見たら微かに両頬が桜色に染まっていて。
照れてる??
「あ、ごめんなさい。」
「……許す。し、知らないお、おなごに触られるのなど初めてだったから…。」
どもりながら説明すると、顔をプイっと横に向けた。
ってオイ、君はどう見てもあたしと同年齢なのに…。
触られた事ないの?
妻帯しててもいい年なのに?
「別に知らないおなごに触られたからって減るもんじゃないし、痛いもんじゃないんだよ。」
と言ってあたしは今度両手で彼の方手を握ってみた。
「…なっ…。」
彼は驚きで、目をパチクリさせていた。
「あたしは、松田屋の木蘭っていうの。ほら、もう知らないおなごじゃなくなった。それよりこういう所は初めてみたいね。」
あたしは握っている手に力を入れた。
「人肌ってぬくいでしょ?」
「……。」
彼はあたしと視線を合わさず、あたしの手を振り払った。
「夜風が冷たくなってきた。わ、私は中に戻るっ。」
そう言うが早く。
彼は背を向けて大股で立ち去ってしまった。
「え…??」
残されたあたしはしばらく呆然と立ち尽くして、慌てて彼を追って部屋に戻った。
それから彼は何度か松田屋に足を運んでくれた。あたしを指名してくれるに至るまでに約二年。
まあ、滅多に京からいらっしゃらないってのもあるんだけれど…。
同衾は…実の所未だ持って実現していない。
でも、進歩したというのか、あたしが彼に触れるのをもう厭わなくなった。
まあ、それ位の信用は得た…らしい。
その事を彼の従者に語ったら、物凄く吃驚された。
口数が少ないけど、ポツリポツリと断片的な彼の話を繋げると、彼は後水尾天皇の血縁で、養子として親戚の九条家に育てられたという事だった。
その上生まれながらにして病弱で、不思議な力を持っているという事も。
そう、あたしには想像不可能な世界=霊の世界の住人と対話出来るのだそうだっ。
だから、彼が宙を向いている時は殆どそいつらと会話をしている…らしい。
「先ほど怪しげな客に触られていたと六助が申しておったから案じておったぞ。」
六助って…それは誰…?
もちろん生きてる人間じゃあないのよね?
「ああ、あの酔っ払いのクソオヤジね。あの客だったらもう酔いつぶれたから大丈夫大丈夫。」
「そうか…。」
ズゥイッと、突然あたしの肩を引き寄せる。
な、な、な、なんすか突然!!!
と驚いていると、細い外見からは想像もつかない力であたしを抑えて仰向けにしてしまった。
ぽすっと音がして、頭に何か添えられたと思ったら。
ドアップで九条様の顔が目の前にあった。
「ぎゃぁぁぁぁぁ!!!!」
思わず叫んでしまったあたしの口を塞いで、ちょっと不快気に顔を顰める。
「今日も一日疲れたであろう。俺の膝の上で寝ていいぞ。嫌か?」
嫌かって…。
ひ、ひ膝枕!!!
「嫌じゃないけど…。でも別に眠くないよぉ!!!」
あたしは真っ赤になって九条様を見上げる。
彼は涼しげな顔で、
「そうか、ならば私に話でもしろ。」
と言ってきた。
「話って…う~ん、何が聞きたいの?」
ちょっとキンチョーして焦り気味のあたしの額に、ポンって手が置かれた。
サラッとした低めの体温が逆に心地よい。
「お前の幼少時代の話が聞いてみたい…。」
言いながら、彼の唇が降りてきた。
そう。
彼が接吻をしてきたのも、ついこの間の事だった。
非現実的な世界に生きている公家のお坊ちゃんは、あたしが遊郭がどんな所か説明した時、男女の行為すら知らなかった…。
いや、知らない振りをしてただけなのかもしれないけど…。
「コウノトリが子供を運んでくるのではなかったのか。」
と、至極真面目な顔で問い質して来た位なんだから。
ちなみに接吻という行為すら知らなかったらしくって、彼の連れが酔いつぶれてあたしの連れの遊女にあつ~く接吻をかましている所を目撃して、
「あれは何だ?」
とあたしに聞いてきたのだった。
そこであたしは、男女のいろはを教える事にした。
「男女とは、そういうものなのか。くだらないな。」
あたしのなが~い長い(愛の生殖行為の)説明を聞き終わった九条様は、格別驚いた風でも恥じた風でもなく、さらりとそう一言述べた。
「そういうものなのですっ!!!っていうか九条様にそういう事を教えた人は居なかったんですか??」
あたしはちょこっとだけ呆れて聞いてみた。
だって、ねえ…。
この歳になってそんな事も知らないなんて、絶対おかしいし。
「私は妻帯を許されていない。妻帯したいとも思わない。このような所に来ている事も実家は知らないであろう。」
と、涼しい顔でまたもや言い放った。
え?
妻帯を許されてないって、どういう意味??
まさか僧侶じゃぁないよねえ??
髪の毛フサフサで長いし…。
「何で?」
と聞こうとしたけれど、白くて無表情なその顔が何故だか寂しそうで…。
どういう訳か、あたしの方が切なくなった。
この人は、どこか孤独な影を宿していて…。
独りじゃないんだよと教えてあげたい、と思った。
「………ちゅ。」
あたしは意図的に、彼の青白い頬に小さな接吻をした。
「…っな!!!!//////」
九条様は目を見開きながら後ろに後ずさる。
「ね。接吻も悪くないでしょ?」
と無邪気に笑ったあたしを無視して、彼はそれから半刻ほど口を利いてくれなかった。
「しょっぱいぞ…。」
あたしの唇に軽く触れた九条様は、顔を顰めた。
そういえば今さっき塩水を飲んだばかりだった。
「ごめん、さっき塩水飲んだから。」
「塩水?…何の為に??」
遊女は定期的に塩水を飲む。
それは、遊女達の間で古くから伝わる魔除けでもあり、避妊の手段の一つでもあった。
「うん…ちょっとね。」
言葉を濁すあたしの頭に彼はポンと手を置いて、優しくひと撫でした。
あたしの言葉の意味を悟ったのだろうか。
「そうか…。無理をするな。……お前に何かあると思うと……心もとない。」
静かな彼の声がまるで子守唄みたいで、あたしはふっと目を閉じた。
→ちょっとこれからどうなるのか覗いてみます??
「あっ!!」
七ツ時。
まだ日も昇っていない早朝。
茶屋のものが遊女達を迎えに来た声とどたどたという足音で、あたしは目を覚ました。
一体いつから眠っていたんだろ?
隣を見ると、目を見張るような美人があどけない顔であたしに寄り添いながら寝ていた。
「う~~~ん。」
朝に弱いあたしは、ポリポリと頭を掻きながら昨夜何をしたか思い出そうとする。
「結局あたしら何やったんだっけ?」
全く持って覚えてない…。
あたし、まだ若いのに…ボケちゃったの???
確か、九条様と色々話してて、それからそれから…。
「あ、……そうだった。」
あたしは隣で安心しきって寝ている美人の顔をマジマジと眺めた。
「木蘭さまぁぁぁ~~!!」
聞きなれた禿の声が聞こえた。
ってか、もう時間!!!
あたしは隣でまだすやすやと寝息を立てている九条様を叩き起こした。
「ああ~~~~朝だあぁっ!!!!」
九条様を見送る為外に出たあたしは、大きく伸びをした。
「お前の様子が心配だ。何かあったら私は六助を代理として遣わそう。」
との九条様の勧めを断って(だってお化けに話しかけられたくないも~ん!!)あたしは
「絶対報告がてら文を送るから。」
と硬く約束した。
「京に戻るまでまだある。またすぐにお前を訪ねるから待っておれ。」
強くあたしを掻き抱いた後、悲しそうな顔をして去っていった九条様を見送ったあたしは、禿を従えて揚屋からトボトボ歩いて松田屋に戻った。
また、今日も一日が始まる。
また同じ梅山の朝。
……でも、その前に置屋でもう一眠りしよっと!!!
暖かい口付けだけでは物足りなくって。
接吻される度、意思に反して体の火照りが増す。
あたしはどんどん貪欲になっていって…。
「…もっと…。」
と首に手を廻してその人を引き寄せた。
一瞬その人はビクッと体を震わせたけれど、やめたりなんてしなかった。
優しい口付けは何度も降って来る。
あたしはそのままその人の上に覆い被さるような格好になった。
ちょっとばかり大胆に、その人の白いうなじや着物から覗いた胸元に唇を這わせる。
「木蘭…やめっ……。」
苦しそうな声が聞こえたけれど、唇で塞いで彼の抗議を止める。
そのままその人のすらりとした体を愛撫した。
「はっ…なっ…何を……っっっ!!!」
最初は胸を。
白い胸の頂を、指で軽く擦ったり抓んだりして刺激を与える。
「…っ…。」
彼の口から快感の喘ぎが零れ出ると、あたしは手を着物の奥深くに侵入させ、わき腹に移動した。
敏感な所を弄って擽る。
「もく…蘭…あ…やめろ…!!!」
次は、凹んだお腹の中心を。
内腿の探索を終えると、あたしは 一番最後の目的地へと手を伸ばした…。
「!!!!!!」
声にならない叫び声が出た。
吃驚したのもあって、彼のそこを確認するかの如く強く弄った。
どんなに揉みしだいても、扱き上げても、着物の下から褌越しに触れたそれは、全然変化をしていなくて。
「…何で…??」
あたしが手を止めたので、僅かに顔を桜色に蒸気させながら彼は半身を起こした。
怒っているみたい。
整った顔の、薄い瞳に冷たい光を宿しながらあたしの手首を強く握る。
爪が食い込む。
「だから言ったであろう?私には妻を娶る資格が無いと…。」
あたしを睨むように見据える茶色い双眸は、泣き出しそうな潤みを含んでいた。
でも掴んでいる手にはどんどん力が入っていって。
「痛っ…。」
あたしが苦痛で顔を顰めると、彼はハッとして手首を離した。
「…悪かった。」
俯いた彼は、少し間をあけて再び顔を上げた。
「お前は私を嫌うか?」
花のような綺麗な唇を、血が滲み出そうなくらいかみ締めて切ない声であたしに問うてきた。
ドキンッ。
胸が一つ大きく鳴った。
「嫌うなんて…そんな。…嫌わ…ない。そんな事で嫌えるはず無いよ。九条様は九条様だから…。」
あたしは頭を振りながら、彼を見る。
何でだかわからないけれど、あたしの方が泣いていた。
その人は、フッと表情を和ませて。
そして再びさっとあたしの手を取った。
今度は優しく。
その手を、彼の心の臓の上に置く。
ドクン、ドクンドクンという鼓動と共に、あたしの中に何かが送られてきた。
それは、水面に映る水鏡の如くゆらゆらと、曖昧な映像で。
「えっ…。」
そして、全てを悟った。
それは、彼の複雑な生い立ちと孤独な半生だった。
彼が。
徳川家康様の孫を娶りながら帝が血の繋がる妹と通じて出来た、血の濃い不義の隠し子であるという事も。
その濃い血に呪われ、性的に障害を抱いて生きてきたという悲しい半生も。
養子に出された後も、養子先の九条家は帝から押し付けられた責任を疎ましいと厭い、妖しい力を持つ彼を恐ろしく忌まわしいと思いながら育てた事も。
幕府に彼の存在…真の生い立ちを知られたら、朝廷は幕府によって潰されるかもしれないだろうという驚くべき事実も。
「残念な事に、私には私の人生を見る力が無い。だが、私は自分がどんな生い立ちだったのかは知っているつもりだ。……こんな私でもお前は厭わないか?」
彼も綺麗な頬に一つ涙を溢しながら、あたしの手を握り続けていた。
「もちろんっ。そっちこそ、こんな遊女なんて身分のあたしでよければねっ。」
あたしは、化粧の崩れた滅茶苦茶な顔で微笑んだ。
「……そうか、良かった。」
滅多に笑わない彼が、笑顔を見せた。
しまった!!
と思ったときには遅かった。
人で賑わっている大通りを駆け抜け、町人の住んでいる長屋の裏通りまで来て上手く巻いたと思っていたのに、甘かった。
あたしを追いかけて来た輩は
「やあ~っと見つけたぜ、お嬢ちゃん♪」
と誇らしげに毛がぼうぼうに生えた胸元を着物の合わせから曝け出し、濃い髭面を近づけて臭い息を吐きかけてくる。
「ぎ、ぎもぢわり~~~~!!近寄って来んな、たこ坊主!!!」
あたしが抵抗しながら後ろに後ずさると、ぽん、と誰かに抱きとめられた。
「そうだよ、そんな細せぇ~足で俺らから逃げようなんて百年はやいんだよ~。」
と、首筋にまたしても悪臭がかかる。
ちくしょ~~、回り道しやがった!!!
「離れろ、ブタ!!!」
あたしがもがけばもがくほど、逃しまいと悪臭男の力は強くなる。
「かなりの別嬪だな。きっと良い値で売れるぜ。ま、その前に味見ってぇーのも悪くねぇよな。」
男は下品に舌なめずりした。
あ、味見って言った今???
ま、まじっすか??
こんなゲスな輩、死んでも嫌だ!!!
あたしは、必死に抵抗した。
全ては、今日の昼の店が始まる前の自由時間に、また例の如く梅山街から抜け出たのが原因だった。
三河屋で売っているお煎餅がどうしてーも食べたくって(あ、あと適当に買い物も)、あたしは布団に細工し寝ている振りをしてこっそり松田屋を抜け出した。
もちろん、町娘の格好をして。
んで、煎餅を頬張りながら今巷で人気の人形芝居を見ていたら、この超怪しげな輩に連れ去られそうになったって訳なのである。
その時はおもいっきり股間に蹴りを入れて逃走したんだけど、なんせ歩幅が狭くって堅苦しい町娘の格好だもんだから、今みたいに捕まっちゃったのだ。
とその時。
あたしの視線に片目に眼帯をつけた一人の男の姿が映った。
人気のないこの裏通りを、浪人風の格好でこちらに向かって颯爽と歩いてきた。
一瞬、あたしと男達の間に緊張感が走る。
あたしを襲っている悪臭男達もその瞬間ギョッとして、あたしが叫ばないように口を押さえつけようとした。
「た、助けて!!!!」
でも、あたしはそいつらの土と垢のついた手を逃れて大声で叫んだ。
浪人風の男の人は。
冷たそうな隻眼で、一瞬あたしと暴漢達を見て、すっと素通りしようとした。
えっ?
チョット待ったぁぁ!!!!
おなごが襲われてるってのに、シカトっすか!!!!!!!!
「ちょっ、助け…!!!!」
とあたしが言う声も届かず、男の人はそのままスタスタと素通りしていった。
え??どうして??
半ば茫然としたあたしに、悪臭男は
「ふあははははははっ!!!残念だったな、お嬢ちゃん。だーれもあんたをたすけちゃぁくれないんだよ!!」
と言いながらあたしの腕を後ろ手に縛り上げた。
ちょっちょっちょっちょ、あたしこのまま、またどっかへ身売りされちゃうの??
まじぃ~~~~???
と、半泣きになっていると。
シュッと何かが飛んできて、あたしの手を縛り上げていた男の眉間にブスッと刺さった。
それは、短い短剣だった。
「うそ?!」
「何だお前はぁぁぁ~~~!!!」
あたしと、あたしの隣の悪臭男が叫んだのは同時で、
気づいたら男は鳩尾に一発食らってその場に伸びていた。
「あの、何方か存じあげませんけどぉ~、有難うございます。」
あたしは、その浪人風の男を見た。
中肉中背の、片目を覆っている黒い眼帯が印象的な肌の浅黒い男の人だった。
吊り上った目が特徴で、冷たい雰囲気。
「…いいえ。」
あたしを品定めするようにジロジロ見つめながら、ちょっと変わった掠れ気味の声で男は答えた。
「その男の顔が気に食わなかっただけ。」
そう言い放つと、その人はさっさとあたしに背を向けて立ち去ってしまった。
「……。変わった人。」
何が起こったのか悟る間も無く、あたしは暫くそこに立ち尽くした。
っつーか、一体何なの??
助けるなら知らん顔しないで最初っから助けろ、と今さっきの男に言ってやりたかったのに。
「かっこつけてないで最初っから助けろ、ばかやろぉぉぉ~~~~!!!」
とのあたしの叫びだけが空しく通りに響いた。
「そうだったか?」
あたしは隣の男に酌を注ぎながら、長々と説明した。
「俺は覚えておらん。」
少しだけ意外そうな顔をすると、その男、石見正利はグイっと酒を仰いだ。
この人はいつもそう。
いつもポーカーフェイスを保って何にも知らない振りをする。
これで四度目の指名。
あまり喋らないで、いつも静かーにお酒を飲む。
きっと名前も偽名なんだと思う。
でも、あたしにはどうでもいい事だった。
それよりも。
彼は、どこでどうあたしがこの梅山で働いていると知ったのか、あの事件があった翌日知らん顔で梅山街にやって来たのだ。
そして、難なく揚屋に上がり、相手をした事も無いのにあたしを指名してきたのである。
「そうです(怒)。なんで石見様はあの時の事覚えてないの!!!」
あたしが怒った顔をすると、彼は方眉を上げた。
「お前も執着するな。その男に惚れたのか。」
くくっと歪んだ笑みを溢すと、また杯に口をつける。
空になるとあたしに杯を突き出して、
「注げ。」
とお酌をさせた。
む、むかつくぅぅ~~っ!!!なんなの、この人の余裕は!!!
あたしは隣の屈折した性格の男を注視した。
左目は眼帯と黒々とした前髪で隠してあって見えない。
でも、傷跡が見え隠れする浅黒い肌に、翳りを持った吊り上がり気味の右目と掠れた低い声が印象的である。
多分、一般的な観念からすると、美男子の部類に入るんだと思う…。
っつーか、なんで眼帯をしているんだろう?
目が見えないのかな??
どんなにあたしがジロジロ見ててもぜーんぜん動じず。
あたしに楽を奏でろとか、舞えとかの注文も一切せず、彼はただひたすら飲んでいた。
見た目はただの浪人。
でも、下級武士みたいな格好の割にはお金をちゃんと持っているようで、支払いは前払いできちんと済ませていると聞いていた。
「変わったお客だわ。」
と、あたしは呟いた。
「石見様、何であたしの名前を知ってたの?あたしの事知らないのによく指名してきたわね。」
あたしは彼にお酒を注ぎながら質問する。
石見様はちらり、とあたしを見て杯に視線を戻した。
「太夫に会いたいと言ったが、忙しいと言われた。」
太夫様??
じゃあ、あたしは太夫様の埋め合わせだったの??
まあ…よくある話だけど。
「と、言うの全くの嘘だ。」
「はあ???うわあ!!!!」
思わずあたしは大声で叫んでしまった。
超吃驚した!!!
だって、だって、石見様がいきなり耳元で囁くんだもんっ。
掠れ気味の声とあたしの耳にかかる吐息が…っ。
しかも、顔が超間近で横を向けない!!!
硬直したあたしの耳元で、石見様は更に呟く。
「梅山の格子木蘭は、一度その味を味わうと忘れる事が出来ないと聞いた。」
そう言うと、ペロリとあたしの耳を舐め上げた。
うわあああああ~~~~~~(←思いっきし動揺!!!)
「俺も酔いが回ったようだ。その果実を味わってみたい。」
マジで???!!!
と思っている暇も無く、あたしは石見様に押し倒された。
→これから何が起きるか読んでみます???
媚薬はともかく、変な暗示にまでかけられてたなんて全然気づかなかったあたしはその後ぐっすり寝てしまい、翌朝ゴソゴソという物音で目が覚めた。
っつーか、手首が痛いんだけど…。
あたし何やったんだっけか??
何故だか記憶がすっかり飛んでる。
昨日は確か石見様のお酒を注いでてぇ…。
それからあたし何したんだろ???
う~ん、と独り唸っていると部屋の片隅から声がした。
「これをやろう。」
身支度をしている石見様は、まだ眠気眼のあたしに向かって何かを投げ寄こした。
「何、これ?」
不思議に思って小さな竹でできたそれを手に取って観察する。
「伝達鷹を呼ぶ笛だ。」
帯を締めている石見様は、後ろを顧みず静かな声で答えた。
「笛?」
何の為に??
と聞こうとすると、
「俺と連絡を取りたければ、伊賀の半三宛てに文を送れ。」
との言葉に遮られた。
あたしはキョトンと小首を傾げながら石見様を見つめた。
「伊賀の半三?」
どっかで聞いた事あるぞ?
「身請けを望むのであれば、半三に文を書け。」
「はあ…。」
う~む。
何で伊賀の半三って人なんだろ??
あたしは、石見様に羽織を着せるのを手伝った。
「見送りはいらん。俺も暇を見つけてまたお前に会いに来てやろう。」
落ち着き払った声でそういい残すと、踵を返して足早に部屋を出て行った。
ふと、彼が立っていた所に目をやると。
一枚の紙切れが落ちていた。
「石見様の忘れ物…。」
あたしは彼の後を追って揚屋を出た。
なのに、石見様の姿はもう何処にも見えなくて。
「はやっ…。」
あたしは揚屋の前でその紙切れを広げて見た。
それは、いわゆる関所越えの為の通行証書で。
その証書に書かれてあった
『~~三河服部党党首、服部半三正利の通行を許可す~~』
という文字を見 て、あたしは凍りついた。
だって、今更ながら思い出したんだもん。
あの、超有名な忍びの一族の事を。
「ちょ、ちょ、ちょ…あたしを騙したのね~~~~~!!!!!」
っつーか彼の正体に気づかなかったなんて…。
いや、それよりも、何で昨夜の事が思い出せないんだろう??
もちろん、その時は石見様…いや、半三様が緻密な諜報力を武器とする忍術と暗示の達人だという事は知らなくって。
「不思議な人…。」
あたしは彼が(恐らく意図的に)忘れていった通行証と竹笛を握り絞めながら、次回会った時は伊賀の里と彼の眼帯について聞いてみようかなどと考えていた。
「俺の右目を見ろ。」
「はあ?右目??」
言われるままに眼帯をしていない彼の吊り上がり気味の右目を見つめると。
石見様はあたしの手を取って手と腕の何箇所かのツボ押した。
「……あ。」
途端に、頭がボンヤリとしだして…。
その上、形良い薄い唇に塞がれたあたしの口の中に、何かが流し込まれる。
この味…。
知っている。
巷で話題の媚薬、紫躰止湯だ…。
「こんな…飲ませっ……ずる…い。」
「ふつうに体を重ねてもつまらないだろう?」
くくっと冷たく笑うと石見様はしゅるるっ、と一瞬にしてあたしの帯を解いた。
素早い。
人形のように体が言う事を利かないあたしは、彼されるがままになっていて。
あたしの両手を取ると、あたしが巻いていた下帯を使って頭の上に縛り上げた。
部屋に常備してある手拭であたしの目を隠す。
普段のあたしだったら、そこでもがくなり叫ぶなりして抵抗するのに、今日はそんな気力も全然起きない。
これは…何?
「生娘以外とは始めてだが…。フッ、男を知り尽くしている女を制すのもまた一興。さて、何をしようか…?」
視界の遮られたあたしの唇を貪りながら、石見様はあたしの裸体に手を這わす。
「ああっ!!」
ビクッと。
少し触られただけで体が大きく震えた。
五感の一つを封じられているあたしの他の感性は敏感になり…。
「何が欲しいのか、言ってみろ。」
あたしの胸と脇腹を荒々しく弄りながら、石見様は意地悪く問うてきた。
愛撫を辞めないで欲しい!!
意識が朦朧としだしたあたしは何故かそう強く願ってしまい…。
「いし…み様に…触って…もらいたい……です。」
としおらしく答えた。
くいっとあたしの胸の先を引っ張りながら、石見様の冷たい質問は続く。
「どこを?言わなければ分からん。」
あたしは頬を赤らめながら、剥き出しの四肢を動かした。
「ここを…触ってください…。」
ふんっと嘲笑うような声が聞こえたと思ったら。
石見様は スッと二本の指をあたしの股の間に差し入れた。
「ひゃあっ!!!」
閉じた花弁を探るように押し開かれてちょこっと芽を擦られただけなのに、あたしの体は大きく震える。
「足を開け。」
との石見様の命令に従って、大きく足を開いた。
「噂どおり、美味そうな果実だな。」
あたしの足元で声がした。
そのまま、ツプッと指が一本挿入される。
「ああああんん!!!!」
たった指一本の侵入であたしは達しそうになった。
「まだ…イク事は許さん。」
言いながらチュルッとあたしの蜜を、いたずらに自らの舌で舐め上げた。
指を奥深くに突き刺しながら、柔らかい舌で蕾を転がす。
「ひゃあっっ!!!お、お願い…。」
もう秒読み段階のあたしの哀願も空しく。
「駄目だ。」
石見様はそう言うと、あたしの下肢から体を離した。
彼を欲して熱くなっているあたしのあそこは火照りが納まらない。
なのに。
グッと熱い塊があたしの口元に宛がわれた。
目隠しされて見えなくてもその歪な形と独自の匂い、それに濡れそぼった先端で何であるかが分かった。
「欲しいのだろう?舐めろ。」
硬く反りたったそれで、ピトピトとあたしの頬を軽く打つ。
「…はい…。」
あたしは彼のそれにしゃぶり付いた。
最初は、出っ張った上の方をチューっと吸い上げ、割れた先端を口の中で舐めまわす。
その後、舌を太い竿の部分に這わせて柔毛が茂っている大きめの袋へ舌を移動させ…。
あたしは、知っている限りの技を尽くして彼の男を味わった。
「……。」
石見様は始終無言で声すら漏らさない。
でも、彼の熱い塊が確実にその時が来ていることを告げていた。
ヌルヌルと、先端の小穴から溢れ出る透明な液を味わっていると。
「出すからな。飲め。」
と一言声が降って来た。
同時にビクリと彼の男が大きく波打つ。
グッと喉の方へ突き上げると、ドワッと一気に口の中に暖かくて苦酸っぱいものが送り込まれた。
「……ンッ。」
あたしは言われるまま、大量に出されるそれを飲み込んだ。
彼は最後の一滴まで搾り出すと。
「なかなかだったな。」
と言い放ってさっさと自身を抜き出し、あたしから体を離した。
媚薬を飲まされて暗示にかけられているあたしは。
下肢を火照らせ視界の遮られた暗闇の世界の中、素直に彼の次の命令を待った。
暫く経つと。
「そうだな…自分で慰めてみろ。」
冷たい感情の無い声音で指示が出た。
「はい…。」
あたしは言われるまま蜜の溢れ出ている自分の花園に手を置いた。
「あ…うんっ・……ん・…・・。」
指で自らの芽を震わせた。
膨張しきったあたしの芽はビクビクしだして。
「んんっ…はっ…ああ…。」
目の前で石見様に見られている、という事をすっかり忘れていた。
いや、この時のあたしの意識自体曖昧で…。
ぴちゃ。くちゅ…。
長い間彼の目の前で蜜を溢れさせながら、自分を慰める。
「はあっ…ん…ふっ……石見…さま…あたし…もう…。」
彼にその時が近づいたと告げようとすると。
「イキそうか?まだ俺はお前に触れてもいないのだが。」
との冷たい声に遮られた。
「俺が欲しいと言え。これが欲しいのだろう?」
目隠で暗黒の世界にいるあたしの頬に、再び頭を擡げた彼の熱い男を擦り付けてきた。
「欲しい…です。」
もう、我慢の限界で。
一刻も早く彼を感じたかった。
「良く出来た。」
石見様は普段通りの抑制した低い掠れ声を発すると、両足を抱えてあたしの中に入ってきた。
あたしを突き上げながら、先ほど果てたばかりの自身を大きくさせていく。
「あっ…ア・・・…んんんっ…・・あふっ…あああんっっ。」
たった何度か突き上げられただけで、感じやすいあたしは果ててしまった。
「どうした?もう終わりか?」
まだまだ果てるつもりの無い石見様は、長い間あたしと繋がったまま腰を打ちつけ続けていた。
あたしは、薬が切れるまで何度も何度も絶頂を迎えた。
家の離れの大きな楓の木の下にいた。
「えいっ、やっ、とおっっ!」
男勝りだったあたしは、木の枝で巨木相手に一人チャンバラごっこをしたり、地面を埋め尽くしたカラカラに乾いた落ち葉の上で足を踏み鳴らしたりして遊んでいた。
家宝の大事な壺を割ってしまったあたしは、父上からこってり絞られて泣きながら家を飛び出した。
「蘭々。」
何処からか、優しい兄上の声が聞こえた。
お蘭という名前のあたしをそうやって呼ぶのは彼だけで。
「兄上!」
顔を上げると、まだ前髪がある元服前の華奢な少年が優しい笑顔を浮かべて立っていた。
あたしは兄上の優しい顔を見つけて無邪気に駆け寄る。
「父上や皆が心配しているよ。形あるものは壊れるが定めなんだ。父上だってそれは分かっている。もう誰も蘭々の事を怒ってはいないのだから、そろそろ強情になるのはやめて素直に中に入ろう。」
小さなあたしの小さな手を取ると、
「蘭々は本当に強情だなぁ。こんなんじゃお嫁に行けないよ。」
と苦笑した。
「お蘭はお嫁に行かないよ。お父様みたいな立派なぶしになるんだから!」
と無邪気に反抗するあたしを見て、
「あははは。それは楽しみだ。きっと僕より強い武士になるんだろうね。」
クスクス笑い声を上げると、兄上は歩いてきた楓道をあたしの手を引いて逆戻りした。
蘭々。
あたしは深い溜息をついた。
「はあ~~~っ。おかしいでしょ?こーんな夢を見るなんて。もうずーっと前に葬った筈の過去なのにさっ。」
囲碁をしながら、あたしは目の前の麗人に昨夜見た夢の事を話した。
この人は。
あたしが東の豊臣方の武将の娘だったという過去を知る唯一のお客だった。
いや、お客というよりも…。
ちらっとあたしは囲碁盤から顔を上げてその麗人を盗み見た。
長い黒髪を結わずにタラリと流して、別に冠婚葬祭があるわけでもないのに年中黒地の着物を着ている。
すれ違えば老若男女問わず誰もが振り向くだろう翳があるものすごい美貌の持ち主だ。
この人は、いわゆるあたしと同業者で。
梅山の奥の方に一本立っている柳の木のそばの一角で、美少年ばかりを置いた男娼宿『虹乃宿』を営んでいる。
お客は主に女性を抱くのを禁じられている僧侶とか、男色の武士とか、あたしら遊女とか、お忍びの武家の妻や未亡人とか色々らしい。
自分の事は一切話さないけど、あたしのつたない推測では自身も昔、この美貌に目をつけられて男娼として売られてこの梅山に辿り着いたみたい。
「それは…木蘭さんがあの頃に戻りたいと思っているからなのじゃないかい?」
言いながらビシッと先手を決める。
「あっ。」
やられた!!!
と思いながら、あたしは答えた。
「別に、もう戻れないものはしょうがないけど…。でも、あたしは父上の後を追って自害なさった兄上が未だに許せない。…兄上まで死ぬ事無かったのよ。浪人になり何なりになってでも、生き延びていて欲しかった。」
東西合戦の後、家は崩壊した。
父上は幕府より切腹を言い付かって自害なされ、母上は心の病に冒され父上の後を追うように逝かれ、兄上は姿を消した。
親戚の話では父の後を追って裏山の崖から身を投げたと言っていた。
そんなあたしも、徳川家に財を押収された親戚によって身売りされたんだけど。
まあ、もう過去の話。
その人、竜之介さんは、苦笑しながら腕を組んであたしの一手を待っている。
「案外君の大切な人達は近くにいて、木蘭さんを見守っているのかもしれないね。その兄上とやらも、きっと君の事が心配だったに違いない。」
「案外近くでって…それはお化けとしてって事?あたしのお客様にそういうのが見える方がいらっしゃるけど…考えただけでぞ~っとする!!!」
「ふふふ…そうかい?」
彼はあたしがなかなか反撃してこないので、腕を組んでニッコリ微笑んだ。
「さて、今日も僕の勝ちみたいだね。」
「うっ……。」
あたしは言葉を詰まらせる…。
だって、だって、竜さんめっちゃ強いんだもーん!!!
「それでは…君と二人だけの逢瀬も久々だし、今夜はここに泊めさせてもらおうかな。」
「え…。」
絶句。
それは…他の言い方に代えると、夜伽の相手をしろって事???
「っつーか竜さんっ!!あなたの宿は歩いてすぐのトコじゃない!!!こんなトコで散財しないでしっかり自分んトコの宿の管理したら??」
あたしはいつものお節介で、そんな事を口走ってしまう。
だって、ねえ…。
彼と褥を共にするといつも…。
「宿の運営で忙しくて、最近休みがとれなかったんでね。おかげさまで繁盛しているし、僕が居なくても宿の子達にはちゃんと躾をしているから、今夜一晩くらい大丈夫でしょう。」
宿の子達って…。
あたしは、彼の宿で働く少年達を思い出した。
どの子も揃って少女かと見まごう美しさで目を引く美少年達。
その上愛想も良い、いい子ばかりなのでこの梅山でも禿や姉様方に気に入られている。
きっと竜さんも昔はあんなだったに違いない。
「さて、と。」
静かに碁盤を片付けた竜さんは。
そうっと自分の帯びに手を添えた。
→これからの二人を読んでみます???
「良い子だね。」
いつの間にか竜さんは片づけを済ませていた。
気づいたらあたしの体も綺麗に拭かれていて。
あたしは、彼にされるがままになっていた。
あたしの裸の体の上を往復する竜さんの絶妙な手つきとお湯に浸された温かい手拭のせいで、眠気があたしを襲って次第にうとうとし始めた。
こんなに気の許せる人は、他に誰もいないなあ…。
などと思いながらあたしは深い眠りに落ちた。
夢は昨夜と同じで。
あたしは再び楓の木の下に居た。
また兄上があたしを探しに来てくれて。
また同じ会話が繰り返される。
夢の中の兄上の顔は、優しいけれどぼんやりとぼやけていて。
あたしは、記憶の中の兄上の顔を思い出そうとした。
見えない。
見えない。
わからない。
兄上。もっとお蘭に顔を良く見せて。
のっぺらぼうのような顔の口元がゆっくり動いた。
懐かしい声で。
蘭々…
蘭々…
蘭々…
幻聴?
あたしは布団を跳ね除けて、バッと身を起こした。
「どうしたんだい?悪い夢でもみたのかな?」
隣には、竜さんが肩肘付いてあたしを愛しげに眺めていた。
「あ…。竜さん、ごめんなさい…。」
目をこすりながら、あたしは一つ大きな欠伸をした。
「蘭々。」
えっ???
心の臓が口から飛び出るかと思った。
竜さんの綺麗な唇から、夢の中で何度も呼ばれた懐かしい名前が零れ出たからだ。
あたしは、サッと顔を強張らせて彼を見た。
「……と、呼ばれていたんだね。寝ている君は何度もその名前を口にしていたよ。」
「あ……。」
夢…。
竜さんは、あたしの頬をそっと撫でた。
気づかない間に、泣いていた。
「大事な人に呼ばれていたんだね。」
竜さんの声はあくまで優しくて。
あたしは目を閉じたまま、頬の雫を拭う竜さんの甘い指の感触を味わっていた。
「もう、君の記憶の中のお兄さんはいないけれど…。僕が新しいお兄さんになってあげよう。君が必要な限り傍にいてあげるから、だからもう泣かないで…。」
そう言ってくれた竜さんの胸の中で。
あたしは子供のように泣き続けた。
「格子の木蘭さんがそんな怯えた顔をしていると、こっちも不安になってしまうよ。」
そっと自分の黒い着物の帯を解き、小首を傾げながら妖艶に微笑む。
ごくっ…。
思わず女のあたしも生唾を飲んでしまうような色っぽさで着物と襦袢を脱ぐと、適度に筋肉のついた身体を露出させた。
この人はどういうわけか褌を履かない。
だから襦袢を脱ぎ去ると…。
「りゅりゅりゅりゅりゅりゅ竜さん!!!!」
真っ赤になったあたしの手を引きながら、自らの体を布団の上に横たえさせる。
め、目のやり場に困るんですけどぉ~~~~(//////)
「何を恥ずかしがっているんだい?男の体なんて見慣れているんだろう?」
あたしの体をヒョイっと持ち上げると、彼のお腹の上に跨がせた。
「そそそそ、そっちこそ、何でそんなに余裕なんですかぁぁぁ!!!」
ドキドキしているあたしの帯の結び目に手を廻してあっけなくスルリと解いてしまう。
「経験の差かなあ?」
白い裸体を曝け出したあたしの胸に一つ小さな口付けを落とした。
「あ…竜さん…。」
巧みな口技であたしの胸の先が快感で張り詰めたのを確認すると、
するりとあたしの体を抱えて横に下ろし、今度はそのままあたしの上に跨った。
彼の妖艶な美貌が目の前にある。
長く垂れた癖の無い黒髪があたしの顔を擽る。
「初めてこの街で僕に会った時、君はまだ小さな少女だったね。…こんなに美しく成長して…。何も知らない相手ではなく、君の良く知っている僕が相手なのだから、落ち着いて。」
悪戯っぽく整った両眉を上げると、もう一言付け加えた。
「それに、僕とは初めてではないでしょう?」
そう。初めてではない。
初めてじゃあないけど…。
でも、この人相手だと少し普通の人と勝手が違っていて…。
何と言うか、その…。
真っ赤になっているあたしの頬に接吻しながら、優しく片手を取った。体を少し上方へ移動させる。
ほらっ、来た!!!
「上手に出来たら、僕も君にご褒美をあげようね。」
そのまま床に膝をつけて仰向けのあたしの顔の上で跨ぐように、陰毛が全て剃られた体を密着させてくる。
「ほら…。君を待っているよ。」
あたしの目の前には、二つの袋とそこから続いた先の小さく引き締まった禁断の蕾があった。
いつも通り、あたしは彼のそこに舌を伸ばして寄った小さい襞の周りを舐め上げる。
「そう…そのまま…あ。…いいよ。」
艶のある声を出しながら、竜さんは悶える。
排泄部分を舐められるという行為は存外快感を高めるらしくて、竜さんは好んであたしに強要した。
小さな蕾はビクビクとあたしの舌に反応している。
「ああっ…このままではいけないね…。木蘭…指を…。」
あたしは指の一本一本を口に含んで充分に濡らしてから、彼の足の付け根の奥の禁断の場所へ宛がった。
ってか、彼の天を向いたお、お、男が目の前でどんどんと…。
「あのお~。竜さんは女の人にいつもこういう事してるの?」
あたしは真っ赤な顔のまま、でも入れる前にどうしても聞いてみたくて竜さんに尋ねた。
もちろん、ソレが視界に入らないように目を伏せて。
あたしの頭の上から声が降ってきた。
「それはもちろんお客様の趣味趣向にもよるけれど、女のお客様には絶対に強要はしないよ。…でも、君との情事は別の話だよ。僕は君と五分五分の快感を分かち合いたいと思っているから。」
答えながら、あたしの小指をとって自分の禁断の蕾に導く。
「ほら、僕の蕾も君の侵入を待ちきれなくてうずうずしているよ…。っん…。」
竜さんは小さく喘ぎ声を漏らす。
「前にも話したと思うけれど、男娼の教育は大変でね…。最初は小指で慣らすんだよ。そう、こんな感じに…。」
彼の中は暖かくて、そして適度にあたしの指を締め付けた。
「襞の周りをよく揉んで…次は、薬指。」
あたしは小指を抜いて薬指を挿入させる。
「そう、いい子だね。とっても上手だ…。ああ……気持ちがいいよ。」
中指に続いて人差し指を挿入させると、竜さんは目の前の熱く火照った塊をあたしの口元に擦りつけてきた。
彼の太く反り返っている雁首からは小さな透明の雫が出てきて男に伝っている。
「竜さん…。」
あたしが小さな雫をぺロリと舐め取ると、竜さんは無言であたしの親指を蕾に導いて宛がった。
水牛の角で作られた張り型は、遊郭で働いていれば誰でも見たことがあるし、好んで使用している人もいた。
でも、鼈甲で作られた高級張り型はあたしですら滅多にお目にかかったことが無かった。
竜さんが自分の所から持ってきた張り型は、特注らしい鼈甲製の男性器そっくりの形のものだった。
あたしが予め用意してあったお湯にそれを浸して暖めている間、竜さんは潤滑油を蕾の周辺に塗っていた。
「木蘭、準備ができたからおいで。君の体を味わいたい…。その、美しい体を…。」
仰向けに横たわり長い足を大きく開いた竜さんはあたしを顔の前で跨がせた。
パックリと口を開いた花弁と小さく窄まった蕾が彼の目前で突き出す格好となる。
「物凄く濡れているよ。僕に触りながら我慢していたんだね。」
いわゆる二つ巴(69)の体勢で。
竜さんはあたしが手に持っている暖かい玩具にも油を塗るように指示して、自身の潤滑油が塗られた窄んだ蕾に導いた。
「…ん……木蘭っ…そう、そのままゆっくりと押して…。」
あたしは言われるまま時間をかけてそれを挿れていく。
小さな蕾にそれは吸い込まれていって…。
「ああっ…。」
竜さんの喘ぎがとても色っぽい。
大きめな型の先端が飲み込まれると、そのまますんなり奥まで入った。
「……動かして…ごらん…。」
快感で声を上擦らせ気味の竜さんは、あたしに彼の中の物を動かせと言う。
あたしがゆっくり出し入れを始めると、竜さんはあたしの花弁をプロ(達人?)の舌使いで舐めだした。
片手で膝立ちのあたしの桃尻を押さえながら、もう片方の手で怒張した自身を扱きだす。
その先端からは透明な液が流れ出ていて…。
「やんっ…竜さ……っ。」
あたしの方はというと、花弁から送られる快感で彼の蕾への刺激を怠りそうになる。
「…ぁ……そう、だ…いい子だね……上手い…よ…。」
竜さんは切なげに呟くと、舌をつかって真珠を小刻みに揺らしたり、禁断の小穴に尖らせた舌を突き入れたり、指を使ったりしながら休まず刺激を与えてきた。
さすがこの道の達人だけあって、あたしの花弁への刺激は並みじゃない。
あたしの下半身はもう既に力が入らない。
それでも、あたしは竜さんにも同様の快感を感じてもらいたくて、徐々に彼の蕾への出し入れを速めた。
ぴちゃ、ぴちゃ…くちゅ。
「ひゃあっ!!!!!!」
あたしの花弁の奥のスポットを竜さんの指が強弱をつけて突付くと、電流が流れたように全身が痺れた。
失禁、のような透明な飛沫を飛び散らせてしまう。
その弾みで、玩具を彼の奥深くへ突き上げてしまった。
と、同時に。
「木蘭、僕も来る…あああぁ!!!!」
竜さんの切羽詰った声が聞こえた。
彼が自分で扱いていた熱い塊から、白い欲望が勢いよく噴出した。
それは上に乗っているあたしの白い腹部に直撃して…。
お互いの愛液にまみれたあたし達は、そのまま暫くぐったりとしていた…。
青空が広がったよく晴れたある日の事。
眩しい朝の太陽に照らされながら、あたしと禿のおりんは揚屋から松田屋に向かって歩いていた。
「ねえ、木蘭姉様。」
まだ小さなおりんはチョコチョコとあたしの後を追いながらふと尋ねた。
「何?」
眠いな~、とか思いながらボーっと歩いていたあたしはちょっと不機嫌な声で答える。
「木蘭姉様。姉様は本気で“恋”した事ある?」
「はあ?」
まさか突然十歳かそこいらの少女からそんなませた質問をされるとは思わなかったあたしは吃驚して気の抜けた声を出してしまう。
おりんは、眉を顰めているあたしを見て
「ううん、やっぱいいやっ。」
と顔を赤らめながら呟くと、あたしを置いて走り出した。
「あっ。こらっ、待て!!!」
清清しい風が心地良い青空の下。
あたしは着物の裾を持ち上げ、おりんを追ってを走った。
その人は、あたしがまだ無名の遊女だった十六歳の時。
楓姉様目的でやってきた有馬惟宗さんについて揚屋に遊びに来た。
彼の名は、有馬次宗。
名門有馬家の次男。
妻を何年か前に亡くし、三十代の男やもめながら一人息子を育てている子連れ狼で。
あたしは彼らが待機している部屋に足を踏み入れた途端、お座敷の奥で胡坐をかいて莞爾と笑いながら酒を飲んでいる彼の姿に釘付けになった。
特別目を引く美形でもない。
ただ精悍で、体格が良くて、年相応の渋い魅力に溢れた男の人で…。
その健康的な笑顔に吸い込まれそうになったあたしは、始終彼から目が離せないでいた。
あたしと十七も歳が離れているけれど。
そのうち、あたしの熱い視線に彼も気付いてくれて。
何度か惟宗さんについて揚屋に上がった後、あたしを個人的に指名してくれるようになった。
「惟宗がいつも世話になっているな。」
初めて二人きりになった夜。
彼はそう言って話を切り出した。
「ええ…まあ。」
いつも楓姉様と喧嘩したり暴れたりして迷惑がかかっていると、素直に本音を言っても良いのだろうかなどと言葉を濁しながら考えていると。
あたしの表情を読み取ってか次宗さんは、
「あの馬鹿もここまで来て人様に迷惑をかけているようだな。恥ずかしい限りだ。」
と苦笑した。
白い歯が覗いた浅黒い逞しい彼に顔を覗き込まれると、体中が火が吹いたような火照りを覚える。
そう。
もう既に気付いていた。
あたしは、この溢れ出そうな想いが尋常ではない事を。
この人を、客以上の存在として見始めていた。
それは、歳の離れた男に対して誰もが持つ憧れのようなものの延長線上にあって。
それでも、あたしは彼を一人の男として欲っする自分に気付いていた。
彼の前では心拍数が上がってしまって声も出ないあたしに気づいているのかいないのか。
「お前は絵を嗜むか?」
落ち着いた低い声音で尋ねると、次宗さんは懐から懐紙と筆を取り出して何かをすらすらと書き始めた。
「俺は根っからの武人だが、水墨画は幼少の頃から趣味でね。今でもたまに嗜むんだ。」
と浅黒い顔を仄かに赤らめ照れながらそっとその紙をあたしに差し出した。
それは一本の墨で描かれた見事な菊の花であった。
「すご…っ。すっごいお上手…。あたし狂歌と囲碁と琵琶だったら自信あるけど、絵の才能は皆無だから…。」
感嘆しているあたしを優しく見つめる。
彼のごつごつとした指が、絵を持っているあたしの手に触れた。
その触れ合った場所が、痺れた。
心臓が、一人でに鼓動を速めていって…。
「惟宗には俺がここに通いだした事は内緒だぞ。またあいつに絡まれたら五月蝿いからなあ…。」
はははと大口で豪快に笑いながら、彼はあたしを広い胸の中にそっと抱き寄せた。
あたしの常連となり、定期的に松田屋に足を運ぶようになった次宗さんと会える日は、とびきりお洒落をして着飾った。
「まるで恋する乙女ね。いい事だわ。」
そう言ってくれたのは、あたしの尊敬していた楓姉様で。
恋というものは女を美しくするものらしい。
周りの禿や遊女達からも、
「綺麗になったね、木蘭ちゃん。男かしらぁ??」
と冷やかされた。
そのまま、彼と知り合って一年が過ぎた。
→これからの二人を読みます??
情熱的な夜を過ごした次の日の四つ時過ぎ。
早朝別れたばかりだというのに次宗さんは、早馬を駆けて松田屋の前に乗り込んできた。
本来ならば、この界隈へ乗馬しながらの侵入はご法度となっているのに。
「木蘭っ。木蘭に会わせろ!!」
何故か息咳切っている。
店先の禿に呼ばれてあたしが顔を出すと、
「今から行く所があるっ。だがその前にお前にこれを渡したかった。」
と、店が開くまで昼寝していた寝ぼけ眼のあたしの手の中に何かを投げ寄こした。
「どうしたんですか?さっきお別れしたばっかなのに…。今度来た時でも良かったのに…。」
ぼーっとしているあたしを馬上から見下ろしている次宗さんの顔は、逆光で見えない。
ふと、口元がゆがんでいるのが確認できる程度で。
「愛している。またすぐに会いに来よう。またなっ。」
来た時と同じ速さで次宗さんは駆け去っていった。
あたしはその場に佇みながら、無言でずっと彼の背中が小さくなるのを見守った。
手の中の薄紙には、黒と白と灰色の見事な色調の水墨画で。
蘭の花を優雅に持ったあたしが描かれていた。
その翌日。
天羽一馬という浪人が、名門有馬一門を破ったという噂が梅山中、いや、江戸中に流れた。
噂では。
有馬一門を代表して道場で二番手の次宗さんが天羽一馬とかいう男の決闘の申し込みを受けてたったらしい。
そして…。
「あはははっ。まさかあの次宗さんがねぇ。そんなんデマに決まってるじゃない!」
最初は噂を信じていなかった。
そう。
弟の惟宗さんが、彼の遺留品のお守りをわざわざ松田屋まで届けに来るまでは。
「すまねーな。兄貴の所持品っていったらこれしか無くってよ。でも、兄貴はこのお守りを羽織の袂に縫い付けてあの男に挑んだんだ。だから、大事に持っててくんねーか?」
中には、あたし宛の遺書と、昨夜渡した髪の毛の一部が入っていた。
「嘘…。」
彼の口から直接その悲報を聞いた時、あたしは呆然とその場に座り込んだ。
そっと、惟宗さんは手をあたしの肩に置く。
「結構いい勝負だったんだぜ。あの男も片目をなくしたし。・・・・・・けどよ、認めたくねーけど、あの男は尋常な強さじゃ無かった。」
心なしか、彼の声は震えていた。
「兄貴が俺たちに残した遺言では、たとえ天羽一馬に負けて命を散らせても、悔いは無いから仇討ちなんて有馬一門の名を汚すような真似だけはするな、って書いてあった。兄貴らしーよな??」
あたしは俯いたまま。
彼の残したお守りを握り締めた。
「……分かってくれ。俺達も、つれーんだ…。」
あたしの肩に置かれた手に力が入る。
愛している…
俺の所に来い…
昨夜の彼の言葉がこだまする。
彼は、今日の決闘の事をあたしに黙っていた。
あの、情熱的な行為の間も。
きっと。
有馬家の跡継ぎである長男が亡くなってはならないからと、自ら一門を代表して決闘に挑んだのだろう。
今の問題が片付いたなら…
愛している…
愛している…
何度も何度も昨夜の言葉が頭の中で繰り返される。
本当に悲しいと、涙と言うものは出てこないらしい。
あたしは地面にヘ垂れ込んだまま、天を仰ぎ見た。
空は、青かった。
どんっ、とおりんを追っかけて走っていたあたしは強かに誰かの肩とぶつかった。
ヨロリとよろける。
だけど、瞬時に伸ばされた手が、助けてくれた。
ふう~っ、転ばなかった(滝汗)!!
危ない危ない!!!
「あっ、すいませーんっっ。」
と顔を上げると。
「大丈夫ですか?」
深く被った編み笠の下から、何処かで見た懐かしい顔とぶつかった。
「え・・・?」
まさか。
もう何年も前に死んだ人間の名前を口にするなんて、馬鹿げている。
でも、咄嗟にあたしの口から、彼の名前が零れ出ていた。
「次宗……さん?」
「松田屋の木蘭さん…ですか?」
その人は、白い歯を見せて健康的な笑顔をあたしに向けた。
「良かった、松田屋に行ったらまだ揚屋にいると言っていたのでそちらの方に向かっていた所なんですよ。」
言いながらあたしの横に並んで歩き出す。
「叔父の惟宗殿の使いで参りました、有馬由一郎と申します。」
隣の男の人は元気に話しかける。
あたしより、一,二歳は若そうだ。
「父上は生前母上以外の女性について一言も私に話をしてはくれなかったんですけどね。」
父上…。
そういえば、今まで会った事が無かったけれど、次宗さんはあたし位の息子がいると言っていた。
「父が死ぬ間際にあのお守りを持っていなかったら、私も惟宗叔父も父上が好んで梅山に来ていたなんて知らなかった。」
ハハハ、と白い歯を見せて笑う。
どこか、懐かしい。
あたしは目を細めながら無言で彼の話を聞いていた。
「私も、やっとこういう場所に来れる年齢になれたものですから…。」
こんな遊郭街とは縁遠そうな、さっぱりした好青年。
「さっきも言いましたが…今日は叔父の代理で…。初めて貴方とお会いしますが…噂どおりの綺麗な御方で…。なんか、緊張します。えっと、あの、明日は父の…。」
知っていた。
明日は丁度、三回忌。
毎年毎年彼の命日には弟さんの惟宗さんがあたしに会いに来てくれていたから。
「蘭の花を。」
「え?何ですか?」
あたしは立ち止まってすぐ横の青年を顧みた。
「あたしの代わりに、今年も蘭の花を一輪彼に持っていってあげてください。」
「蘭の花…ですか?」
あたしはそっと頷く。
「あたしには、彼にあげられる物が他に何一つ無いから。」
それじゃ、と断りあたしは再び松田屋に向かって駆け出した。
「えっ。ちょっと待ってくださっ…。」
後ろで息子くんの困った声が聞こえたけれど、あたしは通りを全速力で駆け抜けた。
次宗さん。
木蘭は、まだ貴方の事を忘れる事が出来ません。
お守りの中身を確認する勇気が出るまで。
梅山を出て、貴方のお墓へちゃんとお参りが出来るまで。
あたしは貴方への涙を溜めておくと決意をしました。
だから、その時まで。
あたしを天から見守っていて下さい。
あたしは青い空を見上げて、そう呟いた。