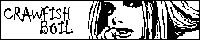俺は寮の有る大学の前で鷹男に車から降ろしてもらうと、そのまままたタクシーを拾って紅の家へ向かった。
「ど、どうしたのその顔......てか、その格好!」
紅が夜型の人間で良かった。
もう午前1時をまわっているのに、仕事中だったのか紅は眼鏡をかけた普段着姿のまま、俺を家に入れてくれた。
「今日鷹男とEFのパーティー行って来た」
「へえ。ドレスはキレイだけど、染みついてるし......顔、メーク取れてるよ。......泣いてたの?」
「な、泣いてねえよっ」
俺はそう言って腕で目を擦る。
黒いマスカラかアイライナーみたいなものが、腕につく。
「ちょっと待ってて、お茶淹れて来るから」
足を引き摺ってキッチンに消えた紅は、1分もしないうちに居間に戻ってきた。
「どうして泣いてたのさ。言ってごらん?兄貴に何か言われたの?パーティーで何かされたの?」
俺がお茶を一服すると、紅は俺を仰向かせてティッシュで目の下を拭ってくれた。
「理由次第では俺、兄貴の事タダじゃおかないつもりだよ」
「だから、泣いてねえよっ」
実際の所、泣いていた。
ここに来るタクシーの中で、俺はシルクの布地が汚れるのも構わないで泣き続けた。
車を降りる直前、再度鷹男から冷たい声で言われた。
「あのキスは単なるお遊びだ。言わなかったか?お前との関係は全て『契約』であり、俺の中では『ゲーム』だと」
そんなの分かっていた事だった。
なのに、女々しくめそめそ泣いている。
そんな自分も許せなくて、余計に泣けてきた。
「紅、俺にキスしろよ」
俺は俺の顎に手を置いている紅の手を掴んだ。
「キス?翠キスって......」
と、そこで言葉を止め、俺の顔をジッと見入る。
「兄貴に、キスされたんだ」
紅が感情を抑えた小さな声で呟く。
俺が答えないでいると、紅は意を決したみたいに俺の瞼に唇を寄せた。
「目、瞑って翠......」
俺は言われるまま目を瞑る。
両目の瞼、額、鼻の上、両頬と来て、小さく俺の唇に柔らかいものが触れた。
羽毛のように軽くて薔薇の花びらみたいなそれは、確認するようにゆっくりと何度も何度も降って来る。
鼻を掠める甘い香りは、紅のつけてるコロンかな。
俺は我慢できなくなって、腕を隣の紅の首に回した。
途端、紅の体が硬直して、また弛緩して、俺に応えてくる。
紅のキスは、甘くて優しかった。
俺を労わる様に、包み込む。
舌を絡ませてお互いの味を堪能する。
長い長い間、俺達はキスしていた。
先に体を離したのは、紅だった。
「これ以上したら、俺暴走しちゃうよ」
舌なめずりしながら、小さく微笑む。
その姿がちょっとだけ色っぽくて、俺も微笑み返した。
「悪い。でも、良かった......」
唇を噛んで、俯いて、俺は腹を括った。
タクシーの中で考えていた事。
紅が俺に頼んだみたいに、俺も紅にしか頼めない。
俺は目を瞑り、意を決して心の中に宿らせていたわだかまりを口にした。
「紅、俺を女として抱いてくれないか?」
言った瞬間、俺は紅に肩を掴まれた。
「理由を教えてくれないと、フェアじゃないよ翠」
たまらなくなって俺は目を開くと、たしかな情熱をくすぶらせた眼がまっすぐ俺を見つめていた。
「俺......鷹男の事が好きかもしれない」
「そうなの?」
紅のヘイゼルの瞳が翳る。
「わかんねえ。でも、気付くと鷹男とのキスの事ばっか考えてる」
「酷いね翠。そんな事平気で俺に言えるんだ」
苦痛に整った顔を歪ませて、紅は囁く様に低く呟いた。
「悪い......だから誰かに違うって言ってもらいたくて......」
俺はこれ以上紅を見ていられなくて、彼を押しやり顔を背ける。
「兄貴は、誰も好きになったりしないよ」
背後から、うなじ辺りに息がかかる。
俺の首の後ろの髪の毛がふわっと揺れた。
「兄貴は世の中の男の欲しい物全て手に入れてるから、女の人に何も求めてないよ。愛だの恋だのって感情に流されたりなんてしないと思う。必要なのは、妻の務めを無難にこなせる飾り物みたいな奥さん位じゃないかな」
俺が黙っていると、紅は続けた。
「じゃあ聞くけど、翠は兄貴を想って眠れない夜を過ごした事ある?体が疼く事ある?一緒に居る度にドキドキして緊張して、いつも通りの自分が出せない時とかあった?」
「クソッ」
俺は俯いたまま、悪態をついた。
違う。
そんな感情じゃない。
そんな感情じゃないんだ。
わけわかんねえ。
ポタッと腿の上で硬く握った拳の上に温かい滴が落ちる。
首筋を掠っていた生ぬるい息吹が、耳のすぐ後ろに当たった。
腕が廻され、後ろから抱きしめられる。
「俺はあるよ。翠に対して、いつもそうだから」
ひどく掠れた声で囁かれて、俺の体に電流が走ったみたいに激しい衝撃を感じた。
「後悔、しないで......。俺ならきっと翠を理解して、幸せにしてあげられるから......」
紅の指が鎖骨から辿って俺の大きく開いた襟ぐりに侵入する。
「ああ......」
俺はゆっくりと頷いた。