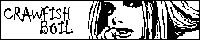黙っていれば、芸能人以上に目を引く華やかな何かを持っている。引き連れていても、俺の影に隠れるような女じゃない。
弊社の夏コレのモデルとして紹介する傍ら、周りがどのような反応を見せるのかも楽しみだった。
案の定、エルセーヌから現れた佐々木翠はこれ以上無いほど仏頂面をしていた。
髪の色と同じ茶色がベースの、胸の前が結ばれている膝上のドレスを着て、髪の毛はいつものように無造作に中央に立てているのでは無く、外はねのようなカールがついている。
化粧も嫌味が無く、オレンジがベースで、完璧だ。
俺は上から下まで佐々木翠を観察し、頷いた。
「なんで鷹男までタキシード着てんだよ。俺達仮面舞踏会にでも行くのかよっ」
待たせてあるリムジンに乗り込むと、彼女は腕を組み大股開きで座った。
「ったく。美容院かと思いきや脱毛とかネイルとかわけわかんねえ事させられて、しまいにはこのヒラヒラドレスだよっ。胸元スースーするっ」
「下着が見えているぞ」
「知った事かっ。んで、どこに行くんだよ。こんなババアちっくな化粧までさせられてっ」
「EF(エフ)と言う雑誌は知ってるか?」
「ファッション雑誌の?」
「その慈善パーティーだ。会費が一人三十万もする。俺の金を無駄にするなよ」
「さっ......三十万!!」
目を見開いて驚きを露にする佐々木翠を見て俺は苦笑する。
「もったいねえっっ。パーティーにんな金払って出るなんて!!」
「付き合いだ。お前もよく社交術を学ぶんだな」
「社交術ならとっくに有るっ!」
「ならば、その大股開きも止めろ。お前をうちの夏コレのモデルとして紹介するから、出来るだけ女らしくしていろ」
「わたし、って言ってればいいのか?」
「そうだ」
俺はミニ冷蔵庫を開いてシャンペンを取り出す。
「場所はどこだよ?」
「横浜の遊覧船を貸しきったそうだ」
「遊覧船?!!すっげ!!食いもんは?」
「お前が食べた事の無いような物が色々とでるだろう」
「うわっ超ーーーー楽しみだぜ!三十万円分食ってやる!」
さっきまで仏頂面だった佐々木翠の顔に笑顔が広がる。
俺はシャンペンを注いで口に運んだ。
1時間程すると、目的地についた。
案の定、デザイナーやら俳優やらモデルやら関東近辺の有権者らで溢れかえっている。
人ごみのなかを鋭く観察し、俺はビジネス用の笑顔を作って顔見知りに挨拶に回った。
その間、佐々木翠は中央のテーブルの上の食べ物を一つずつ手に取り、舌鼓を打っていた。
誰かが話しかけてこない限り、彼女は時折感想らしき独り言を呟いては黙々とそれらを食べている。
俺は人と話しながらも、常に佐々木翠を視界に入れていた。
必要ならば、紹介もしなくてはならない。それに、迷子になられても迷惑である。
数人の男が彼女に話しかけ、つまらなそうに去っていくのも目撃していた。話しかけてくる相手が女だった場合、彼女もにこやかに対応しているようだが。
やはり、女の方がいいらしい。
俺は目の端でその光景を捉え、鼻で笑う。
同性愛者という割には、俺の体によく応えるようになっていた。
この6ヶ月、ベッドの上で何度俺は理性を失いかけたか。
それに、彼女の度胸にはたまに度肝を抜かれる時がある。
一瞬の躊躇いを見せはしたが、あの花瓶の中身を、ただの水か何かのように一気に飲み干した。
その直後の、あの妖しい笑み。
あの時、俺はどうしようもなく動揺していた。
彼女が取り込んだ不浄物を、穢れを取り去ろうと必死になっていた。
何よりも、彼女の中を俺の白い情熱で満たしたい欲望の波に襲われた。
俺とした事が、現実と妄想の境の区別すら出来なかった。熱情に突き動かされ、経験の少なかった若い頃のように彼女を抱いていた。
それだけ、あの行為に酔っていた。
窓の向こうから差し込んできた黄昏が、気だるい橙色に船内を照らしだす。佐々木翠は食事を楽しみながら、時折退屈そうに夜の広がりをみせる外の方を眺めていた。
数人が彼女と一言二言会話を交わし去って行った所で、上品な身のこなしの、明らかに外国人の老人が彼女に近づいた。
不機嫌に対応しているのが傍目でもわかる。
だが、その老人は諦めず熱心に彼女に話しかけていた。
言葉が通じないのか、佐々木翠も身振り手振りで対応している。
しまいには、俺の姿を探し出し、目で合図を送ってきた。
「すみませんが、連れが呼んでおりますので失礼いたします」
俺は話をしていた取引先の連中に会釈をし、佐々木翠の方へ向かった。
「連れに何か御用でも?」
俺は老人の背後に回り、訊ねる。
「おおっ!!」
老人が嬉々として振り返った。
「この子に通訳してくれないかね。君はモデルか、と」
強いイタリア語訛りの英語で老人が答える。
「うちのモデルをやってもらっておりますが......」
俺は名刺を取り出して、老人に渡した。
老人は暫く俺の名刺を眺める。
「ブラボー!素晴らしい!あんたん所の製品は私も何着か持ってるよ。良いもんをつくっとるね。私はマリオ・トロバートと言う。トロバートという名はご存知かね?」
「ええ。イタリア製銀細工や宝石店の老舗ですね。私も何度か宝石を購入した事がありますが」
ファッションを知らなくても、その名前位聞いた事が有る。
「日本へはビジネスですか?」
「今度新宿に日本第2号店をオープンするのでね。ところで、この子をどこで見つけたのかね?」
「おいっ、何話してんだよ!」
佐々木翠がつまらなさそうに、会話に加わる。
老人は彼女に向かって
「ノープロブレーム!」
と酷いイタリア語アクセントで答えて、俺に振り返った。
「この子の所属しているモデルエージェントを教えてもらいたい。この子は中性的で男と女、東洋と西洋の美を併せ持っている!その上、こんなにも美しい銀色の瞳を持った子は見た事が無い!」
老人の大げさな表現に俺は内心苦笑しながら、翠が所属する事務所の名前を教えてやる。
こういう場所では、よくある事だ。
特に日本人は混血、という種に弱いらしい。
又は、憧れを抱いている、とでも言うのか。
現に自分も、20代までは訳の解らない連中から山のようにこういうオファーを受けていた。
流石に30を過ぎた今、『BREEZE』社の社名と俺の顔が知れるようになってからは、こういう誘いは来なくなったが。
「じゃあ、ベイベーちゃん。また会うとしようか」
トロバート氏は派手に音を立てて翠の頬にキスをし、数歩離れた場所で事を見守っていたボディーガードらしき男をを引きつれ、ふらふらとその場から立ち去っていった。
「な......何だあの頭のオカシイじじいは?!」
翠はゴシゴシと手の甲で触られた頬を擦りながら、俺に訊ねる。
「化粧が取れるからそれ位にしておけ。あのご老人はお前がモデルかと聞いてきた」
「へ?モデル?なーんだ、俺が最後の一個のフォアグラじじいが取る直前に奪ったからイチャネンつけてきてるのかと思ってた」
「馬鹿かお前は」
「悪かったなあ!外国語分かんねえんだから仕方ないだろ!」
「そんなナリだから、『外国語を喋ってみろ』などと周囲に言われたり冷やかされて育ってきたのだろう」
「そうだよっ。何で知ってんだよてめえがっ!!」
佐々木翠が怒りと困惑が混じった目で俺の顔をマジマジと見る。
「俺もそうだったから、分かる。お前の通ってきた道は、俺も大概通ってきた」
怪我の事も含めてな、と付け足す。
実際、彼女を見ていると20代の若造だった自分と重なる。
嫌になる程、彼女の行動や思考が手に取るように解るのだ。
お前を見ていると昔の俺を見ている様だ、とは言わなかった。
その代わり、いつもの笑みを浮かべる。
「下でセレモニーが始まる。行くぞ」
俺は呆けたように自分の顔をじっと見つめ続ける佐々木翠の腕を取って、誘った。
「さくらとの婚約を近々解消する予定だ」
帰りのリモの中で、ネクタイを緩めながら独り言のように俺は呟いた。
実際の所、俺のみならず父親も含めた門田家はこの1週間、彼女の父親関連で忙しい毎日を過ごしていた。
「ふうん。そうか」
佐々木翠は頬杖をついて窓の外を眺め、さして興味も無さそうな返事をする。
「さくらさんの親父さんに、何かあったんだな」
「先週の金曜日亡くなられた。新聞を読まないのか?」
「新聞なんて買ってねえし読んでねえよ」
「経営学を勉強しているのならば、毎日読むことを薦める」
「へいへい。オヤジくせえんだよ、鷹男はっ」
「お前はさくらに好意を寄せていたのだろう?」
「ああ、けどもうとっくに諦めた。お前も6ヶ月以上前に諦めろっつってたろ?契約の一部だったろ?それに、この間彼女の婚約者って男にも会った」
「ブライアンか」
「そう。そいつ」
相変わらず窓の外をぼんやりと見つめながら、佐々木翠は相槌を打つ。
「さくらさん、幸せそうだったし、それが一番良いんじゃねえか?お前、女なんて吐いて捨てるほど居るんだろ?」
「困らない程度にはな。お前も、男はどうだか知らないが、女には困らないだろう?」
その言葉に、佐々木翠は弾かれたように俺を見る。
その目が如実に怒りを表していた。
「てめえのせいだよっ」
「何の話だ?また、重要な部分が抜けているぞ」
「てめえがキスなんてすっから悪いんだっ」
「キスと女にもてる事と、どう関係する?」
佐々木翠は一瞬うッと声を詰まらせ、横を向く。
「てめえがキスなんてすっから、てめえの事しか考えらんねえんだよ、ちくしょうっ!!!」
そう言い捨てると、「ああ!」と言って佐々木翠は頭を抱え込んだ。
「お前まさか、あんなキスごときで動揺しているのか?」
「してるよっ。すんげー、してるよっ!お前の事好きになっちまったんじゃねえのかって自分で自分の頭ン中疑うくらい、動揺してる」
「あのキスは単なるお遊びだ。言わなかったか?お前との関係は全て『契約』であり、俺の中では『ゲーム』だと」
俺はそう冷たく言い放つ。
「鷹男お前、そうやっていつも他人との境界線引いて生きてきたんだろ?」
暫く頭を抱えて俯いていた佐々木翠が、上目遣いに俺を睨んだ。
「今、鷹男が境界線引くのが見えた」
俺は「ほう」と眉根を上げる。
この小娘に、何が分かる。
「お前は、俺に何を望んでいるんだ?」
思った以上に険しい顔つきをしていたらしい。
佐々木翠が、ふいに視線をそらした。
「別に何も望んじゃいねえよっ。俺はお前の引いた境界線の中に入ってくつもりはねえ。お前が望まねえ限りは。けどな、お前の都合で俺を振り回すんじゃねえ。迷惑だっ」
大学の寮に着くまで、むっつり顔で意地でも俺と視線を合わせない佐々木翠を眺めながら、俺はアルコール度がいつもより高めのジントニックを味わっていた。