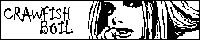「痛ってえ......何すんだっ......ぶわっ」
「口を濯げ」
俺の言葉に素直に従って、佐々木翠はシャワーの水で口を濯ぐ。
数度水を口から吐き出すと、俺は佐々木翠を抱きしめた。
「なっ......何だよ!!はなせっ!」
暴れる佐々木翠を、抱きこめる。
「馬鹿か、お前は!」
「馬鹿って、てめえがやれっつったんだろっ」
「真に受ける馬鹿がどこにいる!」
「何だよ、いっつも変な事強要してくんだろーがっ。鷹男の変態行為は今に始まった事じゃねーだろっ」
俺は自分でもこの行為の理由が悟れないまま、暫く密着した彼女の体の体温を感じていた。
開放してやると、佐々木翠は大きく安堵の息を吐く。
俺は石鹸を取り、彼女の裸の体に塗りつけた。
「何でだよっ」
小さく佐々木翠が呟く。
「何がだ?」
「さくらさんと寝た事あんだってな」
俺は屈んで無駄な脂肪の無い女の背中に石鹸を擦り続ける。
「ああ、昔な。それがどうした?」
「優しかった、っつってたぞ」
「それは良かった。優しくしたつもりだったからな」
「なら何で俺には変態ちっくな事ばっかやらせんだっ」
佐々木翠が振り返る。
顔に付いた水滴が輝いている。
自分の周りには、化粧の完璧な女しか居ない。
しなを作り、着飾り、香水の匂いをこれでもかとばかり振りまき、女という武器を最大限に利用しているような輩ばかりだ。
水に濡れていても全然変わらないのは、佐々木翠が普段化粧をしないせいか。
水滴がしたたり落ちている、長く濃く縁取られた睫毛や整った眉を眺める。
その間の、薄墨色の瞳が感情的に翳っている。
「お前が面白いからに決まっているだろう」
俺は低い声でそう返し、彼女の胸へ手を伸ばす。
親指で頂を擦ると、ビクッと反応した。
「俺はお前の実験台かっ」
佐々木翠は自分の体から泡を掬い、俺の胸に塗りつけた。
彼女の手が這い、適当に胸から腹の方までそれを伸ばす。
「そうだ」
「キ......キスもか?」
俺は佐々木翠の体を這っていた手を止め、彼女に石鹸を手渡した。
俯いている彼女の顎に手を置き、上向かせる。
驚きに目を見開いた彼女の顔は、耳まで真っ赤になっていた。
どういう事だ?
俺は目を細める。
「さ、さくらさんが、お前は本気の相手としかキスしねえって言ってた」
「ああ......」
そういう事か。
彼女の動揺の意味を悟り、唖然とする。
俺は嘘をついた。
「あの当時はな」
そう言って、佐々木翠の唇を塞ぐ。
「ん......」
「暴れるなよ」
唇をつけながら、俺は忠告を忘れない。
シャワーの水が雨のように俺達を濡らしながら、その下で激しく唇を重ねた。
舌が、唾液が、水が、絡み合う。
熱い絹のように互いの口の中を探り、舌をなぶる。
柔らかい唇を堪能し、歯列の裏や舌の届く範囲を舐め続ける。
佐々木翠も、同じように俺に応える。
俺はキスをしながら、どうしようもない衝動に駆られた。
下半身に集まる血流が満たされると、俺は彼女の体を抱き上げ立ったまま貫く。
難なく挿れられたという事は、相手も感じていた証拠だ。
その行為中、唇は離さなかった。
上と下で、佐々木翠の中に侵入する。
「あっ......んぁ.........ああっ」
翠が声を漏らす。
激しく腰を突き上げ、包み込んでくる快感と戦っていると、俺の男を包んでいる佐々木翠の中が一段ときつく締まった。
「んあああっ!!鷹男っっっ!!」
悲鳴に近い翠の声を聞き、俺は彼女の体から欲望を抜き取った。
激しく佐々木翠を抱きしめる。
二人の体の間に放たれた精が滑らかに、そして熱く満たした。
帰り支度をしている佐々木翠を見つめながら、俺はふとある事を思い出した。
タオルを腰に巻き、ベッド横の電話を使い森尾に確認の電話をする。
カーキのハーフパンツにTシャツという色気のいの字も無い格好になった佐々木翠は、腕を組んで俺が電話を切るのを待っていた。
「森尾か。来週の金曜の夕方エルセーヌの予約を入れておいてくれないか。ああ、それには行く。8時からだろう?ああ、そうだ」
電話番号と住所を備えてあるメモ帳に書き付けると、俺はそのメモを佐々木翠に差し出した。
「何だこれ?」
俺の出したメモを眺めながら、女は首を傾げる。
「来週は、4時にそこへ向かえ」
「4時?早くねえか?しかもこれって、美容院?」
「まあ、スパのような場所だ」
「ふうん」
訝しげな表情で俺とそのメモを交互に見やりながら、佐々木翠は俺の前に対峙する。
挑戦的に俺を見上げた。
「何だ」
「良い事教えてやろうか」
銀色の目が悪戯にキラリと光る。
俺は押し黙ったまま彼女を見下ろした。
顎で先を続けるよう促す。
「俺も、同じだよ」
俺は目を細める。
言っている意味が解らない。
「何が、だ。言葉が成立していない。何が同じなんだ」
「だから、キス」
「キス?」
「俺もキスだけは本気の奴としかしなかった。.........お前から奪われるまでは、な」
ぞんざいに笑みを零すと、佐々木翠はくるりと踵を返す。
突然の告白に意表を突かれた俺は、
「堪能してもらえたなら、光栄だが」
と彼女の後姿に声をかけた。
心なし、唸るような低い声が出たのは誤算だったが。
ドアを閉める前、佐々木翠は一瞬俺を険しい瞳で捕らえた。
まるでその銀の眼が何かを語っているようだった。
「ごちそうさま」
そう言うと、彼女はパタンとドアを閉めた。
俺は長い間そのドアを睨むように眺めていた。
その夜、秘書の森尾から電話があった。
石田先生がお亡くなりになった、との悲報の電話だった。