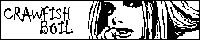自分を覗き込むように千姫が隣に座っている。
四雲は、人の気配すら察知出来ない自分を呪った。
「何か用か」
昨日よりいくらかましになった喉からは、明確な言葉を発する事が出来た。
彼女は涙で人形のような顔を濡らしていた。
大きな瞳から零れ落ちる滴を拭いもせず、ただひたすら一点を見つめていた。
だが、死雲の問いかけに我に返ったように息を飲む。
「申し訳御座いません。貴方の守り神様とお話をしておりました」
刺繍が見事に施された絹の袖でその涙を惜しげもなく拭うと、平静を装って千姫は声を絞り出した。
「守り神、だと?」
怪訝な声で問い返す四雲に、慣れているのか千姫は構わず続ける。
「ええ。失礼ながら、あの...貴方の過去を拝見させていただきました。......それがあまりにも孤独で悲惨なものだったので、つい......」
無言の四雲に戸惑ったように言葉を詰まらせながら、千姫は更に続ける。
「耳が茶色くて、白い狼のような犬が、あなたの周りを心配しながら飛び跳ねております。それと、数十にも登る青白い人間の顔が...」
「ほう?」
鼻を鳴らして、あからさまに嘲りを含んだ声で聞き返す。
この女。
頭が弱いのか、狂っているのか。
「貴方、一体何人罪の無い人たちを殺めたのですか?」
どうせまだ体は思うように動かない。
この女の阿呆で馬鹿げた話に付き合ってやろうか。
「数え切れん」
四雲は鼻を鳴らす。
「貴方の昔のお友達......」
ええと、とつけたし、眉間を寄せながらしばらく宙を眺める。
「友達の...名前を...や、やたろう?......いえ......」
「夜叉が心配している......きゃあっ」
夜叉、という名を出した途端、眼に見えない速さで四雲に胸倉を掴まれ引き寄せられた千姫は、寒い冬の冷え返った夜空のような冷たい顔と今にも息がかかりそうな距離で対峙していた。
その硬い氷のような双眸に吸い込まれそうになる。
思わず、息を詰めた。
そして、この汗臭くやつれて汚い男の無精髭の奥に隠れている美貌に動悸が速まる。
薄い二つの瞳の中に、自分が写っている。
熱い息が、体温が、彼の鼓動すら伝わってくる。
「妄言を吐くな」
男は無表情のまま、千姫を突き放した。
仮にも徳川家の血を引く姫に対し、打ち首にも値する扱いだが、その瞬間何かが見えたのか、千姫は横に倒れたまま惚けたように宙を見つめていた。
四雲の、
「少し寝かせろ」
との一言が無かったら、いつまでも宙を見つめていたかもしれない。
我に返った千姫は、やおら顔を赤らめそそくさと退室した。
「なんということを......」
退室した千姫は、そのまま閉めた戸を背にもたれた。
男の双眸に捕らえられた瞬間、見えたのだ。
太陽に照らされた赤と黄金で煌めく道を、とても美しい女性が歌を口ずさみながら歩いている姿を。
ひらひらと舞い降りる金の雨の中、その美しい人は朝から何刻もそこで誰かを待っていた。
そしてそれと同じ間。
自分も彼女から見えない場所で、ずっと息を殺しながら、気配を消しながらその様子を見守っている。
私はこの寂しい瞳を持った男として、何かを見ていた。
そして、溢れ出す湧き水のように、男の心の言葉が届いた。
即ち、迷い。
姿を現すべきか否か。
この瞬間、彼の人生が決まる。
彼は再度、天を仰ぎ見る。
太陽の光を照らした黄金の紅葉が、風に揺れてさわさわ音を立てる。
銅色の輝きが一斉に飛び散る。
解れた髪が、一房目にかかった。
そして。
「少し寝かせろ」
との男の一言で、私は我に帰った。
初めてだった。
他の人に見えない者や物が見えていたせいで、幼少の頃から周りに気味悪がられ育ってきた。
何を言っても信じてもらえないので、やがて口にするのは控えるようになった。
だのに、この男の場合、あまりに不気味で恐ろしいものを連れ持っていたので、つい口が滑ってしまった。
垣間見えた過去があまりにも辛すぎて、悲しすぎて、途中で止められなくなってしまった。
そして、初めて私は『先見』をしてしまった。
あの美しい女の人は、この男の想い人なのだろうか?
千姫は胸を押さえる。
まだ動悸は納まりそうに無い。
千姫は、戸にもたれたまま、座り込んだ。
豊臣家に秀頼の正妻として嫁いだ時も、初めて彼と共寝をした夜も、このように胸は早鐘を打っていなかった。
彼には贔屓の側室が居たし、それに何より大叔父の策略の一つ、政略結婚という事実と持ち駒としての自分の立場をを彼女は女ながらに充分踏まえていた。
前の夫のことを考え出した途端、喉に痛みが走った。
思わず両手で喉を押さえる。
まるで鋭い刃で切り付けられたように、首が痛くて息が出来ない。
掌に、ぬるぬると滑った温かい感触。
そして、目の前には今しがた話をした男の夜叉のような姿。
それが幻の感触であっても、彼女にはまるであたかも現に起きたような感覚を味わう。
彼の人が持つ刀が振り落とされ、目の前に赤い飛沫が飛び散り、私の視界が回転する。
「やめてっ」
きつく目を閉じて、九字を唱えた。
「私にそのようなものを見せないで!」
いつか旅の行者が千姫に教えてくれたまじないだ。
大抵の悪霊や怨念はこれで消えてくれる。
薄れ始めてはいるが、喉の痛みと重い頭痛が完全に消えるまで、千姫は薄暗い部屋の中で、ずっと呪文を唱え続けた。