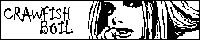「それは傍から見たらただの我侭よ。」
久々に半日のオフがあった私は、今日久しぶりに学生時代からの友人、弘美の家に招待された。
彼女は大学卒業後、こちらの不動産王と結婚して幸せな家庭を築いていた。
「我侭…かしら?」
私はブルマン100%のコーヒーを一口口につける。
でも、正直その一言に胸が一瞬締め付けられた。
弘美はシフォンケーキを頬張りながら続ける。
「そうよ。二兎追うものは一兎を得ずって諺、もちろん知ってると思うけど、あなたの美形の秘書さんの事も、岸さんの事も遊びならいいのよ。でもね、どちらもキープしていたいなんて、そんな虫のいい話は無いわよ。」
「そう…よね。」
苦々しく頷いて、コーヒーをカップに置いた。
弘美は身を乗り出す。
「ね、貴女最近日本の週刊誌読んだ?私気になった記事を見つけたんだけど。」
「そういうものにはあまり興味がないの。読むだけ時間の無駄だわ。」
とあまり興味を示さない私などお構い無しに、弘美は部屋を横切って雑誌を置いたラックから一冊本を取り出した。
「…有名女優の恋愛スキャンダルの話なんだけれどね。ここ、ここ。この写真に写ってる男の人の顔…目元のモザイクがジャマだけど、誰かに似ていない?」
『人気女優寺内祥子(38)、深夜の密会!!彼女の若いツバメの正体は?!』
と大きな見出しの横に載っていた男女の写真に私の目は釘付けになった。
思わず息を呑む。
そこに映っていた男性は。
スーツ姿では無くとも、目元のモザイクが無くとも、私には一目瞭然だった。
「仁神堂…。」
何処かのバーの前で周りを気にしながらその女優と車に乗り込もうとしている彼の姿があった。
私は目で記事を追う。
「若いツバメの正体は、一流企業勤務のNさん。もう、これだけでも誰だかバレバレじゃない。」
弘美の言葉を無視して、一気に私は記事を読み終えた。
雑誌が刊行された日を確認すると、仁神堂が私について日本へ帰国した週の丁度一週間後だった。
ドキドキと動悸が早まっているけれど、それを億尾にも出さず私はそっと雑誌を閉じる。
「…ショックだった?」
弘美は私を気遣ってオズオズと声をかけた。
「こういう事、英恵に知らせるべきかどうか迷ったんだけど、貴女彼の事本気になり始めているみたいだし、そうでなくとも上司としてこういう部下のスキャンダルは知って置くべきなんじゃないかと思って…。私、余計な事してしまったかしら?」
私はクラクラと眩暈を感じる頭を抑えて頭を振った。
「いいえ…そんな事無いわ。…教えてくれて有難う…。」
弘美は、ほうっと溜息をつく。
「英恵が本気になってしまって、後で傷ついて欲しく無いのよ。もしかしたら…向こうはただの遊びだと思っているかも知れないし。ほら、貴女昔からそういう野心家の男に利用されてたじゃない?私は…。」
「ええ。分かってるわ。昔から私は弘美に心配ばかりかけてたわね。でも、大丈夫よ。仁神堂との事は別に本気でも何でも無いから…。私も、割り切っているし…。」
私は弘美の言葉を遮って、身支度を整え始めた。
そろそろ時間だ。
「久々に弘美と会えて楽しかったわ。でも、また社に戻って仕事をしなければね。貴女の家もニューヨーク郊外にあるんだから、たまには私のコンドにも遊びに来て頂戴。」
他愛ないお喋りが気まずい話題で終わってしまうのに罪悪感を感じたのか、弘美はまだやり切れない表情をしていた。
「あのね、英恵。私は貴方がどんな決断を下しても味方だけど…。でも、もう傷つかないでね。ちゃんと自分の気持ちに正直になって頂戴。」
自分の気持ちに正直に。
そんな彼女の言葉をかみ締めながら、私は笑顔で友人に別れを告げた。
社に戻った私は、早速仁神堂と鉢合わせしてしまった。
社長室に戻ろうとしていた私を、彼は呼び止めた。
「社長、お帰りなさいませ。例の取締役会議の件ですが…。」
「あ…。」
振り返ると、書類を抱えた仁神堂と目が合った。
途端に、目を逸らしてしまった。
「………。」
「わ、分かったわ。今から目を通します。」
そのまま社長室のドアを開けて中に入った私を追って、彼も無言で入ってくる。
彼は書類を私のデスクの上に置くと、そのままデスクの前に立ち尽くした。
「……あの、もう用は無いはずよ。何かしら?」
私は平静を装って書類を読んでる振りをしながら、彼に問う。
「それは、私の台詞です。何かあったご様子ですが?」
仁神堂は、私から納得の行く答えを聞くまで梃子でもここから出て行かなさそうな雰囲気だ。
「午前中のオフに何か?社長はまた何かに動揺していらっしゃるようですね?」
私は俯いたまま、考えた。
彼は知っている。
めったに動揺しない私が動揺する理由が一つである事を。
この男が絡むと、本当に調子が狂う。
彼に、あの雑誌について問い質そうかどうか迷ったが、鎌をかけてみる事にした。
「あの…。日本の週刊誌を読んだのよ…。」
私の頭の上から小さな溜息が聞こえた。
私はそのまま続ける。
「私は上司として、貴方の行動や私生活にとやかく言うつもりはないけれど…。」
「無いけれど?…何でしょうか?」
意外にも冷静で、落ち着いた声音の仁神堂に内心舌打ちする。
私に知れたので開き直っているのだろうか?
「でも、ああいった記事は社の信用にも響くから自粛してもらわないと困るわ。」
そう早口で言い放って、彼を見た。
仁神堂は真面目腐った顔で私を見下ろしていた。
そして、フッと表情を緩める。
「な、何かしら?」
私は真っ赤になって彼を上目遣いで睨んだ。
「いや、社長があの様な記事をお気になさるとは…私としては意外で驚いているのですよ。」
「それ…は、どういう意味かしら?」
私は彼の優しい瞳から目が離せず、じっと見つめた。
「社長ほどの方が、あのようなくだらないタブロイド誌を信用なさっておられるのには驚きです。確かに、私はあの方と過去に関係を持っておりました。だが今は只の友人です。」
過去に関係…。
今は只の友人…。
その言葉が私の頭の中でこだまする。
仁神堂は、
「他にご質問は?」
と訊ねると、眼鏡の縁を押さえた。
「信じる信じないは社長のご自由にどうぞ。もうあのようなヘマをするつもりもありませんが、社長にご迷惑がかかるのであれば友人であっても彼女とは以後会いません。」
以後会わないなんて…。
何もそこまで彼の生活を規制する権利は私には無い。
けれども、もう彼女と会って欲しくないと願うもう一人の自分がいて…。
「それより。」
仁神堂の一言で私は我に帰った。
「?何かしら?」
私は小首を傾げながら仁神堂を見上げる。
仁神堂はまた無表情で真剣な顔になっていた。
「今夜お時間がおありでしたら、一杯如何でしょうか?」
そのまま彼は私に熱心な視線を向け、私の答えを待った。
これは…誘い、なのかしら?
クリスマス以来、彼と仕事外で会っていない。
仕事が忙しく、私生活に全くゆとりが無かった。
「いい…わよ。何時になるか分からないけれど。」
と私が返事をした途端、
「そうですか、それではまた後で。失礼致しました。」
仁神堂は顔に笑みを浮かべて、そのまま踵を返して部屋を出て行った。
久々に見た仁神堂の笑顔だった。
ニューヨークは地下鉄を利用した方が、車を使うより早く目的地に着く事が多い。
だから、ニューヨーカーはあまり車を持っていない上、徒歩を好む。
久々に出張も残業も無く帰宅が許された私に、
「私が運転しますから。」
と、愛車のメルセディスベ〇ツのキーを振って見せた仁神堂は、会社のビルの前で私をピックアップすると、そのまま車を走らせた。
案の定…と言っては何なのだけれど。
私の推定どおり、彼の車はセントラルパークのすぐ傍の某ホテルの地下駐車場の中に入っていった。
彼は最上階から二階下のセミスイートを住居として生活していた。
「どうぞ、お入り下さい。」
と通された部屋は彼らしいと言うか、隅々まで無駄を省いたシンプルなデザインの装飾が行き届いたお洒落な所で。
ガラス張りの窓で覆われた部屋からは、ニューヨークの夜景が堪能できる。
眼下にはセントラルパークの緑溢れる風景が広がる。
きっと仁神堂はここでジョギングをしているのだろう。
「素敵な所ね。」
私は思わずそう口に出していた。
彼は私をリビングに通すと、スーツを脱ぎ捨てシャツの袖を捲くり、ネクタイを緩めて隣に設置されているバーカウンターへ向かった。
「有難うございます。社長は赤と白どちらの気分ですか?」
まだ部屋のなかをキョロキョロしている私に仁神堂が声をかける。
「あ…どちらでもいいわ。」
私は彼のリビングの床に置かれている、ノーマン・ロ〇クウェルの絵に釘付けになった。
「これは…本物ではないのですが、とても気に入ったので購入しました。彼の絵は…こう、テーマがハッキリしていて、細部にまで気を使っていて、好きなんです。」
「そうね。」
彼の絵の説明を聞いていて、仁神堂みたいだわ、と私は思った。
きっと彼を絵に表現したら、こんな感じなのだろうか。
隅々まで気配りが行き届いていて、テーマ性のある…。
そっと私の目の前に赤ワインが出された。
私の前のソファに彼は腰掛ける。
「貴方とは…。」
「社長とは…。」
二人同時に声を出してしまう。
「…。社長からどうぞ。」
仁神堂はワインそう言ってワインに口をつける。
「え?ああ、あの、貴方とは殆ど毎日顔を合わせているけれど…こうやって仕事以外でゆっくりするのは久しぶりだと思っただけよ。」
「私も、同じ事を言おうと思っておりました。」
私は無言でワインに口をつけた。
暫しの沈黙の後、仁神堂は単刀直入に切り出した。
「今日、カリフォルニアの岸様から本社にお電話がありましたよ。」
突然彼の口から零れ出た岸さんの名前に、私はワインを噴き出しそうになった。
「え…?」
仁神堂は、そっとワインをガラス張りのテーブルに置く。
「社長はこの所彼の電話にあまり出ないそうですね。」
仁神堂の言う通り。
私はここ数週間、岸さんを意図的に避けていた。
岸さんの声を聞くと、私の心の良心が痛むから。
弱虫で意気地なし。
私は彼を傷つけるのが怖くて、未だ持って別れ話を告げる事が出来ないでいた。
きっと彼は心配になって本社に電話してみたに違いない。
「それは…私と岸さんの問題で…。」
貴方には関係ない。
と言おうとすると、
「自惚れてもよろしいのかと。」
との言葉に遮られた。
仁神堂はもう一度ハッキリした声で言う。
「それは、私に分があると思って宜しいのかと。」
途端に、私達の間に緊張感が漂った。
「私は、こう見えても独占欲の強い男なのですが…。」
仁神堂はテーブル越しにワインを持っている私の手に触れた。
指先から、彼の脈動を感じる。
それは、私の鼓動と同じくらい速く打っていて…。
私は彼の薄い瞳に宿る熱情の炎を直視する事が出来なかった。
でも、確信をもって彼に一言告げることが出来た。
「岸さんとは…もう多分会わないと思うわ。だから…。」
だから、焦らせないで。
仁神堂は無言で私の手の中のグラスをとってテーブルに置く。
そしてまた唐突に、唇を塞がれた。
角度を変えて侵入してくる、彼の暖かい舌を感じながら…。
「あの夜から、ずっと貴方とこうしたかった。」
耳元で彼の切なそうな声が聞こえたような気がした。
私が今まで見過ごしていた、彼の独占欲の強い男としての一面を初めて見た夜だった。