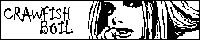何ヶ月ぶりかに降り立った東京は、雪は無くともニューヨークと同じくらい寒くて乾燥していた。
幸いな事にあの夜から特に変わった様子も無く、仁神堂は私と普通に接していた。
たった一夜の迷いごとで悩む年頃じゃないじゃない、と自分に言い聞かせても、やっぱりあの日以来私の彼に対する言動は微妙にぎこちない様な気がする。
今回、私は東京本社の祖父に呼ばれて七日間だけ里帰りをした。
その間、日本各地で重役会議やら日本女性の世界的活躍に関する講演(私は出たくなかったのだが、仁神堂が勝手に決めてしまった)やら、経済雑誌のインタビューなど年末にも拘らず予定は目白押しだった。
「お爺さま!!」
久々に実家の門をくぐった私が一直線に向かった先は、祖父のいる書斎だった。
松葉杖をついて不便この上ないが、しょうがない。
書斎の大きな机で仕事をしていた祖父は、顔を上げた。
もう七十を過ぎているのに新しい事が大好き、その歳で去年スノーボードまで挑戦してしまった飽くなき好奇心が、彼を実年齢より十歳は若く見せているのだろうか?
顔は皺くちゃで髪の毛は見事な銀髪なのに、背筋はピンとしていて老いを感じさせない。
去年会った時とまるで一緒であった。
祖父は眼鏡を外して私を見つめる。
「おお、英恵(はなえ)か!!久しぶりじゃな…。??どうしたんじゃ、そ
の足は?」
そう言いながら戸口の私の方へ来て、暖かいエネルギーに満ちた大きな抱擁をしてくれた。
「この間転んでしまって…。お爺さまは全然変わりないようで何よりだわ。」
ププッ、と自嘲気味に噴き出した私を庇いながら、祖父は私を傍の椅子へ座らせた。
「元気じゃぞぅ。今日はお前が帰ってくるからオフをもらったわい。お前も元気そうでなによりじゃ。ちょこっと痩せたみたいじゃがな。慈英は今研究所に篭っていて留守だが、夕飯までにはもどってくるじゃろ。」
慈英とは、私の弟だ。
私とは正反対で会社の経営には一切興味を持たず、研究所に篭って電気系統の研究をしている。
「では、夕飯の時会えるわね。」
祖父は深く頷いてから、口を開いた。
「秘書の仁神堂くんはどうしている?」
彼の名前が出てドキリ、とする。
「彼は…成田からそのまま横浜の実家に向かいました。」
「ほう…そうかね?彼も帰国したか…。ふーむ。」
祖父は顎に手を置いて暫く考え込んだ。
「日本の方はどうですか?」
私は沈黙を破って仕事の話を始めた。
途端に柔和だった祖父の顔が厳しくなる。
「お前も知っての通り不景気でな。クリスマスの売り上げも散々じゃった。まだ大きな煽りは受けておらんが、下請け会社は幾つか潰れてしもうたしのう。まあ、お前もこっちの状況は耳にタコが出来るほど聞いておろうが…。」
「ええ…。」
「実は英恵。今夜の夕飯の時に言うつもりなんだが、大事な話がある。それまで風呂に入ったりしてゆっくりしておいで。檜風呂は久しぶりじゃろ?」
ニコっと表情を和ませて祖父は深刻になりそうだった話を打ち切った。
「そうですね。」
私も松葉杖をついて席から立ち上がった。
「久々にお爺様に会えて、実家に戻れて嬉しいです。」
最後の祖父の言葉が気になったが私も祖父に笑顔を向けた。
「堅苦しいのは嫌いじゃ!!」
との祖父の我が儘で、私の実家の敷地内には和風の建物と洋風の建物の二つが建っている。
もちろん祖父は日本庭園風な屋敷の方が落ち着くのか、そっちの方に住んでいて、私と弟と今は無き両親は、洋館の方で生活をしていた。
もちろん弟はまだそっちで生活しているし、今夜の「夕食」というのは祖父の家の方で、という意味である。
時差ぼけで生じた眠気は、広くてゆったりとした香り良い檜風呂に入った後消え去った。
洋館の方の自室で秘書達や重役達に電話で指示を与えていると、メイドが呼びに来た。
夕食の用意が出来たので和座敷に来るように、との事だった。
「慈英!!久しぶりじゃないの!!」
人見知りが激しく(というより人嫌いで)滅多に顔を見せない慈英は、暫く見ない間に立派な若者になっていた。
姉の自分が言うのも何だが、顔は悪くない。
悪くは無いのだけれど…。
「お久しぶりです、お姉さま。」
端整な顔に品の良い笑みを浮かべて、慈英は挨拶した。
これで極度の電気オタクでなければ…といつも思う。
電気関係以外の事に関して、彼は何も興味を持っていないのである。
「相変わらず研究所に篭っているようね。」
「仕事ですからね。」
「彼女は出来たの?」
彼の人生二十五年。
女の「お」の字も聞いた事が無い。
絶対におかしいと私も思って昔こっそり調査をさせたけれど、そういう気は一切ないという。
「先日生まれて初めてお見合いをしてみました。」
「ええっ??女の子とまともに付き合ったことも無いのに、お見合いしてしまったの?あなたまさか…?」
驚きと不安は的中した。
「面白い方でしたので、結婚を前提にお付き合いしてみる事にしました。」
はあぁ、と私は深いため息をつく。
よく相手が承諾したものだわ。
いや、相手もお金に目がくらんで弟を落とし入れようとしているだけのかもしれない。
世間知らずの弟を持つとこういう事になるのね、などと思いながらも苦笑混じりに
「では、今度その方に会わせて頂戴ね。」
と言っておいた。
「おおっ、二人とも揃っていたか!!」
上機嫌で部屋に入ってきたのは祖父であった。
「今日は久々に家族が揃った事だし、料理長に頼んで飛びっきりのを作ってもらったからな。」
豪快な笑いと共に、国本家の晩餐は始まった。
「実はな、近い将来…まだいつとは言えんが、わしが持っている KUNIMOTO の株と経営権を半分お前に譲ろうと思っておる。」
食事も終わりに近づいたとき、祖父は単刀直入に切り出してきた。
「ええっ?」
私は驚いて箸を落としてしまう。
「いやな、まだ続きがあるんじゃが、そのあともう半分を……。」
そこで祖父はもったいぶるように間をあけた。
「仁神堂くんに譲ろうと思う。」
ガッチャーン!!と今度は持っていた茶碗まで落としてしまった。
辺りにご飯が散らばる。
仁神堂ですって?
今、仁神堂って言ったわよね?
何故そこであの感情欠落男がでてくるのかしら?
「お爺様!!何を考えていらっしゃるの!!!!」
私はダンッと両手をついた。
久々に、感情的になった。
「何って…会社の将来のことじゃが?」
「それなら…それならもっと真剣に考えてください!!なんでそこで赤の他人の仁神堂の名前がでてくるのですか!!」
「何故そんなムキになっとるんじゃ?お前も彼は仕事が出来ると褒めておったではないか?」
「それは…それは秘書としてであって…お爺様の気が違ったとしか思えないわ!!」
「お姉さま、一体どうしたのですか?そんな取り乱してみっともないですよ。」
落ち着いた慈英の声も耳に入らなかった。
祖父は一瞬口をつぐんだ。
言葉を選ぶように時間をかけながら、声を出す。
「家族経営なんてしてると、会社は今に潰れてしまう。そんなのは常識じゃ。わしは、仁神堂君の事は彼が小さい頃から知っとる。英恵はヘンリー夫妻を覚えておるか?」
「ヘンリー夫妻?」
昔、今は亡き父の元で働いていたアメリカ人のヘンリー氏とその日本人妻の事はうろ覚えにだが、覚えている。
数えるほどしか会ったことがないが、彼は父が祖父を助けてKUNIMOTO USA を立ち上げていた頃、個人秘書兼通訳をしていた。
でも確か父が飛行機事故で亡くなった時、同乗していて彼も亡くなったような…。
「母方の姓名を名乗っとるが、仁神堂君は彼の子じゃ。ミスターヘンリーは義一と一緒にあの日死んでしもうた……。申し訳なくってなぁ。あの事故以来わしがあの母子の経済援助をしていたんじゃ。」
今度は、私が口をつぐむ番だった。
大きな和室に、たとえようもない不気味な沈黙が広がる。
そういえば仁神堂は、両親はいない、と言っていた。
ならば…
「は、母親は?彼は両親は無くなったと…。」
何故こんなにもあの男の事が気になるのだろう?
内心そんな自分に苛々しながらも、聞かないではいられなかった。
「彼が高校生の時、亡くなられたよ。元々身体の弱い人だったからのう。生活の面倒はわしが見てあげたが、彼は頑張って自力で奨学金を得て大学、大学院へと進んだよ。」
「………。」
私は暫く言葉を呑んで祖父を熟視した。
「…でも、だからってそれが彼に経営権を与えるのと何の関係があるのですか?ただの同情じゃない!」
「彼の性格は熟知しておる。あんな頭の切れる男には滅多に出会るもんじゃない。TOPになる資格を充分備えておる。わしも一目置く男じゃ、お前だって理由くらい言わなくともわかっとるじゃろ?」
祖父は鋭い眼差しを私に向けたまま、続けた。
「我が社の将来には、どんな状況下においても冷静で正しい判断を下し、先を見る力を持っている人間が必要じゃ。お前には先を見る力があっても、今のように感情的になり過ぎる所がある。」
「でも!!!」
私は納得がいかなかった。
何故、仁神堂なのか。
そんな事、絶対に許せないわ!
私の中で怒りがふつふつと込み上げてきた。
祖父は小難しげな眉間皺を深く刻んだその顔を、軽く横に振った。
「その為に彼をわざわざ一時的にお前の秘書にしたんじゃないか。彼のお陰で色々助かっとるじゃろ?まあ今すぐという話ではないし、仁神堂君にもお前にもこれから何年もかけて学んでもらう事が山ほどある。しかし…彼もお前にはまだ何も言ってなかったとはなぁ。まあ、言うなと口止めしといたのはわしじゃが…。」
私は息を呑んだ。
あの男は、この事を知っていた。
知っていて、私に黙っていた。
馬鹿な私はそんな事も知らずに、一線を越してしまって……
「私は、嫌です!!断固反対です!!」
そう言い切ると、私は傍らの松葉杖を引き寄せ立ち上がった。
そのまま無言で部屋を横切って出て行く。
「お姉さま!!」
長い回廊にどすどすと杖と足音が響く。
出来るだけ早歩きで闊歩したけれど、この不自由な足が憎らしかった。
「お姉さま!!」
慈英が追いついてきた。
玄関を出た所で、私は立ち止まった。
「どうしたんですか、あんなに取り乱してらしくないですよ?」
私は洋館へと続く砂利道を慈英に支えてもらいながら歩き出した。
胸が苦しい。
「なんでもないのよ。ただ…お爺様のお言葉が信じられなかっただけだわ。」
足元の砂利を見つめながら微かな声を出す。
「あの、仁神堂さんの事ですか?話を聞く限りでは…凄い方のようですね。お爺様もかなりその方の事を高くかっているようですし。」
垂れていたこうべを上げて傍らの慈英の綺麗な横顔を顧みた。
「何考えてるんだかわからない腹黒い男よ。絶対認めないわ。」
「…僕はお会いした事がないので何も言えませんが…。」
慈英はそのまま口角をきゅっと結んで、無言で私を部屋まで送ってくれた。
仁神堂の日本の携帯に電話をしたけれど、圏外だった。
これは、驚き?悔しさ?それとも、怒り?
何故こんな気分になるのか分からない。
ただ分かっているのは…
仁神堂は知っていた、という事実。
私は翌朝彼を呼びつけた。